各国で感染状況が上下する中、ロックダウンを解除した国もあれば、感染状況が悪化した国もあります。家庭に米や豆類などの保存食を常備することは、流行中に免疫力を高めるだけでなく、新型コロナの軽症状の改善にも役立ちます。
家庭に必ず常備しておくべき3つの食品
日常的に使用する調味料や食材の中で、保存期間が比較的長いものを多めに保存しておくとよいでしょう。特に米、豆、乾燥キノコ類が重要です。
● 米
米は人々に好まれる主食であるだけでなく、おかゆにすると非常に良い薬膳料理になります。
米は白色の食品で、中医学では白色は肺に入り、肺陰を養うとされています。そのため、米のおかゆを食べることで肺を守ることができます。米のおかゆは脾胃も調整します。現代科学では、脾臓が免疫機能と密接に関連していることがわかっており、これは中医学の認識と一致しています。中医学では、脾臓と胃が健康であれば、より多くの気血が作られ、ウイルスと戦い、免疫力が高まると信じられています。
また、新米が古米になっても心配する必要はありません。古米は貴重な漢方薬の一つだからです。新米は熱性が強く、食べるとのぼせやすくなる人もいますが、古米はより穏やかです。
もし古米の味や香りが悪いと感じる場合は、チャーハンにすることで胃に優しい食べ方になります。作り方は生の古米を炒って黄色にし、保存しておいて、食べる時に洗って調理します。チャーハンをお粥風にして食べると、消化を助ける効果がある食品となります。
ただし、古米の保存場所は常に乾燥している所を選び、米がカビや変色しない様に注意しなければなりません。また、食べる前にお米の匂いを嗅いで、まだ香りが残っているかどうかを確認することも大事です。
● 豆
乾燥豆は保存しやすく、野菜を食べたいときは人為的に発芽させてスプラウトにすることでき、栄養価がさらに高まります。例えば、大豆、緑豆、エンドウ豆を水に浸けると、それぞれもやしになります。
ソラマメや落花生も発芽させることができます。ソラマメや落花生を一晩水に浸すと、先端から芽が出始めます。殻を取り除いて、料理や煮込みスープに使用できます。
中医学の観点から種子類の新芽は非常に栄養価が高く、芽のエネルギーは免疫力を高める効果があります。
発芽は生命を育むようなもので、すべての精華の気がそこに送られます。同時に、栄養も消化吸収しやすくなります。
当然、すべての食品の芽に栄養価があるわけではありません。いくつかの食品は発芽すると有毒になることもありますが、ここで紹介した豆類は安全で有益です。
● キノコ類
乾燥したキクラゲ、白キクラゲや椎茸などは保存が容易で、血気を補います。キノコ類は体の免疫力も高めます。
4種類の食材で解熱、新型コロナの軽症状を改善
新型コロナウイルス感染症のパンデミック期間中、医療機関の負担が重くなる状況下では、軽症患者は自宅で隔離・自己ケアせざるを得ないことがあります。そのため、家庭では症状緩和に役立つ食材を準備しておくとよいでしょう。
1. 緑豆
緑豆を水に加えて20分煮ると、緑豆水ができます。発熱初日に多く飲むことで解熱効果があります。
高熱が出ると喉が渇きます。これは体が戦ったり、邪気を払ったり、解毒したりしているため、大量の水が必要なので、水分補給をするように体が伝えているのです。しかし、この「水」は沸騰した水を指すのではありません。沸騰した水では十分なエネルギーが得られず、熱を取り除いて解毒する効果もありません。緑豆水がちょうど良いのです。
緑豆水を解熱に使う際は、発熱初日に可能な限り多く飲むことが重要です。次の日以降は、体が水分を補充したいと感じたら飲む量を減らすとよいでしょう。また、空腹時には小麦や米で作った薄い粥を食べることでエネルギーを補給し、ウイルスと戦う力を高めることができます。眠気が増す場合は十分に休息することも大切です。そうすれば、2日目には症状が改善します。
2. ショウガ
一部の人々は発熱とともに寒気(さむけ)を感じることがあります。体が寒気を感じるのは、体内が冷えている場合です。このようなときは、大きな生姜を薄切りにして水に加え、5分間煮ます。生姜を取り除いた後、大棗や少量の砂糖を加えて飲みます。口渇を感じたらたくさん飲み、次に薄い粥を食べ、十分に休息します。通常、次の日には回復します。
3. ネギ
ネギは良薬とされています。ネギの白い部分と豆豉(黄豆や黒豆を発酵させた乾燥食品)を組み合わせた古来の解熱法があります。市販の豆豉は塩分が高いことが多いので、塩分の少ないものを選ぶとよいでしょう。
作り方は、少量の豆豉を水に加えて50分間煮込み、長ネギ3本を切り、白い部分を数段に切って加えます。さらに5〜10分煮込み、砂糖を少量加えて脾臓や胃を保護します。出来上がったスープをできるだけ多く飲み、おかゆを食べ、十分に休息します。体力が低下している時は、おかゆが命の恩人となることがあります。
4.クワイ
クワイは美味しく保存も簡単で、解熱効果も期待できます。ただし、クワイには寄生虫が含まれていることがあるため、使用前に2〜3分間水で煮て皮を剥きます。体調が良好なときはそのまま煎んじて食べ、体調が悪いときはジュースにして飲むとよいでしょう。
また、甘蔗汁も清熱解毒の効果があります。
(翻訳編集 里見雨禾)













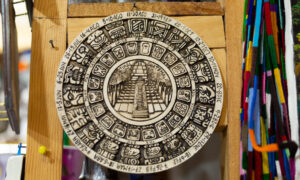






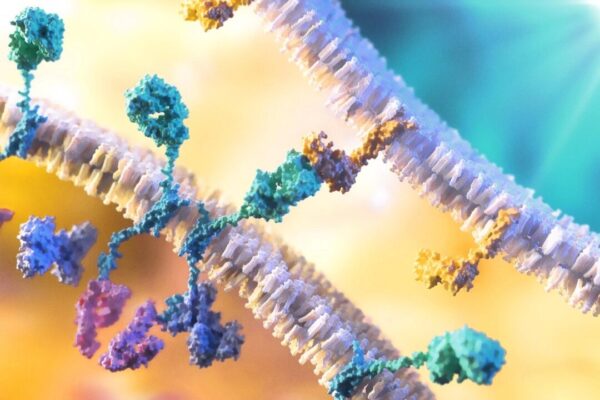



 ご友人は無料で閲覧できます
ご友人は無料で閲覧できます Line
Line Telegram
Telegram





ご利用上の不明点は ヘルプセンター にお問い合わせください。