台湾の伝統的な漢方医療家系「懷生堂」の五代目継承者であり、台中にある「濟生漢方診所」の院長を務める張維均医師は、B型肝炎に感染した後、自然な治療法を求めて多くの漢方薬や療法を試しました。そして、特定の2種類のスプラウト(新芽野菜)を3か月間食べ続けた結果、B型肝炎ウイルスが陰性となり、脂肪肝の症状も完全に治癒したのです。
NTDTVの健康番組「健康1+1」に出演した張医師は、この2種類のスプラウト――赤キャベツスプラウトとブロッコリースプラウト――が持つ驚くべき健康効果について語りました。これらのスプラウトは、肝臓を強化し解毒を助けるだけでなく、がん予防にも役立つ可能性があるといいます。
B型肝炎との個人的な闘い
B型肝炎は、B型肝炎ウイルス(HBV)によって引き起こされる感染症です。進行すると慢性肝炎となり、最終的には肝硬変や肝がんにつながる可能性があります。かつて台湾では、B型肝炎の感染率が非常に高く、感染経路としては輸血、注射針の共有、出産時の母子感染が主な原因とされていました。
張維均医師は、軍に入隊する前の健康診断でB型肝炎と診断されたことを明かしました。彼は、この感染が幼少期に医療注射で針を共有したことが原因ではないかと考えています。「B型肝炎を30年以上抱えていましたが、全く症状がありませんでした。ただ、健康診断で肝臓の超音波検査を受けた際に、長期間のHBV感染が原因の軽度の脂肪肝が見つかっただけです」と述べています。
「この20年間、この病気を自然な方法で治したいという一心で様々な治療法を探し続けてきました。古代中国の伝説的な医者である神農が、百種類以上の薬草を試した精神に影響を受け、私も漢方薬や食品を一つずつ試していきました。そして、3か月ごとにウイルス量や肝酵素の値を検査していました。
2013年からは赤キャベツスプラウトとブロッコリースプラウトの摂取を始めました。その結果、3か月後の検査ではB型肝炎ウイルスのキャリア状態が陰性となり、ウイルス量がゼロまで減少しました。この結果に検査技師も驚き、一時はデータに誤りがあるのではないかと疑ったほどです。その後、脂肪肝の症状も完全に治りました。
また、私の同業者や患者の中にもB型肝炎のキャリアで、同じスプラウト療法を試して効果を実感した方がたくさんいます」と張医師は述べています。最近では、診療所を訪れたある患者がスプラウトを取り入れた食事療法を試した結果、B型肝炎ウイルスのキャリア状態が陰性になったと報告してきたことも明らかにしました。
スプラウト(新芽)の健康効果
張維均医師によると、赤キャベツとブロッコリーはどちらもアブラナ科の野菜で、抗ウイルス作用や抗がん作用を持つ植物由来の成分を豊富に含んでいます。研究によれば、若い新芽(スプラウト)は成熟した野菜よりも植物栄養素の濃度が格段に高いことが分かっています。例えば、ブロッコリースプラウトには、成熟したブロッコリーの10倍から100倍のスルフォラファン(硫黄を含む化合物)が含まれています。
近年、アブラナ科野菜に含まれる成分について、肝臓の解毒作用やがんリスクの低減などの健康効果を示す研究が増えています。
肝臓の健康を促進
ある総合的な研究では、アブラナ科野菜に含まれるスルフォラファンが、肝臓の解毒に重要な役割を果たすグルタチオンという物質のレベルを高め、毒性物質による酸化ストレスを軽減することが確認されています。さらに、スルフォラファンは発がん物質による肝臓へのダメージを防ぐ効果もあるとされています。
また別の研究では、ブロッコリーに含まれるケルセチンが、肝臓に強い毒性を持つことで知られるアフラトキシン(カビ毒の一種)を解毒する作用があることも報告されています。
がんリスクを減らす
慢性B型肝炎の患者は、肝がんを発症するリスクが高いことが知られています。世界中の肝がん症例の半数以上がB型肝炎に関連していると推定されています。
アブラナ科野菜に含まれる硫黄化合物は、抗がん作用があることで知られています。ある研究では、スプラウトはこれらの化合物を成熟した野菜よりも高濃度で含んでいることが確認されています。例えば、動物実験の結果、3日齢のブロッコリースプラウトが乳がん細胞の抑制に最も効果的であることが示されました。
また、別の比較研究では、成熟した赤キャベツと比べて、若い芽のジュースの方が前立腺がん細胞の増殖を抑える効果が高いことが報告されました。この若い芽は、ビタミンCやカロテノイドの含有量も成熟した野菜より多いことが分かっています。
さらに、2019年に発表された『Science』誌の研究では、アブラナ科野菜の抗がんメカニズムについても明らかにされています。がんは、体内の腫瘍を抑制する仕組みが正常に働かなくなることで発生することがあります。アブラナ科野菜にはグルコブラシシンという成分が含まれており、消化の過程でインドール-3-カルビノール(I3C)という物質に変化します。このI3Cは、腫瘍抑制機能を再活性化させる効果が確認されており、その結果、アブラナ科野菜はがんの予防や治療に役立つ可能性があるとされています。
調理方法
張医師は、スプラウトの健康効果を最大限に引き出すための2つの調理方法を紹介しています。
サラダ
赤キャベツスプラウトやブロッコリースプラウトを生のままサラダにして食べる方法です。コールドプレス製法のエキストラバージンオリーブオイルをかけると、簡単で栄養価の高い一品になります。スルフォラファンは脂溶性であるため、健康的な油と一緒に摂取することで吸収率が高まります。

スープ
スプラウトをスープに加えるのもおすすめです。たとえば、生姜を使った鶏肉のスープを作り、最後に赤キャベツスプラウトやブロッコリースプラウトを加えます。スプラウトを軽く湯通しすると、スルフォラファンが効率よく放出され吸収されやすくなります。ただし、長時間加熱すると栄養が壊れてしまうため注意が必要です。また、皮つきの鶏肉から出る脂肪分が、スプラウトに含まれる脂溶性の栄養素を体に取り込みやすくしてくれます。

張医師によると、スプラウトは一度に4箱購入し、1食あたり半箱を1日1~2回食べるのが普段の習慣だそうです。
中医学(漢方)の考え方では、スプラウトは「体を冷やす性質」(涼性)を持つ食品とされています。そのため、冷え性の方や下痢をしやすい方が大量に摂取すると、胃腸の不調を起こす場合があります。体は正午頃に冷たい食べ物を受け入れやすいとされているため、スプラウトを食べるなら昼食時がおすすめです。また、1日3回食べたい場合は、1食あたり箱の3分の1程度が適量とされています。
スプラウトを新鮮に保つには、1回分だけ取り出し、残りは冷蔵庫で保存すると良いでしょう。
注意点
スプラウトを生で食べることは健康に多くの効果をもたらしますが、すべての人に適しているわけではありません。張医師によると、アブラナ科野菜を生で摂取すると甲状腺ホルモンの合成に影響を与える可能性があるため、甲状腺機能低下症やヨウ素不足による甲状腺腫のある人は、生のスプラウトの摂取を控えた方が良いとされています。一方で、甲状腺機能亢進症の人にとっては、赤キャベツスプラウトやブロッコリースプラウトを生で摂取することで甲状腺機能を抑える効果が期待できる可能性があります。
また、ある研究では、キャベツやブロッコリーなどのアブラナ科野菜を大量に生で食べると、甲状腺機能に悪影響を及ぼす可能性があると指摘されています。ただし、この影響についてはまだ明確に証明されているわけではありません。しかし、これらの野菜を加熱調理することで、こうした潜在的な影響を軽減できることが分かっています。
肝臓を傷つける毒素に注意
スプラウトを摂取して肝臓の健康をサポートするだけでなく、慢性肝炎患者は肝臓に悪影響を与える食品を避けることが重要です。カビが生えたピーナッツやナッツ、穀物には「アフラトキシン」」という有害物質が含まれることがあり、これが肝臓の細胞を傷つけ、肝硬変や肝がんのリスクを高めます。
張医師は、ピーナッツバターやピーナッツパウダーを長期間保存しないよう注意を促しています。アフラトキシンを摂取するリスクを避けるためには、白米を小さなパッケージで購入し、湿気や高温の場所で長期間保管しないことが推奨されます。
また、加工食品には添加物や不健康な脂肪が多く含まれており、これが肝臓に負担をかける原因となります。特に加工肉は、肝臓に有害な物質であるニトロサミンを生成する可能性があり、消化器系のがんに関連するリスクがあります。
さらに、早食いや過食、甘いものの摂りすぎ、冷たい飲み物の飲みすぎも消化機能を乱す原因となります。消化が悪化すると、食べ物が腸内で発酵し、毒素が発生しやすくなり、その結果、肝臓の解毒機能に余計な負担がかかります。
B型肝炎感染の危険性
急性B型肝炎の症状は風邪に似ており、倦怠感、上腹部の違和感、食欲不振、まれに黄疸が見られることがあります。急性期は通常短期間で終わり、症状は比較的早く治まることが多いですが、一部の人では慢性化する場合があります。
B型肝炎ウイルスに感染すると、「肝炎→肝硬変→肝がん」と進行することがあります。一部の感染者は一生症状が出ないまま過ごしますが、慢性的な肝炎が進行して肝臓が硬くなる「線維化」が起こることもあります。この状態を放置すると肝硬変に進み、最終的には肝がんを引き起こす可能性があります。
アメリカの研究では、慢性B型肝炎の患者は肝細胞がんの発症率が30倍に上ることが示されています。また、胃がんなど他のがんのリスクも高まることが分かっています。
こうしたリスクを減らすために、張医師はB型肝炎のキャリアに対し、6か月ごとに肝機能検査や肝臓の超音波検査を受けるよう推奨しています。異常が見つかった場合は、すぐに対処し適切な治療を受けることが重要です。
この記事で述べられている意見は著者の意見であり、必ずしもエポックタイムズの意見を反映するものではありません。エポックヘルスは、専門的な議論や友好的な討論を歓迎します。
(翻訳編集 華山律)













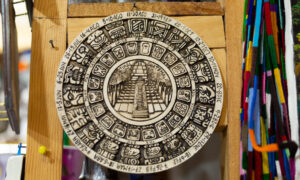











 ご友人は無料で閲覧できます
ご友人は無料で閲覧できます Line
Line Telegram
Telegram





ご利用上の不明点は ヘルプセンター にお問い合わせください。