約2年前のこと。現在、肺疾患と集中治療の専門医として研修中のヴィピン・ムデゴウダー医師は、集中治療室(ICU)での過酷なインターン生活に苦しんでいました。毎日、生死の境をさまよう患者を目の当たりにするうちに、精神的な負担が積み重なり、気分の落ち込みから抜け出せなくなっていたのです。そんな時、彼は「心のケア」を取り入れることを決意しました。毎日数分間の瞑想を始め、それを続けるうちに少しずつ気持ちが安定していったそうです。「たったこれだけの習慣の変化が、自分を救ってくれました」と彼は語ります。
不安と憂うつに悩んでいたインターン時代を経て、今では救急救命室(ER)で患者を支える、前向きで思いやりのある医師へと成長しました。
近年の研究では、「精神的な充実」が心血管疾患やアルツハイマー病のリスクを下げ、メンタルヘルスの改善や寿命の延長にもつながることが明らかになっています。しかし、現代社会では「心のケアが軽視される風潮」が広がっており、その重要性を実感しにくい人も多いのが現状です。
とはいえ、信仰がある人も、無神論者も、あるいはその間の立場の人も、健康が深刻に損なわれたときには「心の支え」を求める傾向があると、家庭医学と肥満治療の専門医であるカイル・ギレット医師は指摘しています。
結局のところ、健康の問題は、身体的なものであれ精神的なものであれ、「自分自身のこと」として向き合わざるを得なくなるものです。
では、「心のケア」をおろそかにすると、どんな大切なものを失ってしまうのでしょうか?
宗教的な活動と寿命の関係
週に一度の礼拝などの宗教的な活動に参加することは、「毎日タバコを1箱吸うことが健康に与える悪影響と同じくらいの規模で、逆に寿命を延ばす効果がある」とする研究結果が、『Review of Religious Research』に掲載されました。その効果は、およそ7年の寿命延長に相当するといいます。
また、『Journal of the American Board of Family Medicine』に発表された研究によると、宗教的な集まりへの参加と寿命の延長には関連があることが分かっています。この研究では、定期的に礼拝へ参加することの健康面でのメリットは、心臓病のリスクを下げるために広く使われているスタチン系の薬と同じくらいの効果があるとされています。論文の著者は、「宗教的な活動は、スタチン系の薬よりもコストパフォーマンスが高い可能性がある」と指摘しています。
さらに、長期間の追跡調査では、宗教的な習慣を持つことと心臓病のリスク低下との関連も明らかになっています。30年以上にわたる調査の結果、低所得層や糖尿病患者など心臓病のリスクが高い人が多いにもかかわらず、宗教的な活動を続けていたグループでは、無宗教のグループに比べて心臓病による死亡リスクが32%低かったことが分かりました。
また、2008年に発表された別の研究では、過去の調査データをもとに約9万3千人の女性を対象に分析が行われました。その結果、定期的に礼拝に参加している人は、そうでない人に比べて死亡リスクが20%低いことが判明しました。
祈りと瞑想が脳の健康に与える影響
2024年、アメリカの研究チームが「祈り」と「心の健康」との関係を調査しました。この研究では、幸福感、うつ、不安、自己コントロール感、人生の目的意識、尊厳などの指標と、さまざまな祈りの形態との関連性が分析されました。その結果、祈りの中で前向きな感情を抱いたり、他者と一緒に祈ったりすることが、心の健康を向上させることが分かりました。一方で、祈りの最中に否定的な感情を持つことは、うつや不安の悪化と関連していました。
ギレット医師は、「祈りに関する研究から、祈ることで身体的な健康が客観的に向上する可能性があることが分かっています」と指摘しています。「その理由はまだはっきりと分かっていませんが、医療の分野でも信仰や祈りの効果についての研究が増えてきています」と述べています。
また、瞑想のような心を整える習慣は、脳の構造に良い影響を与えることが分かっています。瞑想をしたことがない人と比べると、瞑想を習慣にしている人は、脳の前方部分の皮質が厚くなっていました。この部分は、思考や感情のコントロールに関わる重要な領域です。研究では、瞑想を続けることで注意力や感情を調整する力が鍛えられ、それが脳の構造的な変化につながる可能性があると示唆されています。
また、マインドフルネス(瞑想を用いた心のトレーニング)には、不安を和らげる効果があるとされていますが、通常の薬物療法と比べた場合の効果はまだはっきりと分かっていません。2022年に『JAMA Psychiatry』に掲載された臨床試験では、不安障害の治療によく使われる抗うつ薬レクサプロ(一般名エスシタロプラム)と、マインドフルネスの効果を比較しました。その結果、マインドフルネスはレクサプロと同程度の効果があることが確認されました。
さらに、別の研究では、日常的に精神的な活動を増やすことで、強いストレスにさらされた人々の脳の働きを保つのに役立つ可能性があることが示されています。
宗教的信念が炎症を抑える可能性
炎症は、免疫システムが感染症などの外敵から体を守るための自然な反応ですが、長く続くと健康に悪影響を及ぼします。炎症の指標の一つである C反応性タンパク質(CRP) の値が高いと、心臓病、2型糖尿病、アルツハイマー病、パーキンソン病、脳卒中、加齢による視力低下(加齢黄斑変性症)など、さまざまな病気のリスクが高まることが分かっています。また、ストレスやうつ病の発症リスクとも関係があるとされています。
2024年にアメリカで行われた研究では、中高年を対象に「精神的な信念」と「炎症・認知機能・身体的健康」との関係を調査しました。その結果、 宗教的な信念や価値観を強く持っている人は、CRPの数値が最大6.5%低い ことが明らかになりました。
スピリチュアルな力を鍛える方法
スピリチュアルな成長を始めたいけれど、何から手をつければいいのか分からず戸惑っている人へ。ムデゴウダー医師とギレット医師は、「スピリチュアルな力を鍛える」ように、少しずつ取り組むことを勧めています。
ムデゴウダー医師によると、スピリチュアリティとは、単に宗教的な信仰を持つことではなく、「自分の内面がどのような状態にあるか」を大切にすることだといいます。その第一歩として、「思いやりの心を育むこと」から始めるのがよいとのことです。他人に対しても、自分に対しても優しく接することを意識し、何気ない親切を実践してみましょう。「思いやりのある人は、道徳に無関心な人の心さえも動かすことができます。一方で、冷たい態度をとると、同じ価値観を持つ人でさえ遠ざけてしまいます」とムデゴウダー医師は述べています。
ギレット医師は、スピリチュアルな力を鍛えるには、筋力トレーニングと同じように「少しずつ負荷を増やしていく方法」が効果的だと説明します。ベンチプレスでいきなり重すぎる負荷をかけても効果がないのと同じで、無理のない範囲で少しずつ挑戦することが大切です。「少し努力が必要だけれど、乗り越えられるレベル」のスピリチュアルな課題に取り組み、それを継続することがポイントです。たとえば、いきなり長時間の瞑想を始めるのではなく、まずは1日数分からスタートし、徐々に時間を延ばしていくのがよいでしょう。
ギレット医師は、「本当の健康とは、体、心、精神が調和している状態です。どれか一つをおろそかにしては、真の健康にはたどり着けません」と強調します。そして、医師と患者が協力しながら、その人に合った健康プランを考えるべきだと提案しています。
彼は診察の際、患者の内面を知るために、次のような質問をするそうです。
- あなたの人生の目的は何ですか?
- あなたやご家族、友人は、肉体的なこと以外でどんな目標を立てていますか?
- あなたはどのような信念や価値観を持っていますか?
こうした質問を通じて、その人に合った方法を提案しながらも、特定の考え方を押し付けることはしません。彼は、瞑想などのスピリチュアルな習慣を「生活のリズムの一部として定期的に取り入れること」が大切だと考えています。習慣化が鍵なのです。
ギレット医師は、「最低でも年に1回は、自分の人生の目的や目標を書き出し、それに向けてどんな行動を取ってきたか、今後どのように改善できるかを考える時間を持つべきだ」と勧めています。
「これは、いわば『人生の質を向上させるための自己評価と改善のプロセス』です。『精神的な健康』と呼んでもいいですし、『スピリチュアルな健康』と表現してもよいでしょう。自分にしっくりくる言葉を使ってください」と彼は語ります。
さらに、「毎月、信頼できる人たちと集まり、互いの考えや疑問を共有し、困難にどう対処すればよいか話し合う時間を作る」ことも推奨しています。
スピリチュアルな実践や信仰は、心理的・身体的健康を向上させ、人生の満足度を高めることが多くの研究で示されています。もしかすると、今こそ立ち止まり、自分の人生を振り返り、より良い未来に向けてどんな変化を起こせるか考えてみるべき時なのかもしれません。
(翻訳編集 華山律)













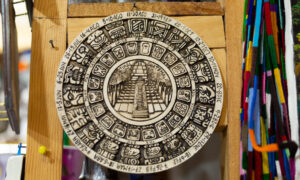








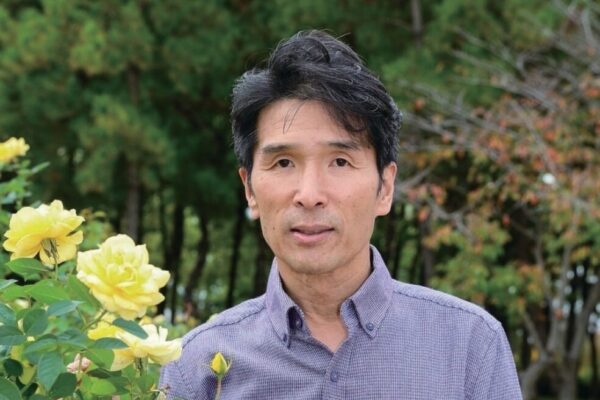

 ご友人は無料で閲覧できます
ご友人は無料で閲覧できます Line
Line Telegram
Telegram





ご利用上の不明点は ヘルプセンター にお問い合わせください。