朝食を正しく選べば、健康を保てるだけでなく、一日をエネルギッシュにスタートできます。忙しい日々を乗り切るためにも、まずは体の基本的な働きを理解し、自分に合った朝食を選ぶことが大切です。
自然のリズムに合わせた食事で健康に
私たちの体は自然のリズムと連動して動いています。そのため、健康を維持するには「自然の流れに沿った食生活」を意識することが大切です。夜の間は体を休息、朝になるとエネルギー(陽気)が太陽のように少しずつ高まります。ただし、この時点ではまだ十分に強くありません。そのため、朝食には体を温めてエネルギーを補う食べ物を選ぶのが理想的です。
一方で、朝起きてすぐに冷たい生野菜や果物を食べると、体が冷えてしまい、せっかく高まり始めたエネルギーが弱まってしまいます。これが続くと、冷えやすい体質になり、さまざまな不調を引き起こす原因になります。最近では、野菜や果物をミキサーで混ぜたスムージーを朝食にする人も増えていますが、実はこれが体に負担をかけることもあります。特に胃腸が冷えやすい人は、朝から冷たいスムージーを飲むと、胃腸の働きが低下し、お腹の張り、息苦しさ、下痢、疲労感などの症状が出やすくなります。
「3・2・1」の黄金バランス! 健康的な食事法とは?
私たちの体は、一晩休んだ後の朝が最も栄養を吸収しやすい状態になっています。すべての内臓がしっかり目覚め、食べ物を受け入れる準備が整い、胃酸の分泌も活発になります。そのため、朝食で摂取した栄養はスムーズに消化・吸収され、不要なものは腸を通じて排出されやすくなります。一方、夜になると、一日中働いた内臓は疲れ切っています。この状態で食べ過ぎると、胃腸に負担がかかり、消化しきれなかったものが体内に蓄積され、慢性的な不調を引き起こす原因になります。
そのため、普段の食事は「朝食3:昼食2:夕食1」の割合を意識することが大切です。朝食は栄養をしっかり摂り、特に魚・肉・卵などのタンパク質を十分に補給して、一日の活動に備えます。昼食は適量を心がけ、バランスの取れた食事を意識します。夕食は軽めにし、消化の良いものを中心にすることが理想的です。
「胃のエネルギー」を守ることが健康長寿のカギ
東洋医学では、胃腸の働きが健康の基本とされており、気(エネルギー)と血(栄養)を生み出す源と考えられています。特に、「胃のエネルギーがあれば健康でいられるが、それが衰えると命に関わる」という考え方があります。つまり、胃腸を健康に保つことが、長生きの秘訣なのです。前述の通り、朝食に生野菜や冷たい食べ物を空腹で摂ると、胃腸のエネルギーが弱まり、体調を崩しやすくなります。
では、どんな朝食が胃に優しく、健康に良いのでしょうか?おすすめなのは、「うるち米」です。うるち米(一般的な白米)は、胃腸に優しく、消化しやすいため、胃の調子を整えるのに最適な食材とされています。
うるち米 胃を元気にする理想の朝食
【別名】白米、稲米(とうべい)、硬米(こうまい)。
【性質・味】体を冷やしたりも温めたりもしない穏やかな性質を持ち、無毒。味はほんのり甘く、淡白。主に胃や脾(ひ)に作用する。
【効能】胃腸を整え、気力を補い、五臓の働きを安定させる。のどの渇きを癒し、下痢を防ぎ、筋肉や骨を強くし、血流を促進し、精力を高め、顔色を良くする。胃の不調や虚弱体質の改善にも役立つ。
多くの食品の中でも、胃の働きを助け、体に活力を与えるのに最適なのが「うるち米」 です。古い文献には「うるち米は人々が日常的に食べる主食であり、自然の恵みを受けた五穀の王である」と記されています。また、中国の医学書にも「穀物を安定して食べれば健康になり、絶つと命を落とす」とあるように、うるち米は生命を支える重要な食べ物とされています。
うるち米は、胃腸にやさしく消化しやすい特徴があり、体に必要なエネルギー(気)や血を補い、筋肉や肌を健康に保つ働きを持っています。そのため、健康維持の基本となる食材はうるち米である と言えます。ただし、ここでいううるち米とは精白された白米のことであり、玄米ではありません。

玄米を長期間食べ続けると健康に悪影響を及ぼす
現代の栄養学では、玄米の栄養価に注目し、玄米は栄養が豊富で白米は栄養が少ないと考えられています。また、白米にはデンプンが多く含まれ、体内でブドウ糖に変わりやすいため、血糖値を上げやすく健康に良くないとされています。こうした考えから、多くの人が白米を避け、健康のために玄米を選ぶようになりました。しかし、実際の臨床結果を見ると、玄米を長期間食べ続けることは、かえって健康を害する可能性があります。
日本で「玄米菜食」を実践した第一人者であり、「東洋健康法」の研究者でもある原崎勇次博士は、著書『医者に頼らない食事法』の中で、「玄米菜食を始めて最初の1〜2か月は体調が良く、順調に進む。しかし、長く続けると危険が伴い、めまいや貧血、体力の低下により倒れることもある。どんな食べ物も摂りすぎは体に良くないが、特に玄米の過剰摂取は白米よりも害が大きい ようだ。私自身の経験では、玄米を食べ過ぎると鼻づまり、口内炎、視力の低下、体のこわばり、息切れ、倦怠感、食欲不振 などの症状がすぐに現れた。私は玄米菜食を続けなかったが、もし続けていたら、さらに深刻な病気になっていたかもしれないと直感的に感じた」と述べています。
では、健康のための玄米菜食がなぜこのような結果を招くのでしょうか? その理由は、玄米の栄養は吸収されにくく、消化に負担がかかるため です。その結果、慢性的な消化不良を引き起こし、胃腸が疲れやすくなることで体調を崩してしまうのです。
もちろん、玄米や野菜中心の食事が悪いわけではありません。しかし、多くの人が「玄米は健康に良い」と信じ込み、自分の体の状態を無視して食べ続けてしまうことが問題なのです。玄米菜食を実践する人の多くは、真面目で自分に厳しい性格の人が多いと言われています。「玄米が健康に良いから」と思い込み、たとえ美味しくなくても無理をして食べ続けることが、体調を悪化させる一因になっています。自分の体に合わない食事を無理に続けると、精神的なストレスが積み重なり、結果として健康を損なうことにつながります。
本稿では、玄米に関する誤解 について触れました。これは、古くからの食文化と現代栄養学の違いを理解し、読者の皆さんに自分の体の声をよく聞き、間違った健康情報に惑わされないようにしてほしい という願いからです。正しい知識を持ち、自分に合った食事を見極めることが、健康を守るために最も大切なのです。
(翻訳編集 華山律)













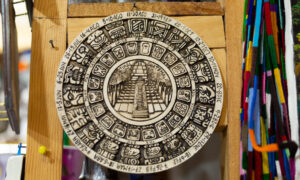










 ご友人は無料で閲覧できます
ご友人は無料で閲覧できます Line
Line Telegram
Telegram




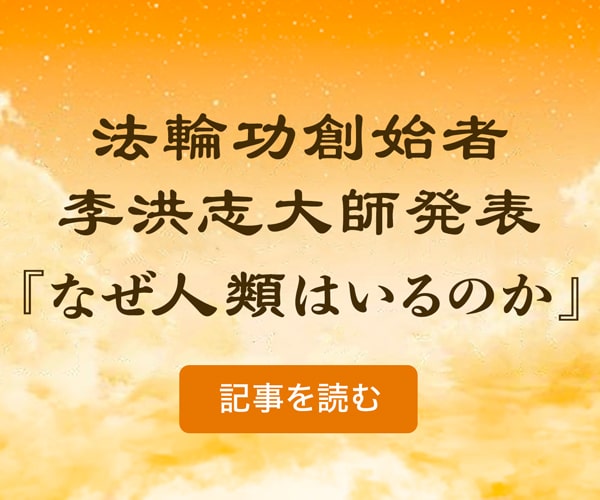
ご利用上の不明点は ヘルプセンター にお問い合わせください。