【破鏡重円(はきょうじゅうえん)】
「離散した夫婦が巡り合う」とか「離婚した夫婦が再び元の鞘に収まる」という意味の中国のことわざ。
これは、ただ単なる美しい愛の物語ではなく、そこには自らを犠牲にして他人を助けるという美徳も反映されています。
このことわざの由来となった物語は九世紀の中国で起きました。当時の中国は、北方で強大な勢力を持つ隋に対して、南方には小さな国がいくつかありました。建康(今の南京)を都とする陳はその一つで、隋は南方の国々の統一のために、陳を虎視眈々と狙っていました。
陳の皇太子の侍従官・徐徳言(じょとくげん)は、皇太子の妹で才色兼備の楽昌(らくしょう)を妻に娶っていました。当時、陳はちょうど衰退し、時局が乱れており、今にも滅びそうでした。
そこで、徐徳言は妻に、「そなたの優れた才華と美貌があれば、たとえ国が滅びても、きっと権力のある裕福な人の家に入ることができるに違いない。私たちは永遠に離れ離れになるかもしれないが、もしも私たちの縁がまだ終わっていなければ、必ずまた会えるだろう。そのときのために、しるしとなる物を用意しよう」と言うと、銅の鏡を二つに割って、夫婦がそれぞれ片方ずつ持つことにしました。
そして、「必ず毎年正月の十五日に鏡を市で売りに出してほしい。もしそれを見かけたら、私は必ずそなたを探しに行くから」と、妻と約束しました。
ほどなく、隋は陳を滅ぼすと、隋の皇帝・文帝は、褒美として楽昌を大臣の楊素(ようそ)に与えました。楊素は彼女を非常に寵愛しました。
徐徳言は路頭に迷いながらも、やっとのことで都に着きました。すると、なんと本当に、正月の十五日に市で片割れの鏡を売っている老人がいたのです。その鏡はとても値段が高く、売れないでいました。徐徳言は、老人を自分の家に連れて帰り、事情を聞いてみると、その老人は、楽昌の家の使用人でした。
徐徳言は自分の経歴を老人に語ると、自分の持っていた半分の鏡を出し、老人の鏡と合わせると、鏡面に「鏡と人はともに去って行った。今、鏡は帰ってきたが、人はまだ帰らない。まるで月に嫦娥(じょうが)がいなく、ただ明月の輝きだけが残っているようなものである」と書き記し、老人に持ち帰らせました。
楽昌はその詩を読むと、泣いてばかりで食事もろくに取れませんでした。楊素は本当のことを知り、非常に心を痛めましたが、侍従に徐徳言を連れてこさせると、妻を彼に返し、多くの金品を与えました。
楊素はまた、徐徳言と楽昌のために送別の宴を設けました。そこで楽昌は詩を書いて、自らの気持ちを表しました。
「今日までの移り変わりを思い出し、今二人の夫が顔を合わせているのを目にすると、笑うことも泣くこともできず、今まさに、身を持することの難しさを知りました」
徐徳言と楽昌は、一緒に江南に帰ると、ともに白髪になるまで、ずっと一緒に添い遂げたといいます。

















 大同小異【ことわざ】
大同小異【ことわざ】  一字千金【ことわざ】
一字千金【ことわざ】  一網打尽【ことわざ】
一網打尽【ことわざ】  一敗塗地【ことわざ】
一敗塗地【ことわざ】  破鏡重円(はきょうじゅうえん)【ことわざ】
破鏡重円(はきょうじゅうえん)【ことわざ】  三顧の礼【ことわざ】
三顧の礼【ことわざ】  風聲鶴唳(ふうせいかくれい)【ことわざ】
風聲鶴唳(ふうせいかくれい)【ことわざ】 
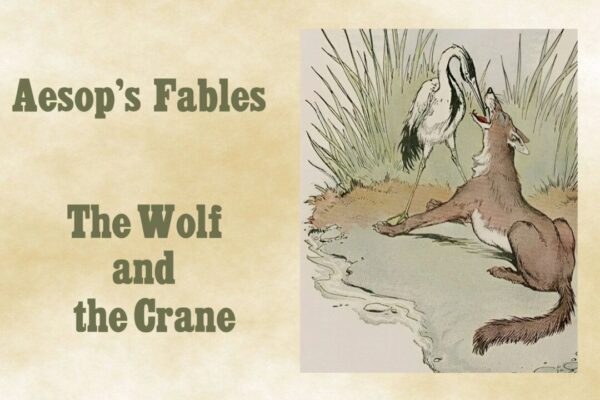





 ご友人は無料で閲覧できます
ご友人は無料で閲覧できます Line
Line Telegram
Telegram





ご利用上の不明点は ヘルプセンター にお問い合わせください。