年齢を重ねるにつれ、薄毛や抜け毛に悩む人は少なくありません。このシリーズでは、自分の抜け毛の原因を見極め、適切な対策を考えるためのヒントを紹介します。
髪の根元には、毛根を包み込む「毛包(もうほう)」があり、そこでは栄養が運ばれ、髪を作るための材料が供給されることで、健康な髪が生えています。しかし、この仕組みに問題が生じると、抜け毛が増えてしまいます。
アメリカでは、男性の約80%、女性の約50%が抜け毛の悩みを抱えているといわれています。原因は人それぞれ異なり、日々の食生活やホルモンバランスの変化などが関係していることもあります。
髪の仕組みについて
髪の成長や生命活動は、すべて根元にある毛包(もうほう)で行われています。
毛包の中の細胞は、体内でも特に活発に代謝し、分裂を繰り返す細胞の一つです。髪の根元は球状をしており、その底にあるのが毛乳頭(もうにゅうとう)です。毛乳頭には多くの毛細血管が集まっており、髪の成長に必要な血液や栄養を供給しています。
毛包の中では、新しい髪の細胞が次々と作られ、それが髪の毛となり、少しずつ頭皮の外へ押し出されていきます。そのため、髪は1か月に約1センチのペースで伸びます。
また、頭皮には約10万個の毛包があり、1つの毛包から複数本の髪が生えていることもあります。
髪の成長には周期があります
髪は植物のように、一定の周期を繰り返しながら成長します。まず、成長期があり、この期間は2〜7年続きます。その後、髪の根元が毛乳頭との結びつきを失い、休止期に入ります。休止期は3〜4か月続き、その後、髪が抜け落ち、新しい髪が生えてきます。このサイクルが絶えず繰り返されます。
髪は植物とは異なり、一斉に抜け落ちるわけではありません。髪の生え変わりの割合は一定に保たれています。成長期の髪は全体の80〜89%、退行期(成長が止まる時期)は1〜5%、休止期(抜ける準備をする時期)は10〜20%を占めます。
髪は常に一部が休止期に入っているため、日々抜け落ちます。健康な成人なら、1日に70〜100本程度の髪が自然に抜けるのは普通のこととされています。
「自然な抜け毛だけで薄毛になることはありません」国際毛髪修復外科学会(ISHRS)のメンバーであり、毛髪移植外科医のラジェシュ・ラジプト氏は、「大紀元時報」のインタビューでこう述べています。「髪の成長サイクルが乱れ、抜けた髪が新しく生えてこなくなると、薄毛が進行します」
抜け毛には回復できるものとできないものがある
抜け毛には、回復できるものと回復が難しいものがあります。回復できる抜け毛は、髪の成長サイクルの乱れが原因で起こるものです。毛包(もうほう)がまだ機能しているため、新しい髪が生えてくる可能性があります。一方、回復が難しい抜け毛は、毛包が深刻なダメージを受け、傷跡のようになってしまった状態です。この場合、毛包が機能を失い、新しい髪が生えてくることはありません。この二つのタイプは、「非瘢痕(ひはんこん)性脱毛」と「瘢痕(はんこん)性脱毛」と呼ばれています。
2019年に発表された、世界中の毛髪専門クリニックによる統計では、脱毛症の患者の約70%が非瘢痕性脱毛、約30%が瘢痕性脱毛だったという結果が出ています。
どちらのタイプの抜け毛でも、ある程度は進行を遅らせたり、改善したりする方法があります。ただし、すべての人に共通する確実な解決策はありません。このシリーズでは、具体的な対策について詳しく説明していきます。
その前に、まずは自分の抜け毛の原因を知ることが大切です。
抜け毛の主な原因
抜け毛の原因はさまざまですが、特に多く見られるものを紹介します。
1. 毛包が男性ホルモンに過敏に反応する——遺伝が主な要因
髪の成長は、男性ホルモン(アンドロゲン)の影響を受けます。男性だけでなく女性の体内にも男性ホルモンは存在します。思春期前の脇の下には細い毛しか生えていませんが、男性ホルモンの分泌が増えると、濃くて太い毛が生えるようになります。
しかし、一部の人では、男性ホルモンが頭皮の特定の毛包に対して抑制的な作用を持つことがあります。特に「ジヒドロテストステロン(DHT)」というホルモンに過敏な毛包があると、抜け毛が進行しやすくなります。
DHTは、毛包を萎縮させる作用が最も強いホルモンです。DHTに敏感な人は、通常のホルモンレベルでも脱毛が起こる可能性があります。特に、前頭部や頭頂部の毛包にはDHTの受容体が多く存在し、DHTがこれらの受容体と長時間結びつくことで、毛包の細胞に影響を与えます。この影響により、毛包は徐々に縮小し、成長期が短くなっていきます。その結果、髪はどんどん細くなり、やがて毛包から生えてこなくなります。最終的には、髪のない毛穴だけが残ります。これが一般に「男性型脱毛症(AGA)」と呼ばれる脱毛症で、「アンドロゲン性脱毛症」ともいわれます。男性型脱毛症は非瘢痕性脱毛症に分類されますが、何も対策をせずに進行すると、毛包が完全に消失し、回復が難しくなります。
男性型脱毛症は、男性だけでなく女性にも見られます。アメリカでは約5千万人の男性、3千万人の女性がこのタイプの脱毛に悩んでいるといわれています。
では、DHTへの過敏性による脱毛は、最も多い原因なのでしょうか? スペイン・マドリードのラモン・イ・カハル大学病院の皮膚科医であり、毛髪疾患の研究者であるダビッド・サセダ=コラロ医師は、次のように答えています。
「男性の脱毛のほとんどは、DHTに対する毛包の過敏性によるものです。女性の場合はもう少し複雑ですが、男女ともに最も一般的な脱毛の原因であることは間違いありません」彼の臨床経験によると、男性型脱毛症の患者の約70%が男性、30%が女性とのことです。
男性の薄毛は、通常額の生え際から始まり、徐々に髪が薄くなっていきます。こめかみ部分や生え際が後退し、さらに頭頂部の髪が抜けていくこともあります。進行すると、最終的には側頭部と後頭部だけに髪が残る状態になります。
一方、女性の場合は、生え際は比較的保たれますが、頭頂部の中央部分が薄くなり、左右に広がるように進行していきます。そのため、前頭部から頭頂部にかけて髪がまばらになり、クリスマスツリーのような形になるのが特徴です。
メルボルン大学医学部教授であり、シンクレア皮膚科クリニックの所長であるロドニー・シンクレア医師は、アメリカメディア「大紀元時報」のインタビューで次のように語っています。「加齢とともに、男性型脱毛症はすべての男性と女性に影響を与えます」
さらに、彼は次のように説明しています。「年齢を重ねると、誰もが男性ホルモンの影響で抜け毛が進行します。唯一の違いは、いつから始まり、どれくらいのスピードで進行するかという点です。50歳になっても15歳の頃のような髪のままの男性は、一人もいません」
シンクレア医師によると、男性型脱毛症は遺伝的要因が約80%、環境的要因は20%以下とされています。つまり、遺伝の影響が非常に大きい脱毛症であるということです。
彼は、過去の研究で出会った印象的なエピソードを紹介しています。「ある男性が、コンサルティング会社の財務部門で非常にハードな仕事をしていました。1日15時間、時には18時間も働き続け、やがて抜け毛が増えていきました。彼はストレスが原因だと思っていました。しかし、オーストラリアに帰国した際、彼は自分の双子の兄弟と再会しました。その兄弟は、9か月間バイロンベイでサーフィンを楽しみ、のんびりとした生活を送っていたのですが、なんと彼と同じように髪が薄くなっていたのです!」
2. 精神的ストレス
双子の兄弟のうち、性格が楽観的なほうも抜け毛に悩んでいることがあるように、遺伝だけでなく、ストレスも抜け毛の原因になります。
毛包(もうほう)は、私たちのストレスを敏感に察知します。毛包にはストレスホルモンの受容体があり、さらに毛包自体もストレスホルモンを生成します。
興味深いことに、頭皮から約3センチの位置にある髪の毛に含まれるコルチゾール(ストレスホルモン)の濃度を測定すると、過去3か月間にどれだけストレスを受けていたかを知ることができます。
ストレスホルモンが毛包内の受容体と結びつくと、信号が発せられ、髪の正常な成長が妨げられます。その結果、髪が抜けやすくなります。また、ストレスホルモンは毛包の成長サイクルを乱し、新しい髪が生えるのを遅らせます。
2021年に科学誌『ネイチャー』に発表された動物実験では、ストレスホルモンが毛包の幹細胞を長期間休眠状態にすることが明らかになりました。さらに、ストレスによって分泌されるコルチゾールは、皮膚内の特定のタンパク質を分解します。このタンパク質は、毛包が正常に機能し、成長を繰り返すために重要な役割を果たしています。
心理的なストレスは、神経ペプチドと呼ばれる物質の分泌を促し、神経系や免疫系を刺激します。免疫システムが過剰に活性化すると、自分自身の毛包を攻撃し、円形脱毛症(自己免疫疾患の一種)を引き起こすことがあります。また、神経ペプチドは毛包の細胞死(アポトーシス)を促し、円形脱毛症の悪化につながることも確認されています。
3. 睡眠障害
仕事や生活のストレスに加え、睡眠不足や夜更かしも、髪が薄くなったり抜け毛が増えたりする原因の一つです。
研究によると、睡眠障害と円形脱毛症には明確な因果関係があることが分かっています。ある調査では、2万5800人の睡眠障害のある人と1万2900人の睡眠に問題のない人を比較したところ、睡眠障害がある人は円形脱毛症になるリスクが65%高かったと報告されています。特に、若年層や中年層でその傾向が強く見られました。台湾で行われた別の研究では、睡眠障害がある人の円形脱毛症の発症リスクは、通常の4.7倍にもなることが確認されています。
また、睡眠時無呼吸症候群(いびきや呼吸の乱れを伴う睡眠障害)は、家族に脱毛症の人がいる男性の薄毛(男性型脱毛症)リスクを高める可能性があることも指摘されています。家族に脱毛症の人がいて、なおかつ睡眠時無呼吸症候群を持つ男性は、どちらもない男性と比べて、男性型脱毛症になる確率が7倍も高いという研究結果もあります。
さらに、1日の睡眠時間が6時間未満、あるいは睡眠の質が悪い人は、男性型脱毛症の発症率が高くなることも確認されています。
4. 体が大きな変化を受けたとき
調査によると、90%以上の女性が出産後3〜4か月で大量の抜け毛を経験してます。枕の上に髪がたくさん落ちたり、シャンプーの際にごっそり抜けたりして、髪全体のボリュームが明らかに減ることがあります。この現象は、多くの新米ママにとって大きな不安の原因となります。
この抜け毛は、妊娠中のホルモンバランスの変化が関係しています。妊娠中は特定のホルモンの分泌が増え、毛包(もうほう)が通常より長く成長期を維持します。しかし、出産後にホルモンレベルが急激に変化すると、成長期にあった毛包が一斉に退行期へ移行し、3〜4か月後に髪が大量に抜けるのです。産後の抜け毛は、休止期脱毛(急な体の変化やストレスによって起こる一時的な抜け毛)の一種です。しかし、通常は数か月以内に新しい髪が生え始め、徐々に元の状態に戻ります。
出産だけでなく、ホルモンバランスの変化、病気、手術、一部の薬の使用、新型コロナウイルス感染なども、体に大きな負担をかけ、休止期脱毛を引き起こす可能性があります。ただし、これらの原因が解消されると、多くの場合、髪は自然に回復します。
「髪の成長は、体にとって最優先ではありません」毛髪移植外科医のラジェシュ・ラジプト氏は、このように説明しています。「病気やストレス、疲労などで体のバランスが崩れたり、健康状態が悪化したりすると、体は生存に必要な機能を優先し、髪の成長を後回しにします。そのため、体が危機的な状況を乗り越えたあとに抜け毛が増えるのです」
5. 日常生活が原因の抜け毛
● 食事の栄養低下
これまで述べたように、毛包(もうほう)は非常に活発に代謝を行っており、健康な髪を作るには十分な栄養が必要です。毛包には毛細血管が豊富にあり、血液を通じて栄養が運ばれ、髪の成長を支えています。
毛髪移植外科医のラジェシュ・ラジプト医師によると、髪の成長には、抗酸化物質、鉄、カルシウム、オメガ3脂肪酸、アミノ酸、ビタミンB群、ビオチン、亜鉛、セレン、マグネシウム、銅など、多くの栄養素が必要です。これらの成分は、髪の新陳代謝に深く関わっています。
現代では食品が豊富にあり、スーパーにはさまざまな食材が並んでいます。しかし、その一方で、必要な栄養素が不足しているという問題も指摘されています。
過去約100年間で、アメリカやイギリスの野菜や果物に含まれるミネラルの中央値は5~40%(またはそれ以上)減少したとされています。ビタミンやタンパク質の含有量も同様の傾向を示しています。アメリカ農務省のデータを1950~99年まで分析した研究では、タンパク質、カルシウム、リン、鉄、リボフラビン(ビタミンB2)、ビタミンCの含有量が明らかに低下していることが分かりました。
1940年代以降、科学者たちは、現代農業における生産性向上が作物のミネラル濃度を低下させる現象を引き起こしていることに注目してきました。これは「希釈効果」と呼ばれています。果物、野菜、穀物の主要成分は、乾燥重量のうち80~90%が炭水化物ですが、農業技術の発展により収穫量や味の向上が優先され、ミネラルや植物化学成分(ファイトケミカル)などの栄養価が軽視されてきました。
さらに、2024年に発表された総合研究では、環境変化、二酸化炭素濃度の上昇、農薬や化学肥料の過剰使用、無土栽培、流通時のロスを減らすための早期収穫、保存技術の発展、耕地の栄養低下などが、食品の栄養価をさらに低下させた要因として挙げられています。
不健康な食習慣
超加工食品や揚げ物の多い食事、暴飲暴食などは、抜け毛の原因になります。
超加工食品は、ビタミンやミネラル、タンパク質などの栄養素が不足している「空っぽのカロリー」です。それだけでなく、過剰な糖分や不健康な脂肪を含んでおり、ホルモンバランスを乱して髪の成長に悪影響を与える可能性があります。さらに、加工の過程や包装材料の影響で、一部の超加工食品には内分泌をかく乱する化学物質が大量に含まれていることもあります。添加物として使われる硝酸塩やリン酸塩などは、炎症や酸化ストレスを引き起こし、毛包(もうほう)を傷つけるとしています。
また、血糖値を急上昇させる糖質を多く含む食品(白米、白いパン、砂糖入り飲料など)も、抜け毛を引き起こす要因になります。こうした食品を摂取すると血糖値が急激に上がり、インスリンが大量に分泌されます。インスリンの過剰分泌は、男性ホルモン(アンドロゲン)の合成を促し、結果的にジヒドロテストステロン(DHT)の濃度を上昇させ、毛包の退化を引き起こします。さらに、インスリンの増加は頭皮の血流を悪化させ、毛包が酸素不足に陥る原因にもなります。
不健康な脂肪を多く含む食品(揚げ物など)も、頭皮の皮脂分泌を乱し、毛包の詰まりを引き起こします。その結果、抜け毛が進行しやすくなります。さらに、悪い脂肪を摂りすぎると、体内でのビタミンやミネラルの吸収が妨げられ、髪の成長に必要な栄養素が不足する原因にもなります。動物実験では、高脂肪食に切り替えたマウスの毛が広範囲に抜けたほか、幼い頃から高脂肪食を与えられたマウスは、毛が薄くなり再生が困難になることが確認されています。
毛髪移植外科医のラジェシュ・ラジプト医師は、「ジャンクフードは体内で毒素、活性酸素、フリーラジカルを増やします。その結果、毛包細胞がダメージを受け、通常のホルモンレベルでも影響を受けやすくなる」と指摘しています。
1千人以上を対象とした研究では、健康な髪を持つ人と比べて、薄毛の人は揚げ物や砂糖、アイスクリームの摂取量が多く、野菜の摂取量が少ないことが分かっています。さらに、砂糖入り飲料の消費量が多い人ほど、男性型脱毛症のリスクが高いことが分かりました。
過度な洗髪、または洗わなさすぎることが抜け毛の原因に
毎日シャンプーをすることを習慣にしている人もいますが、毛包が十分な皮脂を分泌できているかどうかを考えることが重要です。皮脂の分泌が少ない状態で、洗浄力の強いシャンプーを頻繁に使うと、頭皮が乾燥し、髪が傷みやすくなります。
特に、硫酸塩系の界面活性剤を含むシャンプーは、髪の表面(キューティクル)を傷つけ、パサつきや切れ毛の原因となるほか、頭皮の乾燥を引き起こすことがあります。
一方で、「シャンプーをすると抜け毛が増えるのではないか」と考えて洗髪を控えすぎるのも逆効果です。
頭皮や髪には、皮脂や古い角質(剥がれ落ちた皮膚)、整髪料の残留物、ホコリ、花粉、さらにはタバコの煙などが蓄積します。さらに、頭皮には多くの微生物が存在しており、汚れがたまると毛包の健康を損ない、抜け毛の原因になります。また、皮脂が酸化して毛包を詰まらせると、頭皮のかゆみや炎症を引き起こし、抜け毛のリスクが高まります。一般的に、洗髪後72時間(約3日)が経過すると、頭皮のかゆみが増し、皮脂の蓄積も顕著になることが分かっています。
不適切なヘアスタイルや帽子の締め付けが抜け毛の原因に
高い位置でのお団子ヘアやポニーテール、コーンロウ(細かく編み込むヘアスタイル)、エクステの装着などを長期間続けると、頭皮に強い負担がかかり、毛包(もうほう)が引っ張られます。これにより炎症やダメージが生じ、抜け毛の原因となります。このような脱毛は「牽引性脱毛症」と呼ばれます。特に影響を受けやすいのは、髪の生え際など、最も強い力がかかる部分です。
牽引性脱毛症は、早期に気づいて対策をとれば回復が可能ですが、そのまま放置すると毛包がダメージを受け、瘢痕性脱毛(はんこんせいだつもう)へと進行し、元に戻らなくなることがあります。
また、人種によって毛包の構造が異なることも影響します。白人に比べてアフリカ系の人々は、毛包を皮膚に固定する弾性繊維が少ないため、編み込みヘアなどの影響を受けやすいとされています。そのため、髪を引っ張るスタイルを続けると、牽引性脱毛症のリスクが高くなります。対策として、定期的に髪を緩めたり、スタイルを変えたりすることを推奨しています。
また、長時間きつく帽子をかぶることも牽引性脱毛症の原因になります。帽子がきつすぎたり、長期間洗わずに使ったりすると、頭皮の血行が悪くなり、毛包への栄養供給が減少します。さらに、汗や皮脂がたまり、頭皮環境が悪化することも抜け毛の原因となります。
不適切なヘアスタイルや帽子以外にも、大気汚染や特定の病気が抜け毛を引き起こすことがあります。
毛包の細胞は活発な代謝を行い、血流による栄養供給に強く依存しています。しかし、血液は同時に体内に取り込まれた有害物質も運んでおり、これが毛包の炎症やダメージを引き起こすことが分かっています。
また、有害物質(永続性有機汚染物質、空気中の微粒子など)は、頭皮の毛穴や皮膚を通じて直接毛包に侵入し、炎症を引き起こすこともあります。
細胞実験では、大気汚染物質が活性酸素の増加と炎症性サイトカインの生成を促進し、毛包の角化細胞(髪の成長を支える細胞)を死滅させることが確認されています。さらに、動物実験では、微細なプラスチック粒子(マイクロプラスチック)が皮膚細胞のバリア機能を損傷し、毛包のダメージや脱毛を引き起こすことが示されています。
ホルモンバランスの乱れも、抜け毛の大きな要因です。甲状腺ホルモンの異常、多嚢胞性卵巣症候群(PCOS)などのホルモン関連疾患、自己免疫疾患の患者には、抜け毛が見られることが多くあります。
また、一部の薬の副作用として、脱毛が起こることもあります。特に、高血圧治療薬、不整脈治療薬、スタチン系薬(コレステロール低下薬)、抗がん剤、神経系の治療薬、抗けいれん薬、抗凝血薬(血液をサラサラにする薬)、抗HIV薬などは、抜け毛を引き起こす可能性があります。
早めの診断と治療が大切
「脱毛の種類は100以上あり、似たような特徴や症状を持つものも多くあります」とコラーロ氏は述べています。
一般の人が自分で抜け毛の原因を特定するのは難しいため、専門医による診断が必要です。診断には血液検査のほか、「毛髪鏡診(トリコスコピー)」と呼ばれる検査が行われることがあります。これは、特殊なカメラを使って頭皮の高解像度画像を撮影し、毛包や髪の状態を詳しく観察する方法です。これにより、抜け毛の種類をより正確に特定できます。
コラーロ氏によると、一人の患者が複数の種類の脱毛症を同時に発症することもあります。例えば、女性の場合、男性型脱毛症(AGA)と休止期脱毛症(毛髪の成長サイクルの乱れによる一時的な抜け毛)が同時に起こることがあります。
シンクレア氏は、できるだけ早く診断と治療を始めることが重要だと強調しています。「抜け毛を進行させないことのほうが、抜けた髪を再び増やすよりも簡単です」と述べています。
髪の成長には一定の周期があり、治療の効果が現れるまでに少なくとも数か月はかかります。また、継続しなければ効果を維持できないため、根気強く続けることが大切です。
次回は、現在主流とされる脱毛治療の方法とそのメリット・デメリットについて詳しく解説します。正しい知識を身につけ、自分に合った対策を選びましょう。(続く)
(翻訳編集 華山律)













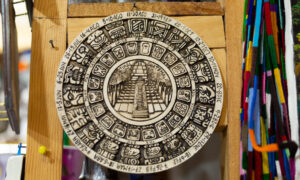










 ご友人は無料で閲覧できます
ご友人は無料で閲覧できます Line
Line Telegram
Telegram





ご利用上の不明点は ヘルプセンター にお問い合わせください。