アロエは、身近な植物として広く知られていますが、その優れた美容・健康効果により、特に注目されています。アロエには、日焼けややけど、湿疹などの肌トラブルを改善する働きがあり、コラーゲンの生成を促進する効果も期待できます。さらに、便秘や胃潰瘍の改善にも役立つため、健康管理においても欠かせない存在です。家庭に一つ備えておくことで、さまざまな場面で活用できる健康の強い味方となるでしょう。
伝統的に、アロエは抗炎症・抗菌作用があり、傷の治癒を助けることから、主に皮膚のトラブルや消化の不調の改善に利用されてきました。やけどや切り傷、虫刺され、湿疹などの治療に使われるほか、便秘解消や胃の健康維持にも役立つとされています。
近年の研究では、アロエに含まれる成分がさらに多くの健康効果をもたらすことが明らかになっています。例えば、アロエエモジンには抗菌作用や糖尿病予防、心臓や骨の健康維持、抗炎症作用、皮膚の保護効果があることが確認されています。また、アロインには炎症の抑制や骨の健康維持、がんや心血管疾患の予防効果があるとされています。
この記事では、アロエの持つさまざまな健康効果について詳しく解説するとともに、適切な選び方や使用時の注意点についても紹介します。
アロエの効能
● 日焼け、やけど、湿疹の治療
蚊に刺されたり、うっかりやけどをしたりしたとき、家にアロエがあればすぐに役立ちます。葉を一枚切り取り、患部に塗ることで、かゆみや痛みを素早く和らげることができます。アロエには冷却作用があり、傷口をすばやく冷やして炎症や腫れを抑える働きがあります。
ニューヨーク大学が2022年に発表した研究によると、アロエを使って2度のやけどを治療した場合、通常の治療よりも約4日半早く治癒することがわかっています。
また、アロエは日焼けのケアにも効果的です。日本の臨床研究では、アロエステロールを摂取することで、46歳以下の男性の光ダメージを受けた肌の弾力が改善されることが確認されました。
さらに、平均年齢44歳の女性64人を対象とした研究では、アロエステロールを継続的に摂取することで皮膚の水分量や弾力が向上し、真皮層のコラーゲン量が増加することが示されています。
アロエは、日焼けややけどのケアだけでなく、湿疹の改善にも役立ちます。中国・唐代の詩人、劉禹錫(りゅう うしゃく)が記した医学書『伝信方』には、アロエと炙甘草(しゃかんぞう)を粉末にし、温めた豆乳で患部を洗浄した後に塗布することで湿疹が治ると記されています。古くからアロエは、皮膚のさまざまなトラブルに活用されてきたのです。
● 保湿とコラーゲン生成の促進
暑い日に長時間外にいて、肌が日焼けで赤くなってしまったときは、アロエジェルを塗ることで乾燥した肌にうるおいを与え、保湿効果を高めることができます。また、乾燥して皮がむけた唇に塗れば、しっとりとした状態を取り戻し、唇のシワを目立ちにくくする効果も期待できます。
2024年3月に学術誌『Molecules(分子)』に発表された研究によると、アロエ葉エキスとトリメチルグリシン(ベタイン)の混合物を使用することで、水分を細胞内へ運ぶ「アクアポリン(AQP)」というタンパク質の量が最大3.8倍に増加し、肌の水分保持能力が向上することが確認されました。
また、アロエには保湿効果だけでなく、コラーゲンの生成を促進する働きもあります。アロエに含まれる多糖類の一種であるアセチルマンナンには、コラーゲンを作る「線維芽細胞」を増やす働きがあり、これにより肌のハリが向上し、より若々しい印象の肌へと導きます。
● 胃腸の保護
アロエは外用だけでなく、内服することで胃腸の健康をサポートする働きもあります。胃潰瘍や胃の不調がある人にとって、アロエは天然の胃薬のような役割を果たし、胃の粘膜を保護し、傷の回復を助ける効果が期待できます。アロエに含まれる多糖類は、胃腸の粘膜に保護膜を作り、胃酸による刺激を和らげることで、胃潰瘍の症状を軽減し、粘膜の再生を促進します。
研究では、アルコールによって引き起こされた胃潰瘍に対するアロエジェルの治療効果は、胃酸の分泌を抑える薬であるパンプロゾールよりも優れていることが示されました。この効果は、抗酸化作用や胃酸分泌の抑制、細胞死の抑制、創傷治癒の促進によるものと考えられています。
ただし、アロエを内服する際は、必ずジェル部分のみを摂取することが大切です。アロエの葉の外皮とジェルの間にある黄色い部分(ラテックス)には、アントラキノン系化合物が含まれており、強い刺激性や毒性があるため、注意が必要です。
●便秘の改善(特に熱性便秘)
アロエは薬としても使用されており、漢方薬の「当帰龍葵丸(とうきりゅうかいがん)」にも配合されています。アロエには腸の蠕動運動を促し、便通を改善する働きがあり、高齢者や慢性的な便秘に悩む人にとって役立ちます。
アロエの乳液(ラテックス)に含まれるアロエエモジンや、アロエジェルに含まれる多糖類には、便秘を改善する効果があることが知られています。
ただし、アロエに頼りすぎるのは避けるべきです。長期間、腸の動きを外部から刺激し続けると、腸の機能が低下し、自然な排便が難しくなる可能性があるためです。
また、アロエは冷やす性質を持つため、体に熱がこもったことによる便秘(熱性便秘)に適しています。熱性便秘の特徴として、便が硬く大きい、またはコロコロとした羊の糞のような形状になることが挙げられます。一方で、体が冷えていることが原因の便秘(寒性便秘)や、体力が落ちている人の便秘(虚性便秘)には適していません。これらの便秘は、便が柔らかくまとまりにくい、粘り気が強い、すっきり出ないなどの症状があり、アロエを摂取すると逆に下痢を引き起こす可能性があります。
●虫刺されのかゆみ止めと口内炎の改善
アロエには虫刺されによるかゆみを抑え、体内の熱や湿気を取り除く効果があります。蚊に刺されたときに、新鮮なアロエの葉を切って直接塗ると、かゆみが素早く和らぎます。アロエの冷やす性質と苦味には、体内の余分な熱を冷まし、湿気を取り除く作用があり、さらに虫除けの効果も期待できます。
また、アロエの抗菌・抗炎症作用は、口内環境の改善にも役立ちます。中国の古典医学書『本草綱目(ほんぞうこうもく)』には、「アロエを粉末にして虫歯に塗ると効果的」と記されています。現代でも、アロエ成分を配合したマウスウォッシュや歯磨き粉があり、歯茎の炎症や歯垢の蓄積を防ぎ、口内炎の改善にも役立ちます。
研究によると、アロエに含まれるアセチルマンナンには、歯茎の線維芽細胞を増やし、細胞の成長を促すケラチノサイト成長因子(KGF)、血管の形成を助ける血管内皮成長因子(VEGF)、皮膚の弾力を保つI型コラーゲンの生成を促進する働きがあり、口内の傷の治癒を助けることが確認されています。
アロエの選び方と食べ方
アロエには多くの健康効果がありますが、すべての品種が食用に適しているわけではなく、誰でも安全に食べられるわけでもありません。摂取する際には、以下の2つのポイントに注意が必要です。
適切な品種を選び、正しく処理する
アロエにはさまざまな品種がありますが、食用として認められているのは「フェラアロエ(キダチアロエ)」と「ケープアロエ(好望角アロエ)」の2種類のみです。台湾の食品薬品管理署でも、この2種類のみが食用可能と規定されています。なお、フェラアロエは「キラソアロエ」「クルーラソーアロエ」「アメリカアロエ」と呼ばれることもあります。
アロエは適切に処理しなければ健康を害する可能性があります。その理由は、果肉(ジェル部分)と外皮の間にある黄色い乳液(ラテックス)に有害成分(アロエエモジンなど)が含まれているためです。この成分は腸や皮膚を刺激し、腹痛や炎症を引き起こすだけでなく、肝臓や腎臓に悪影響を及ぼす可能性があります。
正しい処理方法は、まず外皮をよく洗い、平らな面に沿って皮をむき、果肉(ジェル部分)をすくい取ります。黄色い乳液(ラテックス)が残らないようにしっかり洗い流した後、一口大に切り、はちみつレモンジュースやヨーグルトに加えると、ひんやりとして爽やかな味わいが楽しめます。初めてアロエを食べる場合は、少量(5グラム程度)から始め、体調に問題がなければ少しずつ増やしてもかまいません。ただし、1日の摂取量は15グラムを超えないようにしましょう。アロエは体を冷やす性質があるため、長期間や大量に摂取すると下痢を引き起こすことがあります。冷えが気になる場合は、加熱してから食べるのもよいでしょう。
また、初めて食べる場合は少量(5グラム程度)から試し、体調に問題がなければ少しずつ増やしてもよいですが、1日の摂取量は15グラムを超えないようにしましょう。
アロエを避けたほうがよい人
アロエは健康に良い食品ですが、体質や状況によっては摂取を控えたほうがよい場合があります。特に、体が冷えやすい人(冷え性・虚弱体質)は、冬になると手足が冷たくなりやすく、夏でも風に当たると寒さを感じることが多いです。また、関節の痛みや腰痛を感じやすい傾向があります。こうした体質の人がアロエを摂取すると、腸が過剰に刺激され、下痢を起こしやすくなることがあります。また、妊婦にとって、アロエには子宮を収縮させる可能性があり、胎児に影響を与えるおそれがあるため、妊娠中の摂取は避けたほうがよいとされています。
(翻訳編集 華山律)













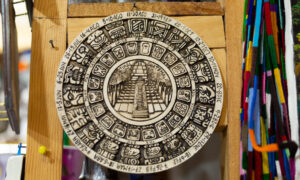










 ご友人は無料で閲覧できます
ご友人は無料で閲覧できます Line
Line Telegram
Telegram




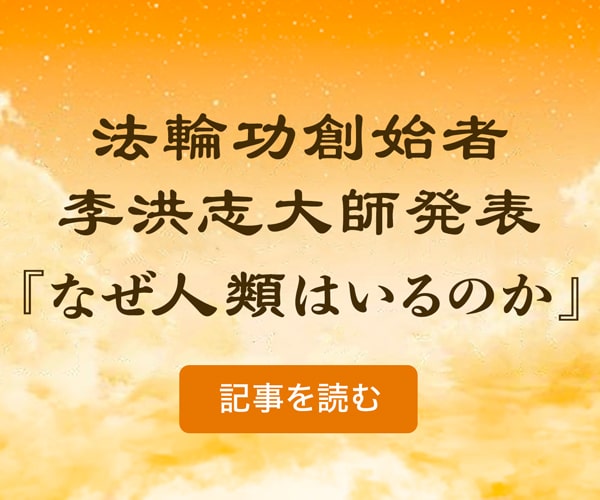
ご利用上の不明点は ヘルプセンター にお問い合わせください。