梅雨の時期、しとしとと降る雨に濡れながら咲く紫陽花(あじさい)は、日本の風景にしっとりと溶け込む、季節の象徴的な花です。その色と形の移ろいは、古来より日本人の繊細な感性を刺激し、詩や歌に詠まれてきました。
紫陽花はただの観賞花ではなく、人の心、季節の気配、時の流れを象徴し、静かに咲き続け、日本人はそれを愛でいくつかの歌で表現してきました。紫陽花が和歌の題材としてはじめて登場したのは奈良時代でした。
日本最初の和歌集『万葉集』では、橘諸兄(たちばなのもろえ)が次のように詠んでいます。
紫陽花の 八重咲くごとく 弥(いや)つ代にを いませ我が背子 見つつ偲はむ
(あじさいの やえさくごとく やつよによ いませ わがせこ みつつしのはむ)
弥つ代とは長い年月という意味で「紫陽花のように幾重にも咲き重なるように、あなたとの日々が末永く続きますように」との願いが込められています。

紫陽花の「八重に咲く」姿に、親密さや深い愛情、繁栄、長寿への祈りを重ね合わせ、温かさを感じさせる歌といえるでしょう。

紫陽花が、1年の時代に、このような優しいまなざしで詠まれていたことは、日本文化の自然観や人との関係性への深い洞察を感じさせます。
また江戸時代の俳諧歌人「奥の細道」で有名な松尾芭蕉は次のように詠んでいます。
紫陽花や 帷子時の 薄浅黄
(あじさいや かたびらどきの うすあさぎ)
「帷子時」は夏の衣替えの頃を指し、淡い黄色(薄浅葱:淡い青色の解釈もある)の紫陽花の色と道行く人々の衣の色が重なる風情を詠んでいます 。

芭蕉は紫陽花の歌をもう一句詠んでおり
紫陽花や藪を小庭の別座舗
(あじさいや やぶをこにはの べつざしき)
自然のままの庭に佇む紫陽花が、わざわざ飾らずとも美しい「別座敷」となっている情景を表現しています。

一方で時代が下り、明治の俳人・正岡子規は、紫陽花を人の心の不確かさや無常の象徴として詠んでいます。
紫陽花や 昨日の誠 今日の嘘
(あじさいや きのふのまこと けふのうそ)
紫陽花の色が咲いてから日を追って変わっていくように、人の誓いや愛情もまた変化しうるという、人間の心の脆さや儚さを読み取った句です。

橘諸兄の歌が「永遠」や「重なり続く幸せ」を象徴していたのに対し、子規の句は「変わりゆくもの」への静かな諦観を含んでいます。
このように、同じ紫陽花であっても、時代や詠み手によって意味合いが大きく異なってくるのは、和歌が日本人の心を捉えて離さない理由のひとつと言えるでしょう。
この梅雨の季節、紫陽花を眺めながら、そうした古の日本人が和歌で表現したきた空気感、奥行きに思いを馳せてみてはいかがでしょうか













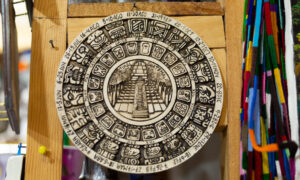







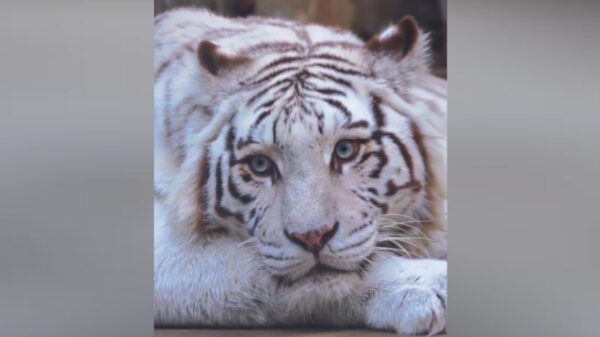


 ご友人は無料で閲覧できます
ご友人は無料で閲覧できます Line
Line Telegram
Telegram





ご利用上の不明点は ヘルプセンター にお問い合わせください。