栄養学の博士号を持つシーナ・マカロウさんと一緒に、食事と健康について考えてみましょう。彼女は科学的な視点で、健康的で幸せな生き方のヒントをお届けします。
世の中にあふれる健康アドバイスを試しても、「なんだか自分には合わない」と感じたことはありませんか? それもそのはず。ほとんどの科学的研究や健康ガイドラインは「平均的な人」に向けて作られたもの。でも、あなたは「平均的な人」ではありませんよね。
どんなに優れた研究や指針も、「あなたの体にとって本当にベストな方法」を教えてくれるわけではありません。だからこそ、自分の体の特徴を知り、体の声を聞くことが大切です。今日から、自分の体の専門家になる一歩を踏み出してみませんか?
個人の健康における科学の限界
私は栄養学の博士号を持ち、長年にわたり研究室での実験を通じて、データの重要性や科学的根拠に基づく結論の価値を深く学んできました。しかし、個人の健康に関しては、科学にも限界があることを実感しています。
科学者が研究を行う際、多くの人に当てはまる結論を導き出すために、研究の条件を統一し、個人差が結果に影響しないよう調整します。そのため、研究対象を選ぶ際には、特定の条件を満たす人だけを参加させ、選定基準に当てはまらない人々(平均的な傾向から外れる人々)を除外することがよくあります。
たとえば、カフェインの代謝が極端に遅い、または速い人、あるいはストレスや薬の影響を受けやすい不安傾向のある人はどうなるでしょうか? こうした人たちは、研究の対象から外されたり、そもそも研究に選ばれなかったりすることが多いのです。そして、もし自分の特性が研究で考慮されていなければ、その研究結果は必ずしも自分に当てはまるとは限りません。
さらに、研究の基準に合致した人々の間でも、体の反応には大きな個人差があります。
今から約20年前、私はボストンで開催された「100歳まで健康に生きる」という会議に参加しました。その中で特に印象に残った研究があります。それは、オメガ3脂肪酸を摂取するとコレステロールや中性脂肪の値が下がるという仮説を検証したものでした。しかし、結果は一律ではありませんでした。
参加者の約3分の1は、予想通りコレステロールや中性脂肪が減少しました。別の3分の1は、まったく変化がありませんでした。そして、残りの3分の1は驚くべきことに、コレステロールや中性脂肪の値が上昇してしまったのです。
これは、重要な事実を示しています。つまり、同じ栄養素でも、人によって体の反応は異なるということです。ある人には驚くほど効果がある一方で、別の人にはまったく効果がなく、場合によっては害になることさえあります。
それにもかかわらず、医療機関や政府機関は、こうした「平均的なデータ」を基に標準的な健康指針を作り上げています。しかし、それでは個々の体質に合わないアドバイスを押しつけることになり、場合によっては健康を損なうリスクすらあるのです。
「万人向け」の健康法がうまくいかない理由
1型糖尿病の患者の中には、低炭水化物の食事を取り入れることで血糖値を安定させ、体調が改善したという人がいます。しかし、この方法は標準的な治療指針とは異なるため、一部の医師は患者や糖尿病の子供を持つ親に対して、「低炭水化物の食事をやめるように」と指導することがあります。
この事例が示しているのは、標準化された健康指針が個々の違いを十分に考慮していないことが多いという事実です。その結果、患者やその家族は、「自分たちにとって効果的な方法」と「公式ガイドラインに従った方法」の間で板挟みになってしまうことがあります。
結果は?
フラストレーション、混乱、自信喪失。本来は助けになるはずの「健康のためのアドバイス」を実践してもうまくいかないと、自分が間違っているのではないか、あるいは自分の体に何か問題があるのではないか、と感じてしまうのも無理はありません。でも、問題はあなたではありません。問題は、「個人」よりも「平均」を優先するシステムなのです。
あなたの体をオーケストラに例えてみてください。消化器系から内分泌系まで、すべてのシステムが調和して機能し、あなた独自の健康のシンフォニーを奏でているのです。
たとえば、腸内環境(マイクロバイオーム)は指紋のように一人ひとり異なり、同じ食べ物でも、人によって体への影響がまったく違います。また、体内の栄養バランスも重要です。マグネシウムが不足しているのか、それともビタミンB群が豊富なのか——その違いだけでも、体の働きは大きく変わります。
さらに、遺伝的な要素、環境要因の影響、ストレス、運動習慣、肝臓の解毒機能などが複雑に絡み合い、科学的に完全に解明するのが難しいほどの「体のシンフォニー」を作り上げています。食物過敏や消化酵素の働きも影響し、「ある人にとってのスーパーフード」が、別の人にとっては害になることもあるのです。
たとえば、私はかつて「鶏肉」を食べると体調を崩していました。 一般的に鶏肉は健康的な食材とされていますが、私の体には合わず、全身の炎症を引き起こしてしまったのです。この経験から学んだのは、「どんなに健康に良いとされる食べ物でも、自分に合わなければ害になる」ということでした。
私たちの体は非常に複雑で、平均値をもとにした科学的な分析だけでは、そのすべてを理解することはできません。科学や専門家は、善意のもとで難しいデータを実用的なアドバイスとして単純化しますが、その過程で、意図せず「一律のルール」に無理に当てはめようとしてしまうことがあります。
しかし、本当に大切なのは、決められたルールに無理に従うのではなく、自分らしさを受け入れながら、自分に合った健康法を見つけていくことなのかもしれません。
自分の健康を理解する「専門家」になる
科学はあくまで「手段のひとつ」であり、すべてではありません。そして、最も強力な手段のひとつが「自分の体のサイン」です。私たちの体は常に何かを伝えようとしています。そのサインに気づき、その意味を理解することができれば、あなた自身が自分の健康の専門家になれるのです。
もし直感を信じて、自分に合う健康法を見つけることに挑戦したいなら、まず試してみるべき基本的なステップを紹介します。
1. 自分の体の声を聞く
何かを変えようとする前に、まずは自分の体のサインに気づく習慣を身につけましょう。最初の目的は、すぐに改善しようとするのではなく、「体が発している小さなサインに気づくこと」です。
日常のあらゆる場面で、自分の体がどのように反応しているか、注意深く観察してみましょう。食事をしたとき、運動をしたとき、人と会話をしたとき、テレビを見ているとき、そのたびに、自分の感覚を意識してみてください。
例えば、特定の食べ物を食べた後に、元気が出たり、逆にだるくなったりすることはありませんか? 運動をしてスッキリする日もあれば、翌日疲れが抜けないこともあるなら、睡眠やストレスなどの影響を検討してみましょう。また、会話やテレビ番組を見た後に気分が落ち込んだり、不安になったりしたら、その気持ちを記録してみるのも良い方法です。
こうしたサインに気づくことで、自分にとって何が本当に合っているのかが見えてきます。
2. 小さなことから始める
一度にすべてを変えようとせず、無理なく取り組める小さな変化から始めましょう。まずは、ひとつのことに焦点を当ててみてください。例えば、新しいサプリメントを試す、特定の食べ物を増やしたり減らしたりする、新しい運動を取り入れる、朝日を浴びる、寝る2時間前にスマホやパソコンの画面を見るのをやめるなど。
そして、その変化が自分の体にどんな影響を与えるのかを観察してみてください。エネルギーのレベル、気分、消化の調子、お通じ、睡眠の質、頭のスッキリ感など。
新しい食習慣を試す際は、次の変更を加える前に、最低でも3週間の間隔を空けることが大切です。なぜなら、特定の食品過敏症では、反応がすぐに出るとは限らず、症状が遅れて現れることがあるからです。
3. 比べるのではなく、好奇心を持つ
健康に関する流行や「万人向け」のアドバイスがあふれる世の中では、周りに流されがちです。友人がある食事法で調子が良くなったからといって、それがあなたにも合うとは限りません。特定のサプリメントを絶賛する人がいても、それが自分に効果的とは限らないのです。それで大丈夫なのです。
大切なのは、「他の人と比べる」のではなく、「自分の体に好奇心を持つ」ことです。「どうして私には合わないんだろう?」ではなく、「私の体は何を伝えようとしているんだろう?」と考えてみましょう。
周りと違っていても、気にする必要はありません。健康とは、誰かのやり方に合わせることではなく、「自分にとって一番心地よい方法」を見つけることだからです。
自分の体の個性を受け入れ、じっくり向き合ってみてください。それは、新しい友人と信頼関係を築くようなもの。時間はかかるかもしれませんが、その過程には大きな価値があります。科学は役立つヒントを与えてくれますが、本当にあなたに合うかどうかを決めるのは、あなたの体そのものです。自分の体を信じ、その声に耳を傾け、自分らしい健康のリズムを大切にしましょう。
あなたの体験をシェアしよう
質問 一般的な健康アドバイスとは異なっていても、自分には驚くほど効果があった習慣や食べ物、健康法はありますか?
ぜひ、あなた自身の体験や気づきをコメントでシェアしてください。みんなで固定観念にとらわれず、新しい視点を見つけていきましょう!
免責事項
この記事の情報は教育目的で提供されており、シーナ・マカロウ(PhD、科学者)さんの個人的な見解を反映したものです。医療的な助言ではなく、医師の診察や専門的な指導の代わりとなるものではありません。食事、薬、ライフスタイルを変更する前に、必ず医療専門家に相談してください。本記事の情報は、自己責任のもとで活用してください。
この記事で述べられている意見は著者の意見であり、必ずしもエポックタイムズの意見を反映するものではありません。エポックヘルスは、専門的な議論や友好的な討論を歓迎します。
(翻訳編集 華山律)













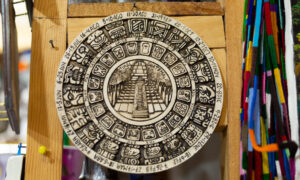










 ご友人は無料で閲覧できます
ご友人は無料で閲覧できます Line
Line Telegram
Telegram





ご利用上の不明点は ヘルプセンター にお問い合わせください。