糖尿病は近年ますます深刻化している生活習慣病ですが、発症前の「境界型糖尿病」(前糖尿病)の段階で高血糖が見つかった場合、適切な対策をとれば改善できる可能性があります。この段階では、生活習慣や食事を見直すことが大切です。また、中医学では体質を整えるための健康茶も役立つとされています。
高血糖の主な原因 食生活の乱れ・睡眠不足・肥満
食事をすると血糖値が上がり、体はインスリンを分泌して血糖をエネルギーとして利用できるようにします。しかし、必要以上に血糖が増えると、余った分が脂肪として蓄えられます。この仕組みにより、血糖値は通常、一定の範囲に保たれます。しかし、「インスリン抵抗性」が原因で高血糖が続くと、体の細胞がインスリンの働きをうまく受け取れなくなり、糖尿病のリスクを高めます。
翰鳴堂(かんめいどう)クリニックの頼睿昕(らいえいきん)院長は、インスリン抵抗性を引き起こす主な要因として、以下の3つの食習慣を挙げています。
- 食事の内容:現代の食生活では、手軽で便利な加工食品やファストフードを好む人が多くなっています。こうした食品は栄養が偏りやすく、血糖値を急激に上げやすい傾向があります。
- 食べる量:ストレス解消のために食べすぎたり、間食をとりすぎたりすることも、インスリンの働きを悪化させる原因になります。
- 食べる頻度:朝食、昼食、午後の軽食、夕食、夜食と、1日を通して何度も食べると、血糖値が常に高い状態になりがちです。特に、血糖値を急上昇させる食品(GI値が高い食品)を頻繁に食べると、血糖が急激に上がり、それを下げるためにインスリンが大量に分泌されます。その結果、血糖値が急降下し、また空腹を感じて食べたくなる、という悪循環が起こります。
インスリン抵抗性を引き起こすその他の要因として、体内の炎症があります。夜更かしやストレスは炎症を悪化させる原因となります。また、体脂肪が多いとインスリンの働きが弱まり、肥満の人は高血糖や糖尿病になりやすい傾向があります。
食事の順番を工夫して血糖値をコントロール
高血糖は、体の機能が乱れ、血糖値をうまく調整できなくなっている状態です。この状態を改善するには、日常生活を見直し、いくつか工夫をすることが大切です。
まず、食事の順番を意識しましょう。多くの人は「ご飯を一口、野菜を一口」と交互に食べることが多いと思いますが、高血糖が気になる人の食事の順番は「野菜→たんぱく質→炭水化物」の順番で食べることです。
野菜は糖質が少なく、食物繊維が豊富なため、糖の吸収をゆるやかにしてくれます。たんぱく質には血糖値の急上昇を防ぐ「クッション効果」があり、食後の血糖値の変動を抑えてくれます。すでに野菜やたんぱく質を食べてある程度満腹感が得られているため、炭水化物を食べすぎるのを防ぐことができます。
炭水化物は少なめにするのが理想ですが、完全に抜くのは逆効果です。特にご飯(白米)は大切な主食であり、「糖尿病の人でも適量は必要」と頼睿昕(らいえいきん)医師は言います。中医学の観点からも、白米は栄養が豊富で、胃腸を整える働きがあるため、適量を守って食べることが推奨されます。
また、血糖値のコントロールには運動の習慣をつけることも重要です。運動をすると筋肉量が増え、体脂肪が減るだけでなく、細胞がインスリンをより効率的に利用できるようになり、インスリン抵抗性の改善につながります。さらに、夜更かしを避け、質の良い睡眠をとることも大切です。しっかり眠ることでホルモンバランスが整い、インスリンの働きがスムーズになります。

食品のGI値(血糖値の上がりやすさ)は?4つのポイントで簡単に判断
血糖値を安定させるためには、GI値(グリセミック・インデックス)の低い食品を選ぶことが大切です。GI値が低いほど血糖値の上昇がゆるやかになり、高血糖を防ぎやすくなります。では、どのようにGI値の高低を判断すればよいのでしょうか?ここでは4つのポイントをご紹介します。
1.食物繊維の含有量:食物繊維が多い食品はGI値が低く、少ない食品はGI値が高くなります。例えば、白パンに比べて全粒粉パンは食物繊維が多いため、血糖値の上昇がゆるやかになります。
2.調理方法:同じ白米でも、白ご飯とおかゆではGI値が異なります。おかゆは米がやわらかく煮崩れており、消化・吸収が早いためGI値が高くなります。一方、パスタは比較的硬く、噛みごたえがあるためGI値が低めですが、長時間茹でてやわらかくするとGI値が上がります。
3.加工の度合い:できるだけ加工されていない「原形に近い食品」を選ぶのがポイントです。例えば、ご飯と麺を比べると、ご飯は精米された白米ですが、麺はさらに加工されているため、GI値が高くなりやすい傾向があります。
4.熟成度(食品の成熟度):果物は熟すほどGI値が高くなります。例えば、熟れたバナナはGI値が高めです。頼睿昕(らいえいきん)医師によると、「果物は糖分を多く含むため、高血糖の人は食べ過ぎに注意する必要がある」とのことです。
特に甘みの強い果物は血糖値を上げやすいため、高血糖が気になる人にはグァバ、りんご、グリーンキウイなどが適しています。また、果物の摂取量は通常の半分にするか、場合によっては一時的に控えるのも一つの方法です。

体質に合った健康茶で高血糖を改善
糖尿病の前段症状の人が中医学による体質改善を取り入れることで、糖尿病への進行を防ぐことができます。高血糖の人は中医学の治療を受け、自分の体質を理解した上で、日常的に適した健康茶を飲むことで体を整えることができます。
以下に紹介する3種類の健康茶は、普段から飲むことができ、1日1回を目安に取り入れるのがおすすめです。作り方は、すべての材料を鍋に入れ、水1500mlを加えて沸騰させます。火を止めた後、そのまま10分間蒸らし、茶こしでこして飲みます。頼睿昕医師によると、中医学では「弁証論治(べんしょうろんち)」という考え方があり、体質に応じたお茶を飲むことで体のバランスを整え、細胞のインスリン抵抗性を改善することができるとされています。
1. 沙参麦冬湯(しゃじんばくとうとう)
適した体質:陰虚燥熱(いんきょそうねつ)タイプの高血糖の人に向いています。具体的な症状としては、口や喉の渇き、便秘、尿の量が少ない、手足がほてる、寝汗、動悸、生理不順、胃の張り、乾いた咳などが挙げられます。
材料:沙参(しゃじん)5g、麦門冬(ばくもんどう)5g、玉竹(ぎょくちく)5g
沙参は体の乾燥を潤し、のどの渇きを癒す働きがあります。玉竹は陰を養い、潤いを与え、麦門冬は肺と胃を潤して、陰虚燥熱の体質を改善します。
このタイプの人は体に熱がこもりやすいため、血糖値を下げる作用がある冷性の食品、例えば山苦瓜(ツルレイシ)を食べるのもおすすめです。
2. 黄耆生脈飲(おうぎしょうみゃくいん)
適した体質:気陰両虚(きいんりょうきょ)タイプの高血糖の人に向いています。体が重くだるく感じやすく、すぐに空腹を感じる、疲れやすいといった特徴があります。また、虚寒(きょかん)タイプの人にも適しており、冷えやすい、腰や膝がだるい、下痢をしやすい、女性の場合は水っぽいおりものが多いといった症状が見られます。
材料:麦門冬(ばくもんどう)5g、黄耆(おうぎ)3g、西洋参(せいようにんじん)3g、五味子(ごみし)2g
麦門冬は乾燥を防ぎ、黄耆は免疫を調整する働きがあります。西洋参は気を補い、潤いを与え、五味子は気を補い、腎陰を養うことで、疲労感や体力の低下を改善します。

3. 陳皮佛手疏肝飲(ちんぴぶっしゅそかんいん)
適した体質:肝鬱脾虚(かんうつひきょ)タイプの高血糖の人に向いています。情緒が不安定になりやすく、食欲がない、食べる量は少ないのに血糖値がなかなか下がらないといった特徴があります。
材料:陳皮(ちんぴ)3g、佛手(ぶっしゅ)3g、茉莉花(まつりか/ジャスミン)3g
陳皮は気の巡りを良くし、胃腸の働きを整えます。佛手は肝の働きを助け、消化を促します。茉莉花は肝の気を調和させる作用があり、ストレスによる不調を和らげます。
(翻訳編集 華山律)













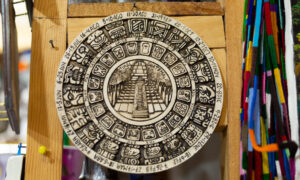










 ご友人は無料で閲覧できます
ご友人は無料で閲覧できます Line
Line Telegram
Telegram




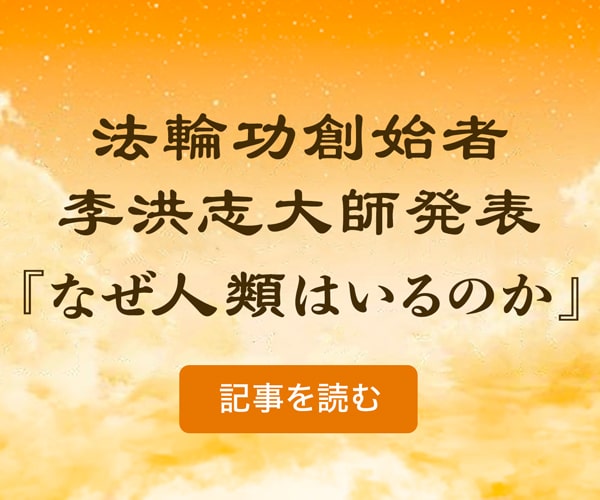
ご利用上の不明点は ヘルプセンター にお問い合わせください。