なぜ春に桜餅がぴったりなのか?
清明のころ、桜が咲き誇り、自然がいきいきと芽吹く一方で、春は「肝」の働きが活発になりやすく、また湿気が多くなることで「脾」(胃腸)に負担がかかる季節でもあります。
「肝」は気の巡りを司り、ゆるやかな状態を好みますが、ストレスや時候の変化などで体調が乱れると、イライラ・食欲不振・目の乾き・めまいなど、さまざまな不調につながります。
そんな季節に寄り添うのが、日本の春の伝統和菓子「桜餅」です。これは単なる季節菓子ではなく、“薬食同源”の知恵が息づく薬膳菓子ともいえる存在です。
桜餅に使われる小豆は、「心の穀物」「補血の豆」とも呼ばれ、古代中国・戦国時代の名医・扁鵲による名方《三豆飲》にも登場し、湿を取り除き、毒を排出し、血を養う主役の食材とされています。もち米粉は脾を助けて気を補い、胃腸をあたためて調子を整える働きがあり、外側を包む桜の葉には、ほのかな香りとともに肝の気をゆるやかにし、胃を整える力があります。これらの素材が合わさることで、肝のバランスをととのえ、春のだるさや湿気による不調をやさしく和らげてくれます。
ひとくちの桜餅に、春の肝ケア・脾の養生・血の補い・湿の排出という、やさしい薬膳の心が込められているのです。
桜餅の簡単レシピ

〈材料(約6個分)〉
- 道明寺粉(もち米を粗く砕いたもの) 100g
- 水 120ml
- 砂糖 20g(甘さはお好みで調整)
- あんこ(粒あんまたはこしあん) 150g(1個あたり約25g)
- 桜の葉の塩漬け 6枚
〈作り方〉
1.塩漬けの桜の葉は水に15分以上浸けて塩分を抜いておく。
2.道明寺粉をぬるま湯に15分ほど浸し、その後20分ほど蒸して、や わらかく透明になるまで加熱する。
3.蒸した道明寺粉に砂糖を混ぜ、粗熱を取る。
4.道明寺生地を6等分し、それぞれにあんこを包んで丸く平たく整え る。
5.桜の葉の表側を外にして包む。香りも見た目も楽しめる仕上がり に。
6.粗熱が取れたら、春の香りとともにどうぞ召し上がれ。
アレンジのヒント
- 桜の葉が手に入らない場合:
しそで代用可能。香りがよく、肝をいたわる効果も。
- 道明寺粉がないとき:
白玉粉に少量の葛粉を混ぜて蒸しても、近い食感に仕上がります。
- 低糖アレンジ:
砂糖を減らし、ほんのり甘いあんこを使えば、味わいはそのままにヘルシーに。
食材の効能
- 小豆(あずき):利尿作用があり、体内の湿気を取り除く。脾を 助け、血を補う。
- もち米(道明寺粉):脾を補い、気を養い、胃腸を整え、軟便や 下痢の改善にも効果がある。
- 桜の葉(塩漬け):温性の食材。肝の気を整え、香りで気の巡りを良くし、血行や経絡の流れを促進します。胃腸をいたわり、心を安定させ、消化を助けます。
- 赤しそ(お好みで):気の巡りを整え、胃腸の働きを整える。寒気を放出し、湿気を取り、消化を促進します。桜の葉と併用すことで肝のケア効果が さらに高まります。
注意点(体質に合わせて調整を)
- 糖尿病の方、血糖コントロール中の方:
砂糖の使用は控えめにするか、代替え甘味料を使い、少量ずつ楽しんでください。
- お腹が張りやすい、ゆるくなりやすい方:
もち米は消化しにくいため、少量にとどめるか、温かいしょうが茶と一緒に食べるとよいでしょう。
相性のよいお茶
- 桜ほうじ茶:桜の香りが肝の気をほぐして気分を和らげ、ほうじ茶のやさしい温かさが脾胃を助けます。もち米などの“もちもち食材”との相性も良く、脾胃が弱く冷えやすい方におすすめ。
- 黒豆茶:体内の湿気を取り、むくみを軽減。腎と肝を補い、気の巡りを整える。脾の働きが弱く、湿気がたまりやすい方や、肝・腎の衰弱による目の乾燥が気になる方におすすめ。
- しそ茶:春のアレルギー症状をやわらげる。肝のストレスを和らげながら、風邪予防や消化促進にも。
- 陳皮緑茶:湿気・熱を取り除き、胃腸の調子を整える。ストレスがたまりやすく、むくみやすい方にぴったり。













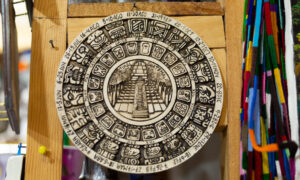




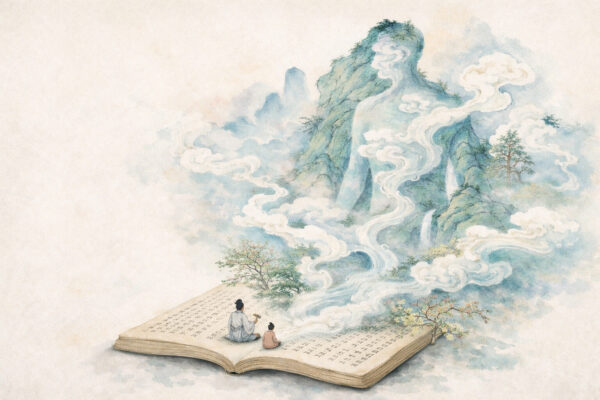





 ご友人は無料で閲覧できます
ご友人は無料で閲覧できます Line
Line Telegram
Telegram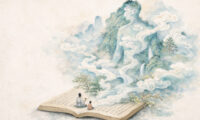





ご利用上の不明点は ヘルプセンター にお問い合わせください。