梅雨入りとともに、私たちはなんとなく体が重く感じたり、食欲がわかず、疲れやすく、気分が沈みがちになったりします。ときにはイライラしたり、夜もぐっすり眠れないこともあるでしょう。
湿気の悪影響 肝と脾のバランスが乱れる
これは実は、体内に「湿気」がこっそり入り込んで悪さをしているのです。中医学では、脾と胃は五行で「土」に属し、湿気は土と響き合いやすいため、消化器系に入り込みやすく、脾胃の働きを鈍らせ、消化吸収の力を弱めてしまいます。同時に、肝の気の流れも妨げられ、気分がふさぎ、胸が重くなる原因にもなります。肝の気が滞ると、気血の巡りが悪くなり、脾胃の働きがさらに低下して、体内にもっと湿気をため込むようになります。だからこそ、肝と脾のバランスを整えることが大切です。
中医学の言葉に「肝は伸びやかさを好み、脾は温かく養われることを好む」という教えがあります。肝は自由に流れることを好む子どものようで、抑えつけられることに弱く、脾は寒さを嫌うおばあさんのようで、温かく丁寧にいたわることで、食べ物をしっかりエネルギーに変えてくれるのです。
そこで今回ご紹介するのが「和風茶葉卵」です。これは、中国の茶葉卵の薬膳の知恵と、日本の出汁文化を融合させたものです。シンプルな材料である卵と茶葉、昆布、かつお節を使い、脾胃を調え、肝の気を整え、心を落ち着かせ、気血をやさしく補う、心温まる小さな薬膳料理です。
なぜ「お茶+卵」ではなく、「お茶で卵を煮る」のか?
「卵を食べて、お茶を飲めば同じことじゃないの?」と思うかもしれません。
でも中医学の観点から見ると、実はその差はとても大きいのです。
お茶は薬性がやや寒性寄りで、心・肺・胃に作用し、熱を取り去って気を巡らせ、水分代謝を促し、体内の余分な熱を下げる効果があります。一方、卵は気血を補う滋養のある食材で、やや濃厚で栄養密度も高めです。
これらを別々に摂ると、特に空腹時や食後すぐにお茶を飲むと、まずお茶の寒性が胃に入って脾の陽気を傷め、そのあとに食べる卵の栄養も吸収されにくく、逆に湿気の中で詰まってしまい、胃の張りや気だるさ、倦怠感を引き起こしやすくなります。
脾胃はちょうど「かまど」のようなもので、ちょうど火をつけて(=卵を食べて)料理をしようというときに、冷水(=お茶)をぶちまけてしまうと、火力が弱まり、食べ物がちゃんと調理(=消化吸収)されなくなるのです。
しかし「お茶で卵を煮る」と、お茶の寒と卵の温、清と補い合い、調和されます。お茶は煮込むことで寒性が和らぎ、刺激が少なくなり、卵はその温かく穏やかな茶の中で薬効を吸収し、重たさを取りながらも乾燥しすぎず、清らかで滋養にもなる、絶妙なバランスが生まれます。
これが中医学で言う「水火の調和、寒熱のバランス」。清熱と補気が共存し、脾を傷めず、胃にも負担をかけないのです。
では紅茶や焙じ茶のような温性の茶でも煮る必要があるの?
紅茶や焙じ茶、烏龍茶などはたしかに寒性が少なく、比較的温和です。
ただ、どんなお茶でも「気を上に散らす」性質があり、たとえ温性であってもそのまま飲めば、体表の気血が発散されやすく、特に虚弱体質や湿気の多い体質の人には、頭がぼーっとしたり、口が渇いたり、動悸が起きることもあります。
その点、こうしたお茶を煮ることで、脾胃にやさしく届き、温めながら潤いを与え、気をめぐらせて神経を落ち着かせる効果が期待できます。
さらに、昆布やかつお節といった「和風出汁」を合わせることで、まるで温かい海が卵を支えてくれるように、味にも深みが出て、滋養効果もより高まります。かつお節は肝を整え陽気を補い、昆布は腎を養い肝を助け、気血の流れを促進します。これはまさに、梅雨の時期に不足しがちな陽気を補い、肝脾のバランスを整えてくれる理想的な食養生です。
鍵は「脾胃のかまど」を守ること
中医学では、脾胃を「中焦」と呼び、全身の気血エネルギーの源とされています。それはちょうど、温かいかまどのようなもの。空腹時や食後に冷たいお茶を飲めば、その火を消してしまい、脾胃が力を失い、湿気が入り込みやすくなるのです。
だからこそ「お茶で卵を煮る」という方法が生きてきます。そこに生姜、シソの葉、陳皮、クコの実など、脾を健やかにし湿気を取り除く食材を加えれば、体を内から温め、気の巡りを良くし、心を落ち着かせてくれます。体が温まりすぎず、冷えすぎず、バランスの取れた状態を保てるのです。
なぜ卵を煮るのに、こんなに気を配るのか
「たかが卵一個、そんなにこだわる必要があるの?」とよく聞かれます。
でも、これは「こだわり」ではなく「思いやり」なのです。
湿気が続く季節、私たちの体も心も、お腹をやさしく撫でてもらったり、太陽の光を浴びたり、ふさぎ込んだ気持ちを整えてもらったりと、ちょっとした気遣いを必要としています。
料理は、そんなときにそっと寄り添ってくれる「やさしい手」のようなもの。何も難しい理屈を語らなくても、自然と乱れた体のリズムを整えてくれます。
茶葉卵に、玄米ごはんや山芋のみそ汁を添えれば、体が「目覚める」ような家庭の養生ごはんが完成します。とてもシンプルだけれど、そこには確かな力があります。
もしよければ、次に紹介する三種類の体質別の茶葉卵を試してみてください。脾虚湿困タイプ、肝うつ気滞タイプ、陰虚内熱タイプ、それぞれに合わせた簡単レシピで、材料も手に入りやすいものばかりです。
一、脾虚湿困タイプの人
- 梅雨の時期にだるくなりやすく、手足が重いと感じる人
- 下痢しやすく、消化不良になりやすい人
- 舌苔が厚く白っぽい、気血が不足して顔色が黄色っぽい人

材料(卵2個分):
- 卵 2個
- 焙じ茶 小さじ1(またはハトムギ茶ティーバッグ1個)
- 乾燥生姜スライス 2枚
- シソの葉 2枚(または乾燥シソ粉 少々)
- 昆布 2cm角の小片
- かつお節 ひとつまみ
- 塩 少々
- 薄口醤油 小さじ1
作り方:
- 卵をゆでて、殻を軽く割っておく。
- 出汁を別鍋で作る:水約250ccに焙じ茶、昆布、生姜、シソ、かつお節を入れ、弱火で10分煮る。
- こしてから、醤油と塩を加えて味を調える。卵を加え、弱火でさらに20分煮込み、その後数時間〜一晩漬けておくとより美味しくなる。
効果:
この卵は、まるで気の利いたお兄さんのように、そっと脾胃を温め、体内のジメジメした重だるさを追い払ってくれます。生姜は小さな火種のように温め、ハトムギは水気を吸い取る綿布のように湿を吸収し、シソは窓を開けて空気を通してくれる風のように、湿を外へ流してくれる頼もしい存在です。
二、肝うつ気滞タイプの人
- 仕事のストレスが強く、ため息が多く、イライラしやすい人
- 女性で乳房の張りや痛み、生理不順がある人
- 梅雨時に気分が沈みやすく、食欲がわかない人

材料(卵2個分):
- 卵 2個
- 焙じ茶(または柚子入り緑茶) 小さじ1
- 柚子の皮 適量(数本削ったもの)
- シソの葉またはミントの葉 2枚
- 陳皮(乾燥したみかんの皮) 小片1枚(なければ省略可)
- 昆布 小片
- かつお節 少々
- 薄口醤油 小さじ1
- 塩 少々
作り方:
- 卵をゆで、殻を軽く割っておく。
- 出汁作り:茶葉、昆布、かつお節、シソ、柚子皮などを水250mlで沸かし、弱火で10分ほど煮る。
- こしてから醤油と塩で味を調え、卵を加えてさらに10〜15分煮る。できれば一晩漬けて味を染み込ませる。
効果:
この卵は、まるで心の中をやさしく洗い流してくれるような存在です。シソや柚子の皮は、まるで窓から吹き込むそよ風のように、胸にたまった鬱々とした気持ちを少しずつ解きほぐしてくれます。陳皮もまた「気の巡りを整え、滞りを取り除く」作用があり、気分が落ち込みがちで、胃が張って食欲が出ないときにぴったりです。
三、陰虚内熱タイプの人
- 体が熱っぽく、顔が赤くなりやすい、口が渇く人
- イライラしやすく、夢が多くて眠りが浅い、寝汗をかく人
- 舌が赤く苔が少なく、体が乾燥気味な人

材料(卵2個分):
- 卵 2個
- 玄米茶 小さじ1
- 乾燥百合の花 ひとつまみ
- 麦門冬(ばくもんどう) 3~5粒
- クコの実 少々
- 昆布 小片、かつお節 少々
- 塩 少々、薄口醤油 1/2小さじ
作り方:
- 卵をゆでて、殻を軽く割る。
- 出汁:玄米茶、百合、麦門冬、昆布、かつお節などを水250ccで弱火で10分煮る。
- こしてから調味料を加え、卵を入れて15分煮込む。そのまま数時間浸けるか、冷蔵して冷やして食べてもよい。
効果:
この卵は、熱くなりすぎた心にそっと風を送ってくれる「うちわ」のような存在です。百合と麦門冬は、初夏の夜に吹く涼風のように、体の中にこもった熱をやさしく落ち着け、心を穏やかにしてくれます。クコの実はほんのり甘く、肝を補い目も潤し、夜の眠りをより穏やかにしてくれます。
ミニアドバイス
- 出汁の材料はあらかじめ煮出して冷蔵保存すれば2〜3日もちます。いつでも温めて卵を浸けられます。
- 体質は一つに固定されるものではありません。自分の調子に合わせてレシピを使い分けましょう。
- お粥や山芋のおにぎりと合わせれば、梅雨の時期にぴったりのやさしいお昼ごはんになります。
- 子どもや高齢者が食べる場合は、味付けを薄めにして、温かいうちに出すのがおすすめです。
(翻訳編集 華山律)













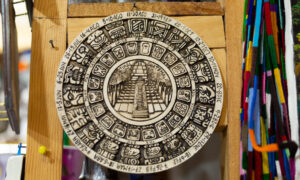










 ご友人は無料で閲覧できます
ご友人は無料で閲覧できます Line
Line Telegram
Telegram





ご利用上の不明点は ヘルプセンター にお問い合わせください。