夏が訪れると、日本の和菓子店はひっそりと涼やかな緑色に彩られます。抹茶大福、抹茶羊羹、抹茶アイスクリーム――そして冷たい水の中にも、ほのかな茶の香りが漂います。さらに、ほぼ欠かさず登場するのが小豆。こしあん、つぶあん、寒天と合わせたものなど、甘すぎず、ひんやりとした中にほんのり温もりを感じさせ、どんなに風が強くても日差しが強くても、心に静けさと安らぎをもたらしてくれます。
多くの中国の人々が不思議に思うことがあります。「日本には豆類を使った食品がたくさんあるのに、なぜ緑豆がないのか?」と。緑豆こそ、伝統的な食養生において「熱を冷まし、暑さをしのぐ」代表的な食材のはずです。
実は、日本の伝統的な茶菓子にも、日本人なりの自然との向き合い方が込められており、古くからの「五行バランス養生術」がさりげなく日常生活に溶け込んでいます。それはまさに、暑さをやわらげて心身を整える「火消し術」の中で、最も理にかなっていて、体にも優しく、生活に取り入れやすく、誰にでも実践しやすい五行の知恵なのです。
木が盛んで風の多い東の島国、日本――肝を整えて「火」を鎮め、心と脾胃を傷つけない知恵
日本は五行で「木」に属する東方の地です。木は肝を司り、春、そして風をも意味します。そのため、春の風が吹き始める頃から夏にかけて湿気が増すにつれ、日本人は年中、風が強く湿度の高い環境の中で暮らしています。このような環境では肝の気が乱れやすく、熱を生じて「火」に転じやすくなります。同時に湿気は脾胃を弱らせる原因にもなります。そのため、人はイライラしたり、めまいや口の渇き、胸のつかえ、情緒の不安定といった症状が出やすくなりがちです。特に体質が虚弱な高齢者や子ども、夜更かしが多かったり、精神的に緊張が続いている人は、風が強い日などにまさに「風に連れ去られる」ような影響を受けやすいのです。風に筋が反応し、関節や筋肉に震えや痛みを感じることもあります。
さらに「立夏」を過ぎると、五行では「火」に属する季節がやってきます。火は心を司り、夏の火は特に心の陰(潤い)を損ない、心の気を消耗させやすいため、気持ちが落ち着かずイライラしやすくなり、不眠や物忘れ、さらには口内炎や動悸といった症状が現れることもあります。中医学では「夏は心を養う」と言われますが、それはつまり、夏の「火」が盛んな時期には、何よりも心を清らかに、穏やかに保つことが大切だということです。
このようなとき、自然界の「木が火を生む」という五行の原理に従えば、燃え盛る心火を鎮め、血と気にこもった熱を逃がすには、源である「肝木の火」をそっと取り除く、つまり「釜の底から火を抜く」ような方法が効果的です。しかし、注意すべきはやりすぎないこと。心や血を傷つけたり、冷えすぎて脾胃を損なうようなやり方では逆効果です。静かに、やさしく火を鎮める――これが夏の養生の要です。
抹茶とヨモギの組み合わせ、冷たすぎず優しい「東洋の薬茶」
中国では、熱を冷まし毒を排出する食材として緑豆がよく用いられますが、緑豆は性質が寒涼で、身体を冷やしやすく、水分代謝を促す作用が強いため、非常に暑く湿気の多い中国南部や、火が強すぎる体質の人に適しています。しかし、日本のように五行で「木」が盛んで涼しい気候の国では、風湿の影響を受けやすく、肝木が脾土を抑える傾向もあり、脾胃が弱りがちです。そうした環境では、緑豆のように冷えが強い食材はかえって脾胃や気血を傷つけてしまう可能性があります。実際に、緑豆を食べた後すぐに胃が冷えたり、膨満感や腹痛、下痢が起きて、食欲がさらに低下する人もいます。
その点、日本人はより穏やかな方法――抹茶や非焙煎の緑茶を選びました。
抹茶は蒸してから乾燥させた茶葉を細かく挽いたもので、茶の芳香とほんのりとした苦味・甘味を持ちながら、焙煎による熱性はありません。清らかで柔らかい性質をもち、「涼」であっても「寒」にはなりません。五行では緑色は木に属し、肝に作用しやすいため、抹茶は肝の気を穏やかに巡らせ、火を和らげる効果がありつつも、脾胃を傷つけることはありません。
さらに注目すべきは、抹茶の持つ苦味です。中医学における五味では「苦」は「心」に属し、心火を鎮め、熱を冷まし、煩わしさを和らげ、利尿作用を促し、心を落ち着かせる働きがあります。適度な苦味は、上に昇った火を下へと導き、心身を静める効果があるのです。つまり抹茶は、喉の渇きを癒す飲み物であると同時に、心を癒す植物性のお茶療法でもあるのです。

お茶はもともと草木からできており、五行では「木」に属します。肝の経絡に作用し、肝の気を調え、熱を解毒する働きを持っています。特に若葉を使うことが多く、青々とした色と香りが上に昇る性質を持ち、五行の「木」の象徴そのものです。風と木の力が強い東洋の土地において、お茶は単なる飲料ではなく、肝火をなだめ、感情を整え、ストレスをやわらげる日常的な食療の良薬なのです。
ただし、五行では「肝は木、脾は土」とされ、木は土を抑制します。そのため、肝火を過剰に冷まし、風木の勢いを抑えすぎると、かえって脾胃を損ねてしまう恐れもあります。特に体が冷えやすい人や、陽気が不足しがちな人が、夏に寒涼なものを取りすぎると、胃の冷えや腹痛、下痢などを引き起こしやすくなります。
そこで日本人は、和菓子などにヨモギやヨモギ団子、温性のあるもち米などを巧みに組み合わせます。ヨモギには体を温めて寒さを散らす作用があり、もち米は胃腸を補い、気を養います。こうして、肝火を和らげながらも、脾土の陽気を守り、「木が土を傷つける」ことを防いでいるのです。

これこそが、伝統の中に息づく五行の調和の知恵――肝を清めつつ脾を傷つけず、体を温めながらも熱しすぎず、「寒」と「熱」の間で土と木のバランスを取る、見事な工夫なのです。
赤い小豆、心と血を養う「やさしい名脇役」
この小さな赤い豆を、あなどってはいけません。
小豆は「性質が平(へい)=温でも冷でもない」ため、体にやさしく働きます。利尿作用に優れ、心火を鎮める一方で、心を養い血を補い、湿気を取り除きながら脾を健やかに整える力を持っています。緑豆のように一気に冷やして排出するような強い作用はなく、まるで調和の取れた支援者のように、余分な湿を静かに取り去り、脾胃を強化し、心や肝が消耗した気血をそっと補ってくれます。
夏は陽気が体の表面に浮きやすく、心の気が消耗されやすいため、多くの人が疲れを感じたり、集中力が続かなくなったり、動悸や不眠に悩まされたりします。そんなとき、小豆は心血を養い、心の気を補ってくれる、まさに「火が盛んな夏」にぴったりの、滋養と穏やかさを兼ね備えた存在なのです。
特に、もち米、葛粉、寒天、米粉など、脾を助け気を補う食材と一緒に用いてお菓子に仕立てれば、そのやさしさと力強さはさらに際立ちます。こうした素材は胃に負担をかけるどころか、気を補い、血を養い、体にエネルギーを与えてくれます。暑さに負けない体をつくるにはうってつけの組み合わせです。抹茶が熱を鎮め、小豆が血を補い心火を清め、米の食品が脾を守り、気を補う――そんな役割分担の中で、これらの食材は温かくも力強い支え合いを形成し、まさに「食で気を調える」理想的な養生法といえるでしょう。体を冷やしすぎず、内側から整える、夏にぴったりの完璧な健康術です。
だからこそ、小豆と抹茶は日本で何百年にもわたり、貴族から庶民に至るまで親しまれ、和菓子にも、お弁当にも欠かせない存在であり続けているのです。

茶菓子で心と体を整える、大自然の五行に寄り添う知恵
風の強い季節、人はどうしてもイライラしやすく、頭がぼんやりしたり、食欲が落ちたりします。これは、肝の気が外界の風の気に呼応し、風に揺さぶられて心肺や頭に影響を及ぼし、さらに脾胃まで弱らせてしまう結果です。そして夏の火が盛んな時期になると、心火がより活発になり、心身がかき乱されやすくなり、眠れなかったり気分が不安定になったりします。
日本人はこうした理由をあえて口にしませんが、そのかわりに、そっと差し出すのは小豆の入った一つの和菓子、そして抹茶や、香り高くも刺激のない一杯の緑茶です。
これらの伝統的な食べ物は、自然界の五行の法則をすでにその中に溶け込ませており、日々の食事を通じて心身を自然に調和させてくれます。
それは単なる味覚の選択ではなく、大いなる自然の流れに身をゆだね、身体を静かに整えるための知恵でもあります。それは理屈ではなく、世代を超えて身体で覚え、受け継がれてきた、生きた答えなのです。
結びに、天と人が調和する養生の知恵
抹茶は、そよ風のように肝を潤し、火を鎮めて心を落ち着かせる緑の力。
小豆は、血を養い心を癒し、湿を取り脾を整える、五臓を調和させる赤いエネルギー。
もち米とヨモギは、脾胃を温め、体の中心を安定させる温かな陽の力。
一見、自然体で何気なく食されている日本の伝統的な和菓子には、東洋の草木の性質や、五行の「生」と「克」の原理が日常の中で息づいています。そこには、天地の理に寄り添いながら心身を養う、調和の道があります。これらは、風・火・寒・湿が入り混じる季節の中で、心の平穏と体のバランスをどう守るかを、私たちに静かに教えてくれます。
どうか、私たちも一杯の抹茶と一口の和菓子の中に、自然に従い時を尊ぶという古人の知恵――「天人合一」の精神を感じ取り、あのほろ苦くも優しい茶の香りの中で、自然を敬い、伝統を大切にする道へと、もう一度心を向けてみましょう。
(翻訳編集 華山律)













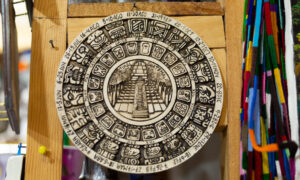










 ご友人は無料で閲覧できます
ご友人は無料で閲覧できます Line
Line Telegram
Telegram




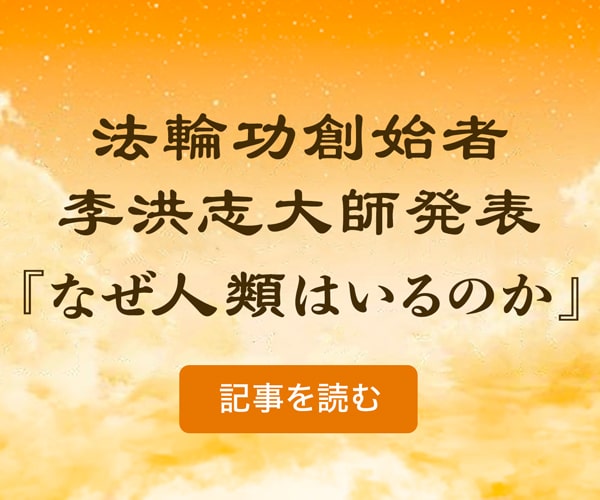
ご利用上の不明点は ヘルプセンター にお問い合わせください。