目次
1. 神に叛(そむ)き、祖先を罵倒
1)神に叛く
2)祖先を罵倒、伝統文化を誹謗中傷
3) 洗脳された人が伝統文化を攻撃
2. 強力な洗脳、善悪反転
1) 「天命」の代わりに「革命」を
2) 党が道徳を定め、悪を「善」に
3) 思想改造運動、血のない殺人
4) 誰も免れない災禍
******
前書き
文化大革命後、中国共産党は存続の危機を乗り切るために、「改革開放」の政策を打ち出した。「階級闘争が基本路線」から「経済建設を中心」へ、「食べ物も惜しんで革命に励む」から「金銭至上」へ、まさに180度の方針転換を行った。表面から見ると中国共産党は生まれ変わったかのように見えた。同時に国際共産主義陣営の解体に多くの人々は安堵し、共産主義の脅威が消えたと思い込んだ。本当にそうだろうか?
中国社会では、資本主義か社会主義かの定義が人々にとって重要だが、共産邪霊にとってはさほど意味のないことである。本書は繰り返し強調してきたとおり、共産主義は一種の学術でも社会制度でも失敗した模索でもなく、悪魔なのである。その目的は文化を破壊し、道徳をも破壊することによって人類を破滅の道へ追い込むところにある。「共産主義の最終目的は人類を破滅させるためだ」という筋書きに従って分析すれば、複雑な表面現象に惑わされず、邪霊が人類を破滅させるフローチャート(流れ図・機能、作業や操作手順)やマニュアルが浮き彫りになる。
殺戮を大衆の目に触れないところで行うようになっても、人類を破滅させる計画は進んでいる。共産党は人々を生かすことも殺すことも、空腹にさせることも満腹にさせることも可能である。今日は禁欲を励行し、明日は享楽がオススメだといった具合である。今まで惜しみなく文化を破壊していたが、時が来れば素早く伝統を「重んじる」姿勢に転じる。これまで社会主義至上だったが、一夜にして徹底的な資本主義に衣替えした。しかし、中国共産党がいくら看板を塗り替えても、「伝統文化や道徳の破壊によって、人間を神に背き人間性のかけらもない生命にする」という本質は変わっていない。共産邪霊は「憎悪」によって構成されており、邪霊に騙された人々は神、伝統、文化を唾棄し、祖先を憎むように仕向けられた。
共産党にとって「殺し」の手段以外に「騙し」も重要な手段である。「殺し」と「騙し」は共産主義の根幹をなす「神や仏を敵視する無神論と闘争の哲学」から生まれたのである。「殺し」と「騙し」は相互補完的な関係にあり、「殺し」に「騙し」があり、「騙し」に「殺し」がある。
共産党の「騙し」は社会生活のあらゆるところに影響を及ぼしている。いたるところに「騙し」がある。金、女を騙し取るほか、偽物のタバコやお酒、毒米や毒粉ミルクで人々を騙している。これは道徳が共産党によって破壊されたことの必然的な結果である。なぜ共産党は人を騙せるのだろうか?人々はただ就職、昇進、金持ちになるため、愛人を作るために騙されたのだろうか?そのような人は当然いるが、特に金銭至上の現代社会ではこのような人は少なくない。しかし、共産党の結成時、一部の裕福な家庭の子弟たちが名誉や財産をなげうって、革命に身を投じた。この違いはどこから生じたのであろうか?
人はみな神に通じる一面がある。仏教の彼岸、道教の帰真への憧れは、神が人間を造ったときに与えてくれたものであり、生まれつきの本性である。共産党はこの願望を利用して人々を騙し、国家の運命や民族の将来という言葉で人々を惑わせ、さらに全人類を圧迫から解放する、人類共同体を形成するなどの聞こえの良い抱負で歴代の党の指導者を騙した。唯一の邪悪生命である江沢民を除けば、あらゆる党首も人間であり、共産悪霊の本質を見抜くことができないからである。彼らは共産主義の実行者であり、被害者でもある。彼らの抱負、人民のために尽くすという純粋な気持ちまで邪霊にもて遊ばれた。心の奥にある神への憧れはこのように邪霊によって壊された。鉄道の分岐レールのように、神の境地へ通じる道は共産党の「人間天国」という地獄への道に切り替えられてしまった。共産党の旗の下で行われる宣誓式は、悪霊が操っている。「生涯を共産主義のために捧げる」と誓った人は以後、悪霊にコントロールされ、その最終目的へ突き進む一方である。
人間は邪霊の邪悪性を認識できる時もある。共産党は嘘を見破られないように、強硬な手段でこのすべてを維持しなければならない。また、嘘の上塗りで人々を騙す必要がある。従って、「殺しつづける」ことや「騙しつづける」ことは必然的手段となった。
人類を消滅させるため、共産党は社会の秩序を乱し、人の心を惑わしてきた。その際、「闘争」という手段を手放すことはなかった。地主を消滅するための暴動に無一文のごろつきを駆り立てたのも、「紅五類」(出身階級の良い者)と「黒五類」(出身階級の悪い者)との闘争を煽ったのも、いずれのキーワードも「闘争」であった。闘争を引き起こすために国民を「人民と敵」、「仲間と敵」に分ける必要があった。中国共産党は一党専制を盾に、悪人を持ち上げ、良い人を批判する闘争を続けた結果、中国は悪人の天下となり、良い人が理不尽な扱いを受けている。
共産悪霊が人類を消滅させるために人の心を邪悪へと変貌させた。
共産党は人間を共産悪霊に必要な人に作り変えた。善悪の基準を乱し、是と非を反転させることによって、古来の伝統に背き、道徳が低下すればするほど、悪霊の思う壺にはまり、そして人々は破滅へと突き進んでいく。
中国社会で共産主義の「理想」が幻滅した後、共産党は金儲けと享楽を追求するよう人々をそそのかした。悪霊は人々の欲望を果てしなく広げた。堕落は権力を手にするための手段となり、人を破滅させる有効な武器となった。今の中国社会に見られた道徳の低下は悪霊が数十年来、破壊し続けた結果である。「天国への道を塞いだが、地獄への扉は開いた」、このように中国社会は共産党によって崩壊の崖っぷちに立たされた。
1、神に叛き、祖先を罵倒
共産主義は悪魔を神に美化し、神を想像上のものに過ぎないと宣伝した。なぜなら、神を信じる人に悪魔が付け入る隙はないからである。
1)神に叛く
本書の第二章ですでにマルクスの邪教への信仰、悪魔に傾倒する過程を詳述した。レーニンも邪教の信者であり、神に叛き、破滅を憧れていた。16歳のとき、首にかけていた十字架を地面に叩き付けたうえ、つばを吐き、足で踏み壊した。彼は「あらゆる宗教理念、あらゆる神への信仰、…あらゆる神にかかわる考えが嫌いで、おぞましい」と言っていた。
スターリンが国家機器を動員し、政権を利用して無神論を広め、暴力でほかの宗教信仰を弾圧し、そして国家無神論政策を行い、つまり、国家として無神論を標榜しているため、国内での宗教及び有神論は認められていない。国民個人の宗教的活動が存在する場合、政府による弾圧の対象にもなりうる。スターリンは「宗教上の偏見を利用して国家の安定を破壊する人に対して少なくとも三年から死刑の刑罰を与えるべき」と述べた。ソ連共産党の重要人物であるブハーリンですらスターリンを「人間でなく、悪魔だ」と表現した。
社会主義・共産主義を代表する曲「インターナショナル」の歌詞に「救世主なんていない、神や皇帝は頼りにならない」という内容がある。これらの歌詞がまるで神に叛く宣誓書のように共産党の会議で繰り返し流されていた。
2)祖先を罵倒、伝統文化を誹謗中傷
『詩経・大雅・文王』にこう書かれている、「无念尔祖,聿脩厥德。永言配命,自求多福」(訳:汝の祖先を尊ぶべし、その徳を継ぎ修め帰す。とこしえに、天命に従い、自らの手で福を呼び寄せる)
祖先は生命の源であり、祖先を敬う念は人間としての基本である。中国の伝統文化では「祖先への尊重」と「孝道」は極めて重要である。そこには深い意味と理由がある。中国は中心の国として神の加護を受けてきた。中国の伝統文化は神と切り離すことができない。神と人間が共存していた上古時代から、中華民族の祖先は神の恩恵を目の当たりにし、神に敬意を抱き、そして与えられた使命を背負ってきた。彼らは神からの言い伝えや恩恵を失わないように代々守り続けてきた。
世界各国の人々も偉大な祖先や皇帝を敬ってきた。ローマ帝国のシーザー皇帝、フランスの太陽王ルイ十四世、プロイセンのフリードリヒ二世など偉大な君主が後代の人々に敬われてきた。米国のサウスダコタ州のラシュモア山には4人の偉大な大統領の肖像が建っており、訪ねてくる多くの人々が敬意を払っている。
常識的に考えれば他人の祖先を中傷することは相手を侮辱することであり、「祖先を認めない」のは人間としてあるまじき行為とされてきた。共産党は人間と神や祖先との関係を切り離すために、中華民族の祖先を貶し、中国の伝統文化を否定してきた。中国共産党とその御用学者は中国歴代の帝王、賢人を「誰一人良い人はいない」と完全否定している。自国民の祖先を完全否定する行為は歴史上にはなかった。中国人も邪悪な共産党に惑わされ、神に叛き、祖先を否定し、文化を破壊し、危険極まりない道を突き進んでいる。
共産党が政権を盗み取るまで、一部の虚無主義の立場に立つ文化人を利用して、中国文化を中傷していた。彼らは共産党員とは限らないが、共産党が成し遂げられなかった効果を挙げた。このような共産党外部からの批判がさらに人々を惑わした。典型的な例は魯迅(ろじん)である。毛沢東がかつてこのように魯迅を評価していた。「彼は文化新軍の最も偉大かつ勇敢な旗手である。魯迅は中国文化革命の主将である」「魯迅の突き進む方向こそ中華民族新文化の方向だ」
中国共産党が魯迅を賞賛し、魯迅の文章は中学校の教科書の定番になっている。その「伝統文化への批判」がもたらした影響の深さと広さは共産党員にも成し得ないものであり、中国の伝統文化に大きなダメージを与えた。魯迅が放った無責任で悪意に満ちた言論は今でも中国の知識人に悪影響を与え続けている。
波乱万丈な人生をたどった魯迅は、人一倍強い怨念を持っている。「強い悪意で中国人分析を行う人」と自称していた。共産党はこの「文化のならず者」の恨みの矛先を中華伝統文化に向けさせた。
魯迅は伝統文化や中国の歴史全体に対して、否定的な態度に終始していた。処女作の小説である『狂人日記』で主人公は、「中国の歴史は『人喰い』という言葉に尽きる」と述べ、魯迅の考えそのものを反映している。
3)洗脳された人が伝統文化を攻撃
中国共産党が政権を手にしてから、政治運動や古い思想、文化、風俗、習慣を打ち破る「破四旧」(歴史遺産を破壊する運動)に明け暮れていた。人類文明の輝かしい成果は「封建主義、資本主義、修正主義」などのレッテルを貼られ、その存在価値が否定された。五千年にも及ぶ中国歴史上の賢人や英雄が階級闘争の理論から「プロレタリア独裁と社会主義に反対する「毒草」」と攻撃されていた。伝統文化に対する蹂躙(じゅうりん)は文化大革命で最高潮に達した。
社会のエリート層を虐殺したことで文化の断層を作り出した。その後、数世代の人々が中国共産党の無神論や党文化の洗脳で、伝統文化についてほとんど何も知らない。1980年代以降、中国共産党は従来の手法を変えた。これまでの暴力破壊を封印し、人に気付かれにくい批判を展開するようになった。共産党の本質はますます隠され、人々は警戒を緩めてしまった。中国共産党とその御用文人が古人を見下し、けなし、矮小化することで自分自身の「偉大さと正しさ」を際立たせた。現代社会の良くない現象が「伝統文化の悪い影響」と身勝手に解釈している。中国共産党の「解読」によって、『三国演義』は「愚かな忠誠心」を宣伝しており、『西遊記』は「封建迷信」であり、『水滸伝』や『紅楼夢』は「階級闘争」を描写しているという。古典文学にある倫理道徳や修練文化、天命や輪廻については一言も言及しようとしない。中国共産党は意図的に人々の注意力を古代文化の「影の部分」に集中させた。伝統文化は宦官(かんがん)、纏足(てんそく)の女性、一夫多妻や宮廷抗争などの同類語となった。
洗脳された文化人が憚らず皇帝や祖先を貶し、「専制主義」や「封建社会」の言い方で伝統文化を唾棄した。彼らは伝統文化に対する敵意から、歴史の主流でない暗君、反乱などを取り立てて宣伝し、共産党の歴史観を支えていている。
人間性には善悪が同時に存在しており、古代文化でも悪の部分はあるが、それは中国文化の主流でもなければ、普遍的な現象でもない。しかし、中国共産党は古代社会の枝葉末節を伝統文化の主体として捉え、攻撃していた。
二十世紀、中国人の民族性の悪根性について論じるブームが起きた。そのなかで、ある有名な作家は中国人の「悪根性」が中国伝統文化に由来するとした。この認識がまさに邪霊の罠にはまった。なぜなら、中国共産党こそが中国人の欠点を増強させた張本人だからである。中国人は先天的に「悪根性」があるわけではない。むしろその反対に、歴史上、神の民として輝かしい文明を築き上げた。中国は世界でも尊敬される礼義の国であった。現代の中国人の常軌を逸する行動は神から伝えられた文化に背を向けた結果である。中国共産党が執政後、意図的に人間の欠点を強化し、魔性を増長させていた。その結果、中国人の道徳観は一瀉千里の勢いで失われた。
共産党が中国文化に未曾有の災難をもたらした。中華民族の復興と社会の再建を願えば、伝統への回帰に取り組むべきである。中国共産党は伝統文化に対して数十年にわたって罵詈雑言を浴びせた。何世代もの中国人が伝統文化に無知であり、敵意を持っている。
2.強力な洗脳 善悪反転
共産党は洗脳を「思想改造」と称している。このような思想改造が強制的な手段によって実施され、誰も逃れることができない。また、さまざまな残忍な手段で人々を精神的に苦しめ、人々を共産党の統治に従わせた。中国共産党政権にとってあらゆる洗脳は、人々に無神論や闘争哲学を中心とした共産主義価値観やイデオロギー、いわゆる「プロレタリアート世界観」に同調させるための手段だ。その本質は邪霊が各々の個人に精神的なダメージを与え、中国人古来の伝統価値理念を系統的に破壊することである。
1)「天命」の代わりに「革命」を
中国人は古くから「天命」で政権の合法性を判断している。もし皇帝が徳を失い、天道や祖先に叛(そむ)き、徳に基づき国を治めることができず、国民に信頼されなくなれば、天命が変わってしまい皇帝も更迭される。「天命」の考えから見れば、共産党は文字通りに天命と逆行している。天道や祖先に従わず、徳に基づき国を運営する姿勢がなく、政権すら合法ではない。政権を奪取した共産党政権は、その合法性を訴えるために、人々の心から伝統思想を除き、代わりに無神論や闘争の哲学を植えつけた。さらに、社会発展に関するマルクスの論理(生産力が増大するにつれて、社会は原始共産制から、奴隷制、封建制、資本主義、社会主義、共産主義へと変化していく、という内容)を真理とみなし、中国の歴史を無理やりその理論に当てはめようとしている。階級闘争を通じて中国を「共産主義」に導くことは歴史発展の必然的な結果であると公言しており、このように共産党政権の正当性を訴えている。それと同時に共産主義の実現は「神聖」な使命であり、共産党の存在を歴史発展の「必然の選択」と自らを美化している。その本当の目的は「天命」の考えを取り替えるためである。
2)党が道徳を定め、悪を「善」に
道徳は神が人間に与えたのである。神が不変であり、道徳の基準も永遠に変わらない。その基準はいつの時代になっても人間が決めるものでもなければ、統治者の権力によって変わるものでもない。中国共産党は今の中国社会の道徳を定義したが、すなわち神の主導権を奪い取った。共産党は自分の行ったありとあらゆることを「道徳的」で、自身が「永遠に正しい」と吹聴している。さらに、道徳の基準を必要に応じてその都度、変更してきた。
伝統的な考えを持つ中国人なら、明確な宗教信仰がなくても、天理や良心といった普遍的な価値観を持ち合わせている。中国共産党はまずその天理や良心を滅ぼすことから始めた。なぜなら、「無産階級の世界観」は普遍的な価値観を認めず、階級を超越する道徳を認めていないからである。共産党から見れば、道徳は人の階級や立場で決まる。人々に称えられる清廉潔白の幹部は、共産党の世界観で量れば、評価が真逆になる。「敵対階級」の官僚なら、廉潔であればあるほど「敵対勢力の統治」に加担し、「労働者の闘志」をなくしてしまうため、「悪」のレッテルを貼られてしまう。また、中国人は「人命はなによりも大事だ」と信じており、命の危険にさらされた人を助けることは素晴らしい行為と認識されている。しかし、共産党の辞書では「人道主義」の前に「革命的」という修飾をつけなければならない。「同志」に対して守る必要はあるが、「敵対階級」に対して残忍であればあるほど、自分の立場をはっきり示した素晴らしい行動と見なされている。
そうすると、どんな邪悪で常識から逸した行為でも「革命的」、「進歩的」または「社会主義」の修飾語を付けられれば、歴史の発展に「合致」する行動になり、絶対的に正しいとされる。一方、どんな高尚な行為、思想でも「封建的」、「資産階級」や「無産階級への攻撃」のレッテルを貼られると、絶対に間違っており「反動派」とみなされる。共産党はこのように善悪の基準を狂わせた。時期によっては使うレッテルはまた異なる。「党のリーダーを攻撃」、「国家政権を転覆」、「迷信を宣伝」、「反科学的」、「国家転覆」などなど。要するに「党」自体が「神聖」な事業をやり遂げるために、時代に選ばれたのであり、党に対するあらゆる挑戦は決して容認されない。この判断基準こそ「無産階級の世界観」の核心である。
この世界観はもちろん中国人に受け入れられない。レーニンもたとえ無産階級でも自発的にマルクス主義的な世界観を持つことはないと認識していた。したがって、無産階級はもちろんのこと、資産階級や地主に対しても思想の改造を行なわなければならない。
中国共産党はさまざまな政治運動を行ってきた。その目的は威信の樹立、信仰や文化の破壊、権力闘争、対立勢力の粉砕と時期によってはそれぞれ異なるが、いずれも「革命」の名のもとで行われ、「無産階級の世界観」を用いて相手を攻撃したり、丸め込めたりしてきた。
中国共産党は政治運動を通じて、人々の命を奪っただけではなく、人々の心にある伝統的価値観を強制的に放棄させた。その後、共産主義の枠組みで反道徳的価値観を作り上げた。残酷な現実を目の当たりにした中国人は伝統的な価値観では生きていけないと分かり、伝統の考えを放棄せざるを得なくなった。直接、攻撃を受けていない人でも、伝統的な価値観を少しでも表出させないように注意を払っている。道徳は行動様式を規定するためのもので、神が人間に与えた基準である。自らの手で埋葬された価値観は完全に消えていなくても、すでに機能しなくなった。これで人類を壊滅させるという邪霊の目的は達成した。
3)思想改造運動、血のない殺人
1950年代、中国共産党は立て続けにいくつかの「思想改造」運動を行った。たとえば、『武訓伝』、梁漱溟、兪平伯、胡適を批判する運動や「反胡風」、「反右」などを行った。その後の文化大革命も大規模な思想改造である。
思想改造には常に虐殺が伴う。50年代、思想改造と同時に「土改(土地改革)」「三反」「五反」「鎮反」など、惨殺が伴う運動が全国を席巻した。真剣さが足りない人、または改造に消極的な人には、想像を絶する結末が待っている。
中国共産党の思想改造は暴力と強制を武器とする。暴力は人々に心理的な恐怖をもたらし、強制は「改造」から逃れられないようにするための手段である。度重なる運動のなか、最初は思想改造に対抗していた人でも、最終的に順応し、そして魂が滅びていく。その過程を見ると、ひとつだけ確信できることがある。つまり直接、暴力を受けていない人でも、この過酷な過程で精神的に大きな傷を負うことになる。
中国共産党の洗脳目的の「革命大学」を経験した人が次のコメントを残した。「中国共産党の思想改造は暴力的な闘争を意味し、そして人間の精神に化学的変化が起こる」「クラスメートの一人がこの自己反省を強いられる改造によって、心に無数の傷を負ったと話した」
作家の沈従文は当時の状況について、「すべての学生がプレッシャーによって不眠症になり、多くは激しく泣いた」と書き留めていた。
4)誰も免れない災禍
文化大革命中、百万を超える人が惨殺されたとされる。その間、精神的に虐殺された人はもっと多く存在した。スターリンの虐殺よりもはるかに凄惨だった。
「全員参加」は文化大革命の特徴である。誰もが攻撃する側、または攻撃される側にいた。
スターリンは国民を殺したり、グラグ強制労働収容所に送り虐待死させたりしていたが、精神的な虐待にそれほど興味はなかった。一方、文化大革命の殺人手段はスターリンの手段よりも残酷で、被害者の規模は大きかった。毎回の政治運動では一部の人だけが締め付けられていたが、その影響は全国民に波及した。闘争に参加し、人を痛めつけたのは秘密警察でも殺人鬼でもなく、被害者の同僚、クラスメート、部下、教え子、友達、隣人だった。なぜなら、参加しなければ「階級の敵に同情している」と判断され、「立場がはっきりしない」のレッテルを貼られ、すぐに攻撃の標的にされるからである。リンチが社会と隔離されている強制労働収容所で行われていたのではない。校舎、教室、工場、街角、「牛棚」と呼ばれる自発的に設置された小屋など日常生活の空間で繰り広げられていた。同僚、クラスメート、先生と教え子、親友の間はもちろん、兄弟姉妹、夫婦、親子の間でもお互いに摘発し合うことが常態化した。誰もが積極的にそれを行い、そうでなければ立場不明瞭の疑いをもたれる。親しい人に対して暴力を振るうほど「立場が強固なもの」と見なされる。
1966年12月に毛沢東の秘書である胡喬木に対する批判大会は北京鋼鉄学院で行われた。当日、彼の娘が登壇して「胡喬木という犬の頭をぶっ潰せ!」と叫んでいた。最終的に彼女は父親の「犬頭」をつぶすことはなかったが、本当に父親の頭をつぶした中学生がいた。それは北京市内に住む「資産家」に起きた話だった。「紅衛兵」が資産家の老夫婦を半殺しにして、さらにその息子に両親を殴るよう強要した。結局その中学生の息子は鉄アレイで父親を殺してしまい、自身も精神異常に来した(『我が家:私の兄遇羅克』)。この全員参加型の批判闘争運動が、家族倫理を基礎とする伝統的な価値観を中国人の心から排除し、代々継がれた価値観は完全に崩壊した。
このような摘発が社会で日常的に行われ、人々は過激な方法で中国共産党に忠誠心を表すようになった。倫理や道徳に叛き中国共産党と一致すればするほど、「道徳的」とみなされ、社会の主流と認められる。このように、共産党は伝統文化の価値を人々から遠ざけたのみならず、社会に「党文化」を充満させた。


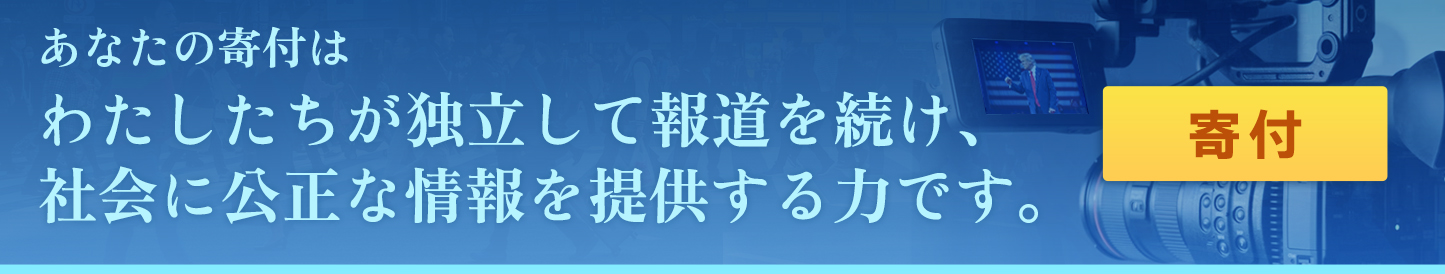







 ご友人は無料で閲覧できます
ご友人は無料で閲覧できます Line
Line Telegram
Telegram


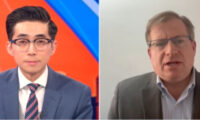







ご利用上の不明点は ヘルプセンター にお問い合わせください。