米通商代表部(USTR)のキャサリン・タイ代表は8日、上院財政委員会の公聴会で、日本との通商交渉について「農産物の市場アクセス拡大に取り組んでいる」と述べた。米側が国産農産物の輸入拡大を迫る公算が大きく、農産品分野が交渉の山場となりそうだ。
アメリカは、牛肉や乳製品の関税引き下げを強く求めており、日本との駆け引きが激しさを増している。背景には、2017年にアメリカが環太平洋経済連携協定(TPP)から離脱したことで、日本市場における農産物の競争力が相対的に低下した事情がある。
TPP11(CPTPP・TPPを基に、アメリカが離脱した後に締結された自由貿易協定)の枠組みによって、オーストラリアやニュージーランドなど加盟国の農産物は関税優遇を受ける一方、米国産のシェアは後退。2019年の日米貿易協定によって一部改善が図られたものの、米国はさらなる市場開放を求めて交渉を加速させている。
交渉の焦点は明確だ。牛肉については、2023年時点で約25.8%となっている関税を、TPP加盟国並みの水準である9%まで段階的に引き下げることが米国側の要求の核心である。さらに、チーズや脱脂粉乳といった乳製品に対する関税割当枠の拡大も議題に上っており、ウィスコンシン州など中西部の酪農地域からの政治的圧力が強まっている。
また、TPP離脱により設定されなかったアメリカ向けコメ輸入枠(年間7万トン相当)の新設や拡張も、米側の関心事項とみられる。
一方、日本政府は、CPTPPや日EU経済連携協定(EPA)で定めた関税削減水準を「譲歩の上限」とする方針を堅持しており、コメ、小麦、乳製品、牛肉・豚肉、砂糖の「重要5品目」については関税撤廃に強く反対している。
問題は関税にとどまらず、非関税措置にも及ぶ。米国は、日本の遺伝子組み換え食品(GMO)に対する表示義務や、農産物検疫における煩雑な手続きを「科学的根拠に乏しく、輸出を妨げる障壁」だと批判。検査プロセスの透明化やデジタル化を求めている。これに対し、日本側は「消費者の安全と安心」を理由に規制維持を正当化している。
加えて、アメリカ側は、日本の消費税制度における「輸出還付」についても注視している。日本では、フランス型の付加価値税(VAT)をベースに、輸出品にかかった消費税が還付される仕組みとなっており、これが「事実上の輸出補助金ではないか」との批判が一部から上がっている。とりわけ、国内農産品と競合する輸入品に対し、日本政府が間接的に有利な制度設計を行っているとの見方が根強い。
この通商交渉には地政学的な要素も絡んでいる。アメリカは日本に対し、液化天然ガス(LNG)の長期購入契約の拡大を提案しており、農産物市場の開放とエネルギー安全保障を連動させる戦略を進めている。
政治日程の影響も無視できない。2026年秋の米中間選挙を控え、トランプ政権は中西部農家の支持確保を急いでいる。一方、日本では2025年夏に参議院選挙を控えており、農業票を意識した慎重な対応が求められている。
日本の農業は現在、構造的な課題に直面している。日本の労働生産性の水準は米国の約3分の2で、農地の集約化やスマート農業の導入は遅れており、国際競争力の低下が深刻化している。
今後の展開としては、短期的には牛肉関税のさらなる引き下げを日本が受け入れる代わりに、アメリカが日本車への追加関税措置を回避する「パッケージ妥結」が模索される可能性がある。一方、中長期的には、和牛や日本酒といった高付加価値の国産品輸出を拡大し、「守る農業」から「稼ぐ農業」への転換が日本側の鍵となる。
日米通商交渉は、農業、エネルギー、補助金制度、政治が複雑に絡み合う局面に突入しており、今後数か月の動向が両国経済に大きな影響を与えることになりそうだ。













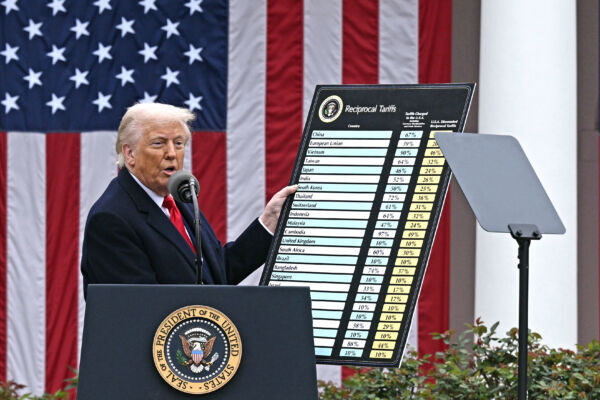


 ご友人は無料で閲覧できます
ご友人は無料で閲覧できます Line
Line Telegram
Telegram














ご利用上の不明点は ヘルプセンター にお問い合わせください。