第三話
再び、今の邦男は家を飛び出し、スミの駄菓子屋を目指していた。窮地に陥ると、笑ってごまかすのは十の時から世間の荒波を渡ってきた習いだ。木立の影が被さる駄菓子屋の入り口をニカニカしながら入るや否や、邦男はサラッとたずねた。
「スミちゃん、そろそろ良いだろうか?」
ふだんと変わらず邦男を迎えたスミは、様子のちがいに慌てることもなく冷静である。
「なにがですか? 邦男さん」
と、すこしかすれた声で聞き返す。
「俺さ、家出してきたんだ」 スミは表情を変えず、姿勢も崩さない。
「それで?」と、自然体で聞き返した。
「だからさ、ここに住もうと思うんだが……」
邦男のすこし力の入った言葉にも、ボケたかのように動じない。驚きもせず、拒絶するでもなく、
「咲ちゃんは、どうするんです?」
前のめりかかった邦男にスッと顔をあげ、目じりをわずかに細めながら彼になつく孫の事を心配する。
「咲はもう五才だし、毎日遊びに来るさ」
スミの顔に光がさすが、
「ずいぶん、勝手じゃありませんか?」
今度は本音を少し混ぜてにらみつける。だが子供のいたずらをさとすような柔らかさだ。
「そ、そうかな」
邦男は愛想笑いを振りまくしかない。
「笑われますよ、世間様に」
スミのその言葉を待っていたのか、
「もう、笑われてるさ」
邦男はさもそれが当然なように、スミの隣に腰を下ろす。
「私はいやですよ。笑われるのは」
言葉とは別にスミはもう、微笑んでいた。
その表情を見た途端、邦男は自分が急に大きくなったような気がした。皺が寄り、体は小さく丸まってしまったが、十四の頃の黒々とした髪が風になびき、冷たい空気に冴え冴えとさらされた富士額の初々しい姿に飲み込まれたのだ。
神社の木陰の中で、湖畔のような瞳がじっと若き邦男を見つめていた。その眼差しに耐えきれず、自然と、嫁に来てくれと子供のようにねだった。スミがゆっくりうなずいてくれた時の興奮さえ、よみがえった。
「なんですか? よだれがたれそうな顔?」
「いや、昔のスミちゃんを思い出しての」
スミも微笑みながら朱に染まった真向いのチャペルに視線を注ぐ。
「しかしなんだな。ここは静かでいいなぁ。ここにいれば世間様の笑いも届かないだろ?」
スミは黙っている。怒ってもいないし、考えているふうでもなく、ボケているはずもないから、とぼけているに違いなかった。
その夜、スミは襖で隔たれた仏間四畳半に自分の布団をしき、邦男の布団を六畳間にしいた。邦男が横になると、スミは目を合わさぬように六畳の電気をけし、襖を静かに閉め、四畳半の電気もけした。
すかさず邦男が、裏返った声で呼びかける。
「スミちゃん、覚えてるかのう?」
月の光が障子を照らし、暗闇も柔らかい。
「なんです? 邦男さん」
スミの声は月のように落ち着いていた。
「あの日なあ、スミちゃんから石鹸の匂いがしてな」
神社で二人っきりなった日のことだ。終戦の年である。
「わしゃ、スミちゃんに、あの日、惚れちまったんだ」
スミの声はか細い。
「ずいぶん昔のことです」
「忘れちまったのかい?」
スミはくすっと微笑むと、
「邦男さんはとっても汗臭かった」
邦男はぐきっと布団の端を握りしめる。すぐには言葉が返せない。
スミは布団を口元に引き寄せ、さらに聞こえにくくしながら、
「でも、それが男らしく……」
「え、なに? スミちゃん、よう聞こえんぞ」
邦男は起き上がると、襖の側に寄り、掌を添えながら聞き耳を立てた。
スミはすこしだけ声を大きくする。
「死んだ父がよく言っていたのです。働き者は匂うものだって」
それも邦男には良く聞こえない。目を白黒させながら、襖をこっそり十センチほど開けると、
「スミちゃんの声が良く聞こえんから、ちょっとだけ、襖を開けさせてもらうよ」
部屋の中を覗こうともせずに、邦男はこそこそ布団に戻るのだった。
スミはそんな邦男にまた微笑んでしまう。
邦男がじっとこちらを見ている。耳に手を当てている。スミは布団の消音を取り除いた。
「汗の匂いは、懐かしい夏の匂いでした」



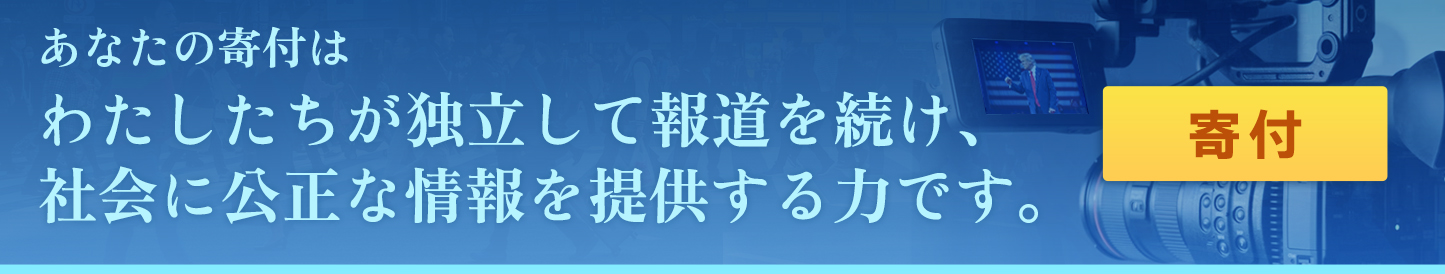












 ご友人は無料で閲覧できます
ご友人は無料で閲覧できます Line
Line Telegram
Telegram














ご利用上の不明点は ヘルプセンター にお問い合わせください。