2022年に漏洩した中国警察のデータが示唆する、中国の実際の人口が14億ではなく、約10億人である可能性がある。本記事では、新型コロナウイルスの流行が、中国の人口に与えた影響と、塩消費の統計から見え隠れする事実について、三回に分けて解説する。
中国共産党は2023年1月に、国の人口統計を更新し、前年に比べて85万人の減少を記録し、60年ぶりに人口が減少したことを発表した。初めての減少かどうかは別として、人口増加が停止したことを公式に認めたのはこれが初めてである。しかし、実際には公表された数字よりも中国の人口減少ははるかに深刻だと考えられるデータが存在する。
2022年6月、上海の警察機関からのデータ流出があり、それにより中国の実際の人口は約10億人である可能性が示唆された。情報の厳格な管理と長年のデータ改竄(かいざん)や混乱が原因で、中国の正確な人口数を知ることは困難である。
21世紀に入ってから、中国の人口は2003年のSARSや2020~23年にかけての新型コロナウイルスの流行により大きな影響を受け、感染症による死亡者数は数億人に上るとされているが、中国共産党はこれを隠蔽している。
日本では過去に、中国人の年間食塩消費量を基に、中国の実人口を推計する方法を用いたことがある。この手法は科学的根拠に基づいており、工業用電力消費、交通量、金融データを分析して経済動向を予測する方法と同様に、一定の傾向と規則性があり、参考になる。健康や味覚を重視する観点から、食塩は料理に不可欠な調味料であり、通常、1人当たりの1日の使用量は一定である。
食塩の生産と供給が十分に確保されているにも関わらず、特定の地域や都市で食塩消費が大幅に減少している場合、住民が意図的に薄味を好むように味覚が変わったとは考え辛く、人口が大幅に減少したためというのが正解であろう。
この記事は、中国の各地域の最新の食塩消費量を分析し、中国の人口が顕著に減少していることを示している。中国人の味覚傾向は、中国大陸の住民ならよく知っている。実際には、中国人が好む味はますます濃厚になっており、東北料理、四川料理、湖南料理、安徽料理などの人気料理は、塩辛さと濃い味が特徴である。また、年々販売量が増加するテイクアウト食品も塩分が多い傾向にあり、塩分の多い食事が原因で心臓病や脳卒中などの疾患が、国全体で増加している。
一 .食塩の種類と基本データ
1. 食塩の種類
中国の「食塩専売法」と「漁業・畜産用塩の管理法」によると、食塩とは直接食用や食品製造に使われる塩である。
塩業界では、用途に応じて食用塩、工業用塩、畜産用塩に分類される。中国国家市場監督管理総局が2020年に発表した食品生産許可の分類目録には、食用塩が食用塩と食品生産加工用塩に細分されている。市場に出回る食用塩は、個人や家庭、飲食業(社員食堂含む)、食品加工業(例えば醤油製造や水産・畜産品の加工)向けである。
市場では、個人や家庭、飲食業向けに小包装の塩が供給され、これを食べる塩と呼ぶ。この文章では後に、食塩の消費量と人口との関連分析を行い、その際にはこの小包装の塩の消費量を一人当たりの食塩摂取量の目安として使用する。
一方、食品加工用の塩は大包装(25キログラムや50キログラム)で販売されることが多い。大包装の塩は、一部地域のデータは公開されているが、多くは地域を超えて販売されるため、人口と直接関連付けることは難しい。例えば、醤油製造工場が出荷する醤油がその地域だけで消費されるわけではなく、他地域にも流通するため、正確な人口統計には向いていない。
2. 原塩の販売量の減少は注目すべき事象である
原塩(海水をただ乾燥させただけのもの)は、食塩や工業塩、その他の化学製品の原料として使用されている。2019年までの中国では、年間約1千万トンが食塩製造に、残りは工業用途に使われていた。
中商産業研究院の統計によると、2022年の中国の原塩生産量は約4986.4万トンで、パンデミック前の2019年の6701.4万トンから約25%減少している。この減少は注目に値する。

原塩のほとんど(約80-90%)は工業用途で使用され、石鹸、染料、医薬品、陶磁器、ガラス製品、日用化学品、石油掘削など多くの分野で利用されている。また、製氷や道路の除雪作業にも使われている。原塩の生産量は徐々に減少しており、これは中国経済の停滞や製造業の下降傾向と一致している。特に、新型コロナのパンデミックが3年間続いている中で、食塩と工業用塩の需要が減少し、原塩生産に大きな影響を与えている。
中国共産党の専門家たちは、原塩の生産減少を在庫削減や財務レバレッジ*の縮小と関連付けているが、彼らが指摘するのは一部の事実に限られ、他の要因には触れていないようである。
*「少ない資金でも大きな取引ができる」という取引方法をレバレッジと呼ぶ。
統計によれば、2017~21年にかけて中国の食塩輸出は輸入を大幅に上回り、海外需要が高いことは明らかである。在庫削減や財務レバレッジの縮小は国内需要の減少が原因で、特に人口減少が大きく影響している。食塩は人間にとって基本的な必需品であり、生活に欠かせない。新型コロナの厳しい封鎖措置が、工業用塩の生産を減少させ、中国共産党が公表していない死亡データが、食塩需要の減少に繋がり、これらの要因が、原塩の生産減少に影響しているとされている。
3. 中国における小包装食塩の販売量
「中国の食塩産業と企業発展の概況(2015年版)」によると、2009~14年にかけてパッケージされた食塩の販売量と市場シェアは減少傾向にある(図2参照)。
2009年の年間販売量は534万トンであったが、2014年には472万トンにまで落ち込み、この期間で11.6%の減少を記録した。対照的に、食品加工用塩の販売は56.1%増加し、生産量の増加や味付けの濃度上昇がその理由である。調味用塩、栄養強化塩、入浴用塩、美容塩、医療用塩などの需要も若干増えている。高級食用塩は価格が高いので、市場での消費者層は限られている。

2017~21年にかけて、食塩の生産は増えているが、小包装の食塩の販売が同様に増えているわけではない。2019年、中塩製塩工程技術研究院の朱国梁院長が指摘したように、最近の食用塩の消費は減っており、一方で食品加工用の塩の需要が増加している。
通常、表面上の需要量は消費量に基づいて概算される。理論的には、食塩の消費量は生産量に純輸入量を加え、在庫を差し引いた数に等しい。2017~21年の間、中国の食用塩の輸出は輸入を上回っているため、純輸入量はマイナスである。その結果、図3に示されるように、食塩の生産量は年々増加しており、これは輸出の増加と食品加工用塩の需要の増加によるものである。また、図に示される表面上の需要量は2018年以降、大きな変動が見られない。これは国内の需要と在庫が安定していることを示している。食品加工や工業用塩の使用が増えれば、家庭での食塩使用量は減少すると考えられる。

(つづく)
















 ご友人は無料で閲覧できます
ご友人は無料で閲覧できます Line
Line Telegram
Telegram






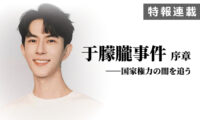






ご利用上の不明点は ヘルプセンター にお問い合わせください。