国連安全保障理事会(安保理)は6月10日、アメリカ主導の決議を採択し、バイデン大統領が5月31日に提案したガザ停戦協定を確認した。安保理の15加盟国のうち、13か国がアメリカの提案に賛成票を投じ、拒否権を持つロシアは棄権した。
この停戦協定は、イスラエル軍とガザ地区を支配するハマスとの、戦闘が終了する可能性を示している。戦闘は8か月以上にわたり続いていた。ガザの保健省によると、戦闘で約3万7124人のパレスチナ人が死亡し、8万4712人が負傷している。しかし、戦闘員と非戦闘員の区別は明確にしていない。
バイデン大統領によると、協定の第一段階は、少なくとも6週間続く予定で、全面停戦、イスラエル軍のガザからの撤退、女性や高齢者、負傷者を含む人質の解放に対する数百人のパレスチナ囚人の解放が含まれている。さらに、毎日最大600台のトラックがガザ地区に食料を輸送する措置も取られる。
第二段階では、第一段階の平和が6週間以上続くことと、さらに交渉が進展することが条件となる。この段階では、ハマスが残りの捕虜を解放することが求められる。捕虜は主にイスラエルの男性軍人である。すべての人質が解放されれば、イスラエルはガザから完全に撤退し、停戦は恒久的なものとなる。
第三段階は、ガザ地区の再建を開始するものであり、ハマスがすべての死亡した人質の遺体を引き渡すことも含まれている。
バイデン政権は、この提案がイスラエル政府の意向に基づいていると述べているが、イスラエル国内では批判の声も上がっている。ネタニヤフ首相は、ハマスに影響を与えない恒久的な停戦には反対しており、この提案はその目標を達成できないと主張する。ネタニヤフ内閣の一部のメンバーも、もし、ハマスを打ち負かすことなく協定が成立すれば、連立政府からの離脱を示唆している。
アメリカのリンダ・トーマス・グリーンフィールド国連大使は、6月10日の投票後、「今日、安保理はハマスに対して明確なメッセージを送った。現行の停戦協定を受け入れよ」と述べた。
過去のガザ紛争を巡る安保理の議論は、メンバー国間での対立を招いていた。アメリカは2月、アルジェリア主導の停戦決議を拒否権で阻止した。3月22日には、中国とロシアがアメリカ主導の停戦決議を否決し、その後、アメリカは別の停戦決議を唯一棄権した。
ロシアのヴァシリー・アレクセイエビッチ・ネベンジャ国連大使は、6月10日の投票で棄権した理由として、バイデン氏の提案の詳細が不十分であることを挙げた。彼はまた、イスラエルがこの提案を完全に受け入れているかどうかも疑問視した。
イスラエル代表、無意味な交渉には参加しない
イスラエルのレウト・シャピル・ベンナフタリ国連代表は、安保理での投票に参加し、イスラエルが停戦協定を結ぶ前にハマスを完全に打ち負かすことを目指していると述べた。
「イスラエルは、すべての人質の解放、ハマスの軍事力と統治能力の破壊、ガザが将来イスラエルに脅威を与えないことを目標としている」とベン・ナフタリ氏は語った。「これらの目標が達成されれば、戦争は終わる。ハマスが人質を解放し、自首すれば、一発の銃弾も必要ない」
バイデン政権は、第二段階の交渉が進展すれば、停戦は6週間以上続くと述べているが、ナフタリ氏は、イスラエルが無期限の停戦を受け入れることはないと警告した。
「イスラエルは、ハマスが再武装し、再編成することを許さない。これは我々の確固たる目標である。無意味で終わりのない交渉には参加しない」とナフタリ氏は述べた。
ナフタリ氏は、安保理メンバーに対し、ハマスに圧力をかけ、人質を解放し降伏するよう促した。
安保理メンバー、民間人の死を非難
ガザ停戦決議の採択後、マルタのヴァネッサ・フレイザー国連大使は、イスラエルに対し、ガザの民間人の被害を防ぐ努力を強化するよう求めた。ナフタリ氏は、6月8日にイスラエルがヌセイラート難民キャンプ付近でハマスによる拘禁から4人の人質を救出したことを歓迎した。一方で、その行動で民間人の死者が出たことに失望を表明した。
「すべての被拘禁者は直ちに無条件で解放されるべきである」とフレイザー大使は述べた。「しかし、イスラエルのヌセイラート難民キャンプへの行動後、数十人のパレスチナ人が死亡したとの報告があり、これは非常に残念である。この事件は孤立したものではなく、ガザが直面する苦しみを象徴している。国際人道法の尊重はすべての当事者に求められる」
スイスのパスカル・バエリスヴィル国連大使も、「救援活動中に報告されたパレスチナ人の高い犠牲者数に衝撃を受けた」と述べ、「民間人と戦闘員、民間物と軍事目標を常に区別する必要がある」と強調した。
















 ご友人は無料で閲覧できます
ご友人は無料で閲覧できます Line
Line Telegram
Telegram

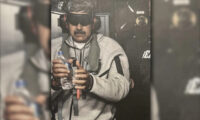












ご利用上の不明点は ヘルプセンター にお問い合わせください。