政府は11日、今後5年間の農業政策の指針となる「食料・農業・農村基本計画」を閣議決定した。異常気象や国際情勢の悪化などによる輸入途絶に備え、国内の安定供給体制の強化と食料自給力の向上を柱とする。コメ輸出を2030年までに8倍に増やすなど、意欲的な数値目標を示す一方、農業の構造的課題をどう乗り越えるかが問われる。
計画案では食品メーカーや外食チェーンの海外収益を1.8倍の3兆円、農林水産物・食品の輸出額を3.3倍の5兆円に拡大。さらに、食料自給率38%を45%に引き上げる。これらは、少子高齢化で縮小する国内市場を補い、海外需要を取り込んで農業を強化する戦略だ。しかし、野心的な数値の裏には乗り越えるべき課題が山積している。
訪日客の食消費4.5兆円 観光頼みの不安
2024年の訪日客は約3500万人と推定されるが、食関連消費を4.5兆円に増やすには、観光客の大幅な増加か1人当たりの支出アップが欠かせない。地方の飲食店や観光資源を活用し、ハラルやビーガンなど多様な食ニーズに応える必要がある。
しかし、飲食業は人手不足が深刻で、地方の観光インフラもまだ十分でない。円安は訪日客の消費を後押しするが、輸入食材の値上がりで飲食店のコストが増え、価格競争力が落ちる恐れもある。国際情勢の不安定さも、訪日需要の変動要因となる。
コメ輸出35.3万トン 高価格の壁
コメの輸出を35.3万トンに増やす計画は、パックごはんなど加工品を武器に日本食ブームを追い風とする。輸出用コメを国内に振り向ければ、食料不足の際の安定供給にも役立つ。
日本産のコメはタイやアメリカ産の5~10倍の価格だ。富裕層や高級店向けに限られがちで、中国や東南アジアでの需要開拓は鍵だが、価格や現地の好みに合うかが課題だ。さらに、農家の平均年齢は67歳を超え、農地面積(2024年で約430万ヘクタール)も減少中。生産拡大には新たな担い手と土地が必要だが、その道のりは険しい。
食品・外食の海外収益3兆円 世界での認知度向上を
食品メーカーや外食チェーンの海外収益を3兆円に増やす目標は、日本食の魅力を世界に広げる試みだ。
欧米の大手ブランドに比べ、日本企業の知名度はまだ低い。現地の食文化や厳しい食品規制に合わせた商品開発、物流網の整備には巨額の投資が要る。円安は収益を増やすが、原材料コストの上昇が利益を圧迫。国内市場が縮小する中、海外と国内の両方で成功する戦略のバランスが求められる。
食料自給率45% 構造転換の難しさ
食料自給率を45%に上げるのは、食料安全保障の要だ。しかし、コメ消費は1960年代の半分(1人当たり年50キログラム)に減り、小麦(自給率18%)、大豆(26%)、飼料穀物(ほぼ全量輸入)に頼る食生活が壁となっている。農地を水田から麦や大豆に転換したり、国産飼料を増やしたりする必要があるが、農地面積の減少と労働力不足が足かせだ。例えば、小麦生産を倍増しても自給率は2%しか上がらず、コストがかさむ。国産品の魅力を消費者に伝える努力も必要だが、食文化を変えるのは簡単ではない。
輸出額5兆円 国際競争の激化
農林水産物・食品の輸出を5兆円に拡大するには、和牛や果実など高付加価値品が鍵だ。一方、アメリカやオーストラリアの低価格品との競争や、中国の輸入規制などの障壁が立ちはだかる。輸送によるCO2排出や物流コストも課題で、環境意識が高いヨーロッパでは持続可能な取り組みが求められる。中小企業が輸出に参入するには資金や知識の支援が急務だが、支援体制の整備は遅れている。
共通の課題 担い手不足と気候変動
すべての目標を支える農業は、深刻な課題に直面している。2024年の就農者は約110万人で、10年前から3割減少。スマート農業や若手の就農支援は進むが、規模拡大は遅々として進まない。気候変動による不作や豪雨、国際情勢(例 ウクライナ紛争)の影響もリスクだ。自給率向上と輸出拡大は時に相反し、限られた農地や労働力をどう使うかの優先順位が不明確だ。
農水省の目標は、人口減少に直面する日本の食と農業に新たな可能性を開く挑戦だ。しかし、生産基盤の弱さ、国際競争、気候変動への対応など、課題は山積みしている。成功には、最新技術の導入、若手農家の育成、国産品への消費者意識の向上、国際連携が欠かせない。単に数字を追うのでなく、環境と共生し、食の安全を支えるシステムを築く必要がある。日本食が世界で輝く未来は、こうした努力にかかっている。














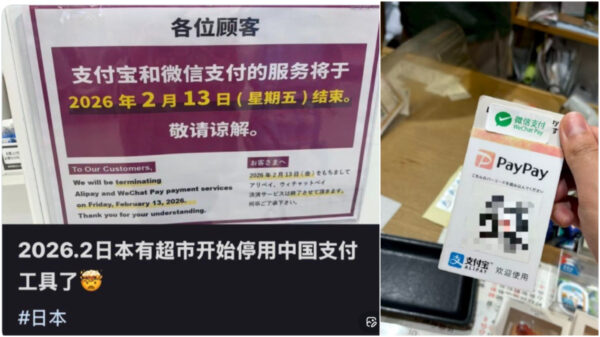
 ご友人は無料で閲覧できます
ご友人は無料で閲覧できます Line
Line Telegram
Telegram








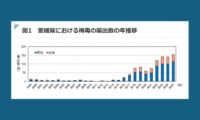





ご利用上の不明点は ヘルプセンター にお問い合わせください。