7月26日に台湾史上初の大規模なリコールが行われた。対象となったのは国民党議員24人と新竹市長だったが、いずれも成立には至らなかった。そこには、中国共産党(中共)による認知戦、政党による戦術的な対応、台湾特有の政治文化など、複数の要因が複雑に絡み合っている。本記事では、全25件が不成立となったこの“リコール完敗”の理由と、それが台湾政治に与える影響を多角的に分析する。
台湾史上前例のない「大リコール」行動は世界の注目を集めた。7月26日に行われた第一波リコールでは、市民団体が24人の国民党の立法委員(議員)と新竹市の高虹安(こう こうあん)市長に対してリコールを行うことに大きな期待を寄せていた。これは「朝小野大」と称される立法院(議会)の政治構図を変え、「親中」や「親共」といった行為を抑制することを目指している。しかし結果は、有権者がすべてのリコール案を否決し、25件すべてが失敗に終わった。
この大規模な政治運動が失敗に至った背景には、台湾社会の歴史、文化、民族構造、政治生態、そして外部勢力の影響が複雑に絡んでいる。本稿では、特に重要な六つの原因に焦点を当て、この運動がなぜ現状を動かせなかったのか、そして台湾社会にどのような影響をもたらすのかを分析する。
一、中共による長期的な認知戦の浸透
中国共産党(中共)は、台湾社会に対して長期的な認知戦を仕掛けてきた。親中共メディアやSNS、有名人などを通じて中共の意向に沿う世論環境を形成し、今回の大リコールに対しても破壊工作を展開した。
台湾国内では、親中共メディアが「両岸平和」「経済繁栄」といった美辞麗句を使い、中共の脅威を意図的に覆い隠している。今回のリコール行動も「反中感情」「イデオロギー闘争」といったレッテルを貼り、本来の国家安全保障という問題意識を曖昧にしていた。
さらにSNSでは、親中アカウントや偽情報がリコール団体の士気と動員力を削いだ。こうした状況は、単発的な現象ではなく、長年にわたる浸透戦略の成果である。有権者の一部は、リコールを「政治的茶番」と捉え、国家防衛の一環とは認識しなかった。
中共は台湾社会に根強く残る「戦争への恐怖心理」をも利用した。有権者の中には、リコールが両岸関係の緊張を高めると懸念し、投票に消極的な姿勢を示した。その結果、リコール団体は「反中共」の理念を広く浸透させられず、世論場で劣勢を強いられた。
現実には、立法院の一部勢力が国防予算を削減し続けてきたが、それによって平和が訪れることはない。ロシア・ウクライナ戦争の教訓からも明らかなように、弱腰な姿勢は侵略を招くに過ぎない。台湾が平和を守る道は、軍事力を強化し、アメリカ・日本・オーストラリアなどの民主同盟国との連携を深めることである。平和は実力からしか生まれず、妥協や譲歩では得られない。
二、メディアと政党による議題のすり替え
リコール運動が失敗した第二の要因は、メディアと政党が議論の焦点を巧妙にすり替えたことである。
2024年の総選挙後、国会に当たる立法院で過半席を占める野党の国民党と民衆党は「国会改革法案」を推進したが、青鳥運動や市民団体はこれを強く批判し、中共の浸透を促す内容だと警鐘を鳴らした。しかし、リコール対象となった国民党および一部メディアは、速やかに議題を生活問題や政党間対立に移し、法案自体への関心を薄めた。
国民党は「生活を優先」と主張し、リコール行動を民進党による「政治的報復」と位置付けた。一部メディアも地方経済や生活議題を前面に出し、リコールを「イデオロギー闘争」と単純化した。こうした言説が有権者の関心を分散させ、「反中共」や「民主防衛」というリコールの本質が霞んでしまった。
さらに、国民党と民衆党は「リコールにリコールで返す」という戦術を採り、民進党陣営に対する報復的なリコール署名運動を展開した。その結果、有権者の多くがリコール全体を「政党の応酬劇」と捉えるようになり、市民団体の訴えは浸透力を失った。
三、国民党優勢の選挙区における高い動員力
2024年の総選挙後、有権者の構造には大きな変化がなかった。リコール対象となった24人の国民党議員はいずれも「国民党優勢」の選挙区に属しており、国民党陣営は強固な支持基盤を保持していた。リコール署名は成立したものの、実際の投票では国民党陣営の組織力が圧倒的に勝った。
国民党は、自党の影響力が削がれることを回避すべく、リコール阻止に全力を注いだ。地方派閥や基層組織が一体となって動員を行い、多くの有権者を投票所に送り込んだ。例えば、台北の蔣万安(しょう ばんあん)市長は徐巧芯(じょ こうしん)議員に同行して投票所に赴き、団結ぶりをアピールすると同時に、有権者の信頼を高めた。
これに対し、リコール団体は主に若年層やSNSを中心とした活動に頼っており、地上戦では力不足が目立った。
また、台湾のリコール制度は成立条件が厳しい。有権者総数の4分の1以上が投票し、そのうえで「同意」票が「不同意」票を上回る必要がある。国民党陣営が積極的に投票を呼びかければ、リコール団体はこの二重ハードルを超えることが難しくなる。結果として、25件すべてが成立に至らなかった。
それでも、第三段階まで進み、多くの有権者が「同意」票を投じた事実は、政治的環境の中では一種の奇跡とも言える現象である。
四、民進党は気を使いすぎて動員力と長期政権の蓄積効果を欠く
民進党は国民党と比較して、終始慎重な態度を貫いてきた。立法院での法案否決に直面しながらも、「政党間の争い」と見なされることを避ける姿勢を崩さず、党内の主要政治家は大規模なリコール運動への支持表明を避けてきた。この姿勢によって、リコール推進側の動員力は大きく制限され、民進党陣営の支持層においてもリコールを支持しない層が広がった。
民主国家では、いずれの政党も政権を担えば問題を積み重ねる可能性がある。有権者は選挙を通じて評価し、結果次第で政権は交代する。うまく政務を執行できなければ、有権者は投票でその結果を突きつける。
2016年以降、民進党は約10年にわたり政権を維持してきたが、その間に国民の不満が多く積み重なった。経済、エネルギー政策、住宅問題などにおいて、有権者の一部は不満を強めている。これが「権力の傲慢」といった印象を形成し、中間層の一部がリコール運動に対して消極的な立場を取る要因となっている。彼らは、リコールを民進党が裏で操作する政治的手段と見なし、市民の純粋な声とは認識していない。
また、もう一つの重要な要素として、台湾の保守層と民進党の価値観の違いが挙げられる。米国では、保守・リベラル両党とも中国共産党に対抗している。しかし、台湾では、民進党が積極的に反中共を掲げているが、理念上は、リベラル政党であり、この価値観が保守的な有権者には馴染みにくいものとなっている。たとえば、同性婚の合法化などの政策がその典型である。
ここで想起されるのが、覚者や予言者が語った「末法の時代」という概念である。社会価値観の混乱は中共の浸透を招く隙となる。
一方、アメリカではトランプ政権の一期目の後半以降、「中共」と「中国」を明確に区別する認識が広がった。中国を愛することは中共を支持することではないという立場を政府が発信してきた。しかし、台湾の民進党はこの点において明確な区別を打ち出す場面が少なく、「中国の侵略」という表現で中共の脅威を語ることが多い。この認識の曖昧さが、国民党内に存在する「中華民国を愛し反中共を掲げる」勢力の結集を妨げ、さらには中共および親中メディアによる認知戦に付け入る余地を生んでいる。
五、地方選出議員の地域活動と有権者との結び付き
リコール対象となった国民党の議員、例えば傅崐萁(ふこんき)氏や徐巧芯氏らは、長年にわたり地元で活動を続け、強固な支持基盤を築いてきた。彼らは、地域のインフラ整備や予算獲得を通じて、有権者との信頼関係を構築してきた。
台湾の有権者は感情を重視する傾向が強く、国家安全保障よりも「地元のために尽くしてきたかどうか」が投票行動を左右することが多い。傅崐萁氏は中共常務委員・王滬寧とつながりを持ち、台湾に混乱をもたらそうとしていると批判を受けたが、地元では「花蓮王」と呼ばれるほどの影響力を保ち、リコールの圧力を容易に跳ね返した。
この現象はアメリカでも見られる。信仰心や愛国心が強い米国民が、なぜ民主党候補を支持するのかと疑問を持たれることがあるが、地域に根差した候補が有権者の信頼を獲得するという構図がその一因である。
六、中央と地方における投票行動の乖離と台湾独自の政治文化
台湾の総統選挙を観察すれば、有権者が「総統票」と「政党票」を別々に扱っていることに気づく。たとえば、蔡英文氏や頼清徳氏に総統としての信任を与えながらも、政党票では民進党ではなく、別の政党に投票するという行動を取る。
2020年の選挙では、蔡英文氏が得票率57.13%(817万231票)で国民党の韓国瑜氏(38.61%、552万2119票)を大きく上回ったが、政党票では民進党が33.98%、国民党が33.36%とほぼ拮抗していた。
2024年も同様の傾向が見られた。頼清徳氏は40.05%(558万6019票)で勝利したが、政党票では民進党36.16%、国民党34.58%であり、その差は2ポイント未満だった。台湾民衆党は22.07%を獲得し、一定の存在感を示した。
このような現象は、有権者が台湾総統選では「国家を守る候補」を優先し、議員選では「地元を守る人物」に投票するという傾向を反映している。したがって、リコール運動において主催者が「反中共」や「民主主義の防衛」を訴えても、有権者は地元の議員を手放すことに消極的であった。
さらに、第三党の民衆党の支持者の一部がリコールに不同意の立場を取ったことにより、リコールの動きは一層勢いを失った。
今後の展開:リコールは後に影響を残す 市民の力は今後さらに大きな役割を発揮する可能性
7月26日のリコールは一段落した。8月に予定される第2波リコールは残り7議席のみとなっており、実質的な影響は限定的である。また、台湾の「選挙法」により、リコールが一度不成立に終わった場合、対象者の任期中に再びリコールを仕掛けることは不可能である。この規定により、大規模なリコールの動きは一時停止する形となり、今後は頼清徳政権が重大な試練に直面することになる。
ただし、この展開はすべてをリセットするものではない。青鳥運動、ブラックボックス法案(改正国会職権関連法)への反対運動、さらには全土に拡大したリコール行動の流れを通じて、台湾の市民はもはや政治の采配を一方的に受け入れず、「親中共勢力」に立法機関を支配させることを拒否する姿勢を明確にしている。これは、市民社会の力が目覚めた証左である。
リコールが不成立に終わった後、民間の動きはより戦略的な「長期抗争」モデルへと移行する可能性が高い。具体的には以下のような方向が考えられる。
議員の出席状況、法案提出、投票記録を監視し、その情報を社会へ公開し、メディアによる監視を促進する。
地域団体や若者世代との連携を深め、「市民政党」あるいは「地域監督プラットフォーム」の再構築を進める。
2026年の県市長・議員選挙の準備に関与し、リコールによって蓄積されたエネルギーを選挙での投票行動へと転化させる。
台湾の過去のリコールに関する歴史的事例を振り返れば、リコール対象となった政治家の多くが短期的には議席を保持したものの、次回選挙で敗北あるいは立候補を断念する事例が頻発している。リコールという行動がもたらすイメージの損傷や社会的評価は、時を経て政治的な影響力を弱体化させる効果を持っている。
たとえば、時代力量の黄国昌氏は2017年にリコール運動の対象となり、結果は不成立だったが、その後に勢いを失い、2020年の再選を見送って静かに立法院から退いた。国民党の陳学聖氏は正式にリコール対象とはならなかったが、繰り返される署名活動や批判の中で支持を喪失し、2018年の市長選に敗北した後は政界から姿を消した。
これらの経験から考えれば、今回リコールの対象となった30人余りの政治家の中にも、今後の選挙で有権者の審判を受け、政治的命運を転換させられる者が相当数現れることになる。まさにその時こそ、真の政治的代償が具現化する瞬間である。
頼清徳総統にとって、今回のリコール不成立は強烈な警鐘である。もし彼が閉ざされた「高い壁」の外に出て、社会からの監督を受け入れ、政権チームの刷新を進めなければ、政策の推進は難航し、2026年の中間選挙、さらには2028年の総選挙において、四面楚歌の危機に直面することになる。
国際情勢の観点から見ても、中共は今回のリコール失敗という結果を利用し、認知戦および経済的恫喝をさらに強化しようとしている。これにより台湾内部の分裂や動揺が拡大し、中共の侵略戦略を後押しする可能性がある。もし台湾の与野党が「基本的な民主主義の共通認識」を構築できなければ、内部の対立は中共の攻勢をより深刻なものとするだろう。
それでも、私は悲観しない。中共の企図はもはやすべて失敗し、すでに民心と国際社会の信頼を失っている。台湾を呑み込むなど、もはや不可能である。
天は中共を滅ぼし、天は台湾を守る。



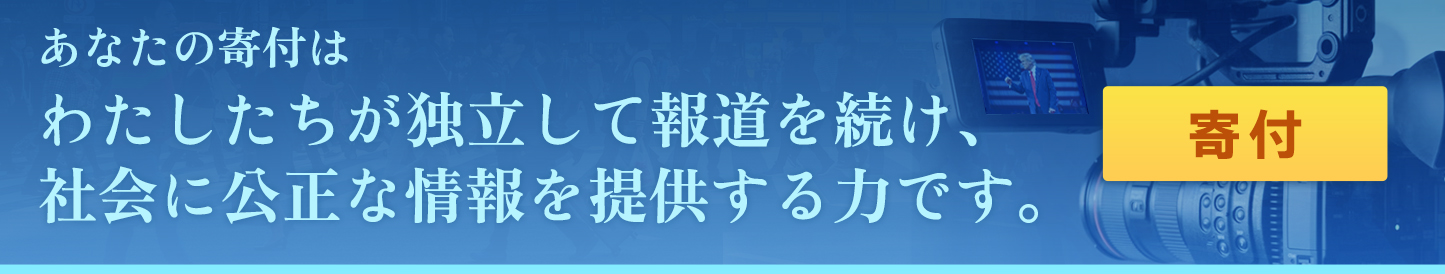












 ご友人は無料で閲覧できます
ご友人は無料で閲覧できます Line
Line Telegram
Telegram














ご利用上の不明点は ヘルプセンター にお問い合わせください。