漫画『ベルサイユのばら』の映画版は、昨年の秋に公開された。原作の漫画は池田理代子氏によって描かれたものであり、「少女漫画」あるいは「恋愛小説」と呼ばれるジャンルに属している。本日はこの映画、そして原作漫画について論じる。
なぜなら、残念ながらこの作品は日本で非常に広く知られており、数多くの日本人にとって、ヴェルサイユ宮廷、そしてそれを通じて旧体制のイメージの基盤となっているからである。
純粋にフィクションや小説としての観点から見ると、これはまさに恋愛小説のジャンルに属し、マリー・アントワネット、フェルセン、オスカルという古典的な三角関係を描いた作品だ。プラトニックな愛を背景に、このジャンルに典型的な大袈裟な表現や、このジャンルに典型的なグラフィック的な手法(大きな輝く目、宮廷の華やかさ、フリルなど)が用いられている。
一方、その内容に関しては、映画も漫画も、1950年代から60年代にかけての革命史学で流行した歴史上の固定観念を提示している。漫画は、フランスと世界にとって暗黒の時代であった1972年と1973年に出版された。革命の勝利、性的解放、フェミニズム、そして信徳と道徳を破壊した第二バチカン公会議の精神の勝利を背景としている。
マンガはフィクションであるはずだが、主人公オスカルも架空の人物であるにもかかわらず、マンガの中ではすべてが現実のように見えるように作られており、実際の歴史に精通していない多くの人々は、描かれている出来事が歴史的事実だと思い込むだろう。
しかし、それは大変な間違いだ。この漫画は歴史的観点から見ると、著しく不正確で偏見が多く、事実として誤った描写が多数存在している。
この漫画は、革命的な歴史観を無批判に受け入れており、さらに、これらの著者がたとえ非常に革命的な人物であったとしても、口には出さないような重大な誤りも含まれている。フィクションと想像力は、あらゆる誇張を許すようだ…。
歴史小説は、この点で恐るべき戦争の武器となる。なぜなら、誤用されれば、作者にその意図がなくても、完全に誤ったイメージを永続的に植え付ける可能性があるからだ…。
紙を売るため、人々の娯楽のためという理由があっても、すべてが正当化されるわけではない。
この漫画のもう一つの偏向の特徴は、日本の歴史の厳しく暴力的で不公正な側面を、アンシャン・レジーム(旧体制)の現実に投影しているという非常に興味深い現象にある。率直に言えば、18世紀のフランスの宮廷を描いているのではなく、江戸の将軍時代を西洋風の衣装や宮廷で覆い隠しているだけである。
また、本作には宗教的な側面は全く描かれていない。宮廷で重要な存在であった聖職者や司祭は一人も登場せず、革命時の宗教的迫害や聖職者民事基本法に由来する「宣誓拒否聖職者問題」など、重要な宗教的テーマが完全に排除されている。
地政学的な状況への理解も図式的に単純化されており、それは恋愛小説の単なる背景としてしか機能していない。
このジャンル特有の甘美な物語の展開通り、宮廷での個人的な出来事が連鎖して描写され、マリー・アントワネットの生涯をある程度追っているが、当然ながら彼女の裁判までは描かれておらず、あたかも彼女が自らの行動の結果として相応の結末を迎えるのが「当然の報い」であるかのような印象で終わっている。
しかし、これらの間違いは本質的には二次的な要素に過ぎない。問題は、この漫画の大成功が、まさしく反歴史的な疑似歴史的側面に支えられていることである。
この漫画のせいで、間違った革命のイメージやマリー・アントワネットのイメージが作られてしまった。
この点をさらに明確にするため、いくつか具体例を挙げてみることとしたい。
(つづく)


 第1回:革命と宮廷の幻想――『ベルサイユのばら』が作ったフィクションと歴史認識の危うさ
第1回:革命と宮廷の幻想――『ベルサイユのばら』が作ったフィクションと歴史認識の危うさ  第2回:「レディ・オスカル」の同性愛的転覆と歴史の歪曲――旧体制と女性像の真実
第2回:「レディ・オスカル」の同性愛的転覆と歴史の歪曲――旧体制と女性像の真実  第3回:バスティーユ襲撃の真実――革命の血塗られた幕開けと歴史の再考
第3回:バスティーユ襲撃の真実――革命の血塗られた幕開けと歴史の再考  第4回:江戸がヴェルサイユを覆う――日本式封建ドラマとしての『ベルばら』
第4回:江戸がヴェルサイユを覆う――日本式封建ドラマとしての『ベルばら』  第5回:虚像が歴史を支配する時 「ベルばら革命」に警鐘を鳴らす
第5回:虚像が歴史を支配する時 「ベルばら革命」に警鐘を鳴らす 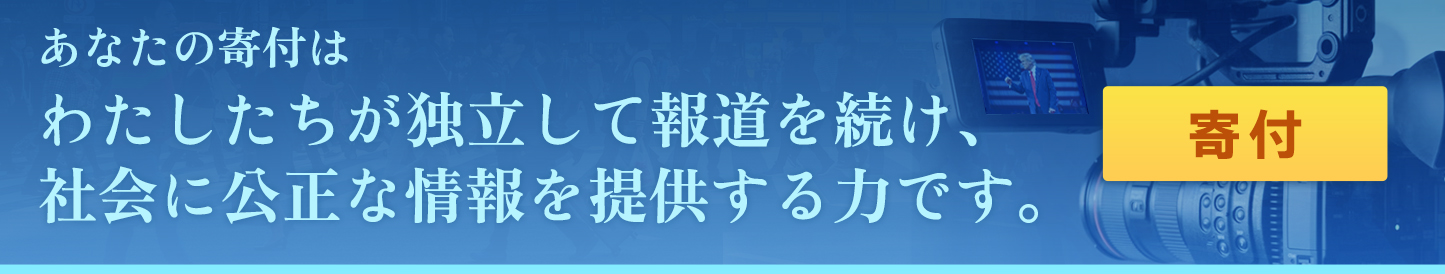












 ご友人は無料で閲覧できます
ご友人は無料で閲覧できます Line
Line Telegram
Telegram














ご利用上の不明点は ヘルプセンター にお問い合わせください。