漫画『ベルサイユのばら』の映画版は、昨年(2024年)の秋に公開された。原作の漫画は池田理代子氏によって描かれたものであり、「少女漫画」あるいは「恋愛小説」と呼ばれるジャンルに属している。本記事はこの映画、そして原作漫画について論じる全5回シリーズの第4回目の記事である。
III. 昔の日本を昔のフランスに誤って投影
ここで、私たちのささやかな分析の中で最も興味深い点、そして多くの評論家たちが見過ごしていると思われる点に触れる。それは、日本の歴史をフランスに投影している点である。
この傾向は一方で顕著に現れ、他方で歴史的には全く誤ったものである。この点は、日本とヨーロッパ(ここではフランス)が類似した、同等の歴史を持つと信じる日本の歴史学の伝統を如実に示しているだろう。これは、日本の誇りを支え、現在の状況を安心させる方法でもあるだろう。
しかし、これは歴史的に大きな誤りであり、この問題について深く研究すると、旧体制下のフランスと旧日本社会は、表面的な類似点はあるものの、その精神や制度は根本的に対照的であることがすぐに明らかになる。一言で言えば、その違いは、カトリックが制度、王権、社会に与えた影響に起因する。
ここですべての例を挙げることはできないが、少なくとも、同様のテーマについて「中世」の日本と「中世」のフランスのやり方を比較しながら、いくつかの考察の材料を紹介しようと思う。
a. ルイ15世による使用人に対する即決かつ不公正な判断
その材料となるひとつの場面を要約しよう。オスカルの使用人アンドレは、マリーアントワネットの馬術訓練の補佐中に、彼自身には責任のない純粋な事故を起こしてしまった。この事故は王女に重大な被害をもたらす可能性があったが、結局は何事も起こらずに終わった。
その後、ルイ15世はアンドレと彼の主人オスカルを威厳に満ちた姿で呼び出し、アンドレを裁き、死刑を宣告する。しかし、オスカルがアンドレの身代わりになって王の特赦を請うことで、アンドレは最終的に救われる。
この場面は、日本の現実をフランスの過去に投影した想像の産物であり、歴史上、現実には決して起こったことのない、また起こり得ない出来事である。
このような情景は、主、領主、王の権力がローマ時代の家長の権力のごとく広範であった時代の日本において起こり得た典型的なものである。当時は、厳格な手続きを経ずに、臣民や「家」の構成員の生死を決定できる世であった。すなわち、主人が使用人だけでなく、自分の妻子や家族全員を所有していた支配の現実があった。また連座制度が存在し、身売りも行われていた世界である。
しかし、このような状況はキリスト教的色彩の強い王政フランスでは全く見られなかった。王の権力は、天主や自然法、教会の法や慣習、そして法の手続きといった、より上位の規範によって当然制限されていた。王は決して自らの臣民をこのように即断即決で裁くことはできず、必ず法が適用されなければならなかった。
旧体制下においては簡易裁判は存在せず、王の司法を実際に執行する多くの王政官人、とりわけ高等法院は、制度上大きな力を持ち、時に王の機能を阻害し、王国の改革を麻痺させることさえあった。
ヴォルテールがラ・バル騎士事件やカラ事件などについて描いた偽のスキャンダルも、こうした事態が現実には考えられなかった証左である。
仮に『ベルサイユのばら』で描写されるような独裁政治や簡略裁判が可能だったならば、啓蒙思想家たちは王政を攻撃する格好の材料として飛びついたであろう。
しかし、実際にはそのような批判もなければ、虚偽の主張すら存在しなかった。それは、このような事態がそもそも不可能であり、想像すらされなかったためである。
さらに強調すべきは、王が個人的に裁きを行うことができたのは、「リット・ド・ジュスティス(Lit de justice)」(王親臨の荘厳裁判あるいは勅令公布)と呼ばれる厳粛な決定を下す時、もしくは、極めて明確な手続きが踏まれ、常に官吏や関連機関が関与する場合に限られていたという点である。王が自らの判断だけで事件を簡易に裁くことは、決して許されていなかった。
「ベルサイユのばら」に描かれた上記の場面は、キリスト教の道徳的基盤を完全に無視しているという点において、なお一層荒唐無稽である。罪なき者が、仮にそのことで死に至るとしても、他の罪なき者を厳しく罰することはできない。当時、過失致死にはすでに刑罰の軽減規定が存在し、場合によっては罪そのものが免除される可能性もあった。
さらに、作中の場面には負傷者もおらず、王族への冒涜や攻撃に該当する行為も全く見られない。キリスト教国において、偶発的、かつ故意でない行為による死亡事案で、死刑に処されることはありえない。
フランスの歴史的文脈に照らせば、この場面は著しく荒唐無稽であり、むしろ当時が極めて公正であったというイメージを歪めている。
おそらくこのシーンが意味を持ち、心に訴えるものとなっているのは、それが日常であったわずか150年前――漫画が出版された当時から遡って100年前、すなわち曾祖父母の世代まで――の江戸時代の日本人、あるいは現代フランスにおいてそうした状況を経験し始めた人々だけなのである。
b. 貴族が馬車の前を通りかかった貧しい人を殴る風刺
フランスではありえない、日本の過去を題材にしたもう一つの不条理な場面の例を紹介する。貴族が、馬車の前を「あえて」通りかかった農民、しかも子供(このジャンルでは涙を誘う必要がある)を、ほとんど死に至るまで殴りつけるという場面がある。農民はアンドレによって間一髪で救われ、同時にアンドレは貴族をも民衆のリンチから救うのである。
この場面は、キリスト教の騎士道精神(未亡人や孤児を守るべし)と「貴族の義務(ノブレス・オブリージュ)」に深く根ざしたフランス貴族の現実と真っ向から矛盾している。
聖木曜日、イエズス・キリストが使徒たちの足を洗い、自ら奴隷の仕事を引き受け、彼らにも互いに足を洗うよう命じたように、キリスト教の指導者である貴族たちも同じ義務を負っており、実際にその義務を多くの場合真剣に履行していた。なぜなら、彼らの名誉がかかっていたからである。このような暴行は決してフランス社会では容認されることがなかった。
ここでもまた、フランスの昔の法律が私たちの主張を証明している。フランス王国では、貴族たちは他の者たちと同様、法律に従わなければならなかっただけでなく、貴族であるということが刑罰を重くする要因となっていた。同じ犯罪でも、貴族は農民よりも厳しい罰を受けたのだ。
日本やその他異教の地では逆だ。法律(成文法)は庶民にのみ適用され、貴族、宮廷、領主は法律の上に立つ。彼らは、相互に殺し合いにならないよう礼儀作法(いわゆる礼と法との関係)によって規制されているだけだが、法律に服従する民衆に対しては、あらゆる権力を持っている。
この種の寡頭政治は、現代のグローバリズム社会にも通じるのではないか。今日では、あるエリート階級が事実上法律の上に立ち、もはや法律が彼らに及ばず、一般大衆にとってのみ苛烈となっている。このような論理に従えば、権力者は弱者を自らの利益のために自由に利用できるということになる。
しかし、これはかつてのフランスには存在しなかったことである。不正の行為を行った貴族は民衆のリンチを受ける必要すらなく、司法のもとで裁かれた。ジャンヌ・ダルクの副官にして元帥の地位にあった、しかし子供を虐待する卑劣な強姦犯であったジル・ド・レイ元帥の事件を思い起こすべきである。彼は高位の身分にもかかわらず、法廷により死刑判決を受けている。
この映画に出てくる上述の場面も、江戸時代の日本の現実をフランスの過去に投影したものである。たとえば、領主の行列を横切れば即刻死刑に処されるという慣習は、日本の江戸時代に深く根付いたものだった。犠牲者には外国人も含まれ、特に有名なのが1862年の「生麦事件」であり、4人のイギリス人が大名行列を横切ったために殺害された事件である。
(つづく)


 第1回:革命と宮廷の幻想――『ベルサイユのばら』が作ったフィクションと歴史認識の危うさ
第1回:革命と宮廷の幻想――『ベルサイユのばら』が作ったフィクションと歴史認識の危うさ  第2回:「レディ・オスカル」の同性愛的転覆と歴史の歪曲――旧体制と女性像の真実
第2回:「レディ・オスカル」の同性愛的転覆と歴史の歪曲――旧体制と女性像の真実  第3回:バスティーユ襲撃の真実――革命の血塗られた幕開けと歴史の再考
第3回:バスティーユ襲撃の真実――革命の血塗られた幕開けと歴史の再考  第4回:江戸がヴェルサイユを覆う――日本式封建ドラマとしての『ベルばら』
第4回:江戸がヴェルサイユを覆う――日本式封建ドラマとしての『ベルばら』  第5回:虚像が歴史を支配する時 「ベルばら革命」に警鐘を鳴らす
第5回:虚像が歴史を支配する時 「ベルばら革命」に警鐘を鳴らす 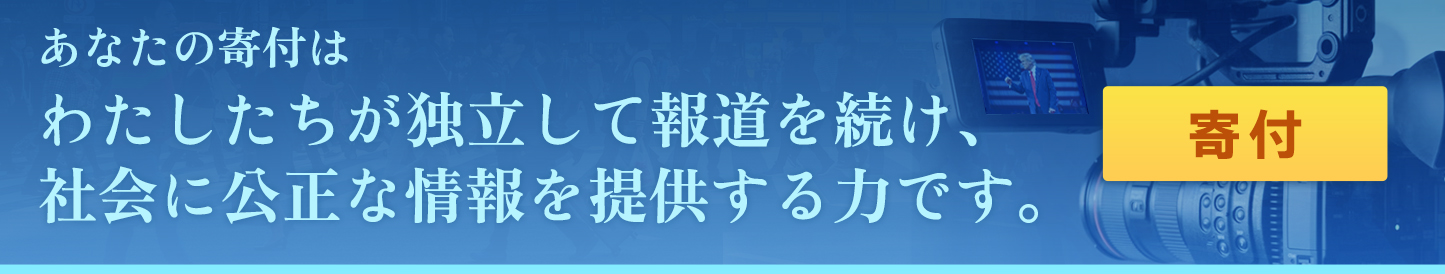












 ご友人は無料で閲覧できます
ご友人は無料で閲覧できます Line
Line Telegram
Telegram














ご利用上の不明点は ヘルプセンター にお問い合わせください。