はじめに
2024 年パリ・オリンピックの開会式は、イエズスの最後の晩餐を冒涜するシーン、マリー・アントワネット暗殺を賞賛するシーン(まったく恐ろしい描写)、LGBT などの推進の名の下に、不自然な行動を奨励するシーンで全世界に衝撃を与えた。
宗教がなんであろうが、国籍がなんであろうが、政治思想がなんであろうが、これらのシーンがオリンピックを不必要かつ衝撃的に傷つけ、『オリンピック』の精神に反するものであることは誰もが認めるところであった。
ブルボン家の末裔であるアンジュー公ルイは、フランス王の正当な末裔であり、ルイ 20 世の名で王位継承法上、実質的なフランス王であるが、2024 年 7 月 29 日付の大手フランス紙1で、「パリ・オリンピックの開会式は、フランスの古くからの遺産の一部を嘲笑することによって、そのオリンピック創設の理念と従来の高尚さから逸脱した。フランスのこの遺産は尊敬と崇拝に値する」と出張し、そして、1793 年以来フランス歴代国王がたゆまぬ努力を続けてきたように、フランス国民に、またフランスのすべての友人に以下のように呼びかけた。
「屈辱と軽蔑を感じたすべてのフランス国民、神聖で宗教的な感覚を持つすべてのスポーツマンおよびスポーツウーマン、そして憤慨したすべての世界中の国民に告ぐ。この開会式は単に、自分たちが恩義を感じている千年前の遺産を踏みにじったイデオローグたちの発案にすぎない。このような大規模な式典が、事前に計画され、考え抜かれたものでなかったわけがない。偶然や不器用さに委ねられるものは何もない。わが国は、この極めて不自然で破壊的なイデオロギーからますます攻撃を受けている。それゆえ、私たちフランス人にとって、フランスに望むモデルを選択することが日々、緊急性を増している。愛する祖国を再建し、伝統、尊敬、団結に根ざした堅実で信頼できる未来を築く必要がある」
このメッセージは、家族の破壊、社会の破壊、各国の歴史や神聖さの否定につながる革命によって、学校や外交、社会問題で苦しんでいる日本に向けられているようにも思える。
しかし、この式典は、あくまでフランス革命の精神を反映したものに過ぎない。そしてその精神は、今や「グローバリズム」と呼ばれる世界規模の革命へと姿を変えている。日本も、他のすべての国々と同様に、この「フランス的」でない――フランスを含む全ての国を否定する――より大きな「世界革命」に巻き込まれている。
本稿の第一の目的は、「革命」に照らして現代史を読み直すことである。革命は決して終わることがなく、さまざまな形をとるが、その精神は現代に至るまで同じである。第二の目的は、1789年以降に世界で起こってきた出来事について、そして日本も知らず知らずのうちに「革命」の影響を受け、その被害者となっている現実について考えることだ。革命によって否定され続けてきたフランスの経験を知ることは、日本にとっても大いに参考になるだろう。
人権主義、リベラル・デモクラシー、共産主義、近代的な戦争の在り方、東京裁判史観、その他多くのものは、すべて同じ「革命的な毒」の現れであり、これらは必ずしも暴力的な形で現れるとは限らないが、文化・性別・宗教の差異の消失をもたらし、やがては性別、家族、上下関係、職業などの分化を基盤とした全ての社会秩序を破壊するものだ。
I.フランス革命とはなんであるのか
革命とその進展に直面した伝統的なフランス人は、この問題について多くのことを考えた。『ソフィーのいたずら』などで知られるセギュール伯爵夫人の息子であるルイ=ガストン・ド・セギュールの言葉を借りよう。19 世紀末に書かれた小冊子『若者たちに説明する革命』(La Révolution expliquée aux jeunes gens)の中で、彼はこう説明している。
「革命とは、前世紀末にフランスを、さらにはヨーロッパを震撼させた歴史的で血なまぐさい大事件でもない。革命という出来事は、その穏健な段階においても、また恐るべき行き過ぎにおいても、事実以上に思想であり、原理である革命の果実、現れ、結果に過ぎない。これらを混同しないことが重要である。では、革命とは何か?」
さて、セギュール氏の答えを見よう。
「最も一般的な意味でとらえれば、革命とは、原理として、また基本法として確立された『反乱・反抗・反逆』である。革命とは、暴力的反乱という事実だけではない。いつの時代にも反乱はあったからである。
– 革命とは合法化された反乱であり、反乱の原理が現実的な規則となり、社会の基礎となることである。
– 正当な権威を徹底的に体系的に否定する反乱の理論である。
– それは反乱の賞賛であり誇りであり、すべての反乱の原理そのものを法的に聖別するものである。また、正当な上司に対する個人の反乱でもない。この反乱は単に不服従と呼ばれるからである。
– それは社会としての社会の反乱である。革命の性格は本質的に社会的なものであり、個人的なものではない。
革命には 3 つの段階がある:
1. 教会の破壊
私たちに直接関係するこの第一段階では、革命は、原則的に設定され、法律に定式化された教会の否定であり、国家を発見し、その根本的な支持を奪うことを目的とした教会と国家の分離である。
2.王位と正当な政治的権威の破壊である。
王位と正当な政治的権威の破壊は、カトリックの権威の破壊の必然的帰結である。この破壊は、近代民主主義の革命的原理と、現在人民主権と呼ばれているものの最後の言葉である。
3.社会の破壊、家族と所有権の破壊につながり、これらの破壊は国家強化の利益のためである。
社会の破壊、すなわち、社会が神から受けた秩序の破壊、言い換えれば、革命家たちが国家と呼ぶ抽象物の利益のために、家族の権利と所有権を破壊することである。
これが社会主義である。
これが社会主義であり、完璧な革命の最後の言葉であり、最後の反乱であり、最後の権利の破壊である」
現代のグローバリズム研究者であるピエール・イラールの足跡をたどりながら、この革命は共産主義的、自由主義的な形態を経て、今日もグローバリズムの標準化という形で続いていることを付け加えておこう。
「2019/2020 年の変わり目にダボス会議『世界経済フォーラム』の庇護の下で推進された有名なグレート・リセットに関連して、COVID-19 によって始められた人類を圧制した諸要素(恐怖政治、社会コントロール、監視社会、基本的自由制限)は、最も完全な隷属化させる特徴を持つ別の世界の利益のために、ある世界を破壊することを目的とした、明確に定義された形而上学的方向性に基づく、長く綿密なプロセスの物質的な結果(政治、経済、法律、デジタルなど)にすぎない」
ジャン・ジョセフ・ゴーム師 (1802 – 1879) は、1856 年に『革命:その起源およびヨーロッパにおける悪の伝播に関する、ルネッサンスから現代までの歴史的探求』という書を出版し、フランス革命が何であるかを次のように説明している。
「もしも革命の仮面を取り剥がして、革命に「おまえは誰だ?」と尋ねるなら、革命はこう言うでしょう。『私は、人々がそうであると信じているものではない。多くの人が私のことを話しているが、私のことを知る者はほとんどいない。私は、カルボナリ(秘密結社)主義でもなければ、暴動でもない。君主制から共和国への変更でもなければ、ある王朝から別の王朝への置き換えでも、公共秩序の一時的混乱でもない。ジャコバン派の叫び声でもなければ、山岳派の怒りでもなく、バリケードでの戦いでもなければ、略奪でもなく、放火でもなく、農地改革法でもなく、ギロチンでもなく、水責めの拷問でもない。私は、マラ(Marat)でもなく、ロビスピエール(Robespierre)でも、バブーフ(Babeuf)でも、マツッーニ(Mazzini)でも、コシュート(Kossuth)でもない。これらは、私の子供らであり、私ではない。これらは私の作品であり、私ではない。これらの人とこれらのことは、一時的な出来事であるが、私は永続する状態である。』『私は憎しみである。人間が確立しなかった全ての秩序、そこにおいて人間が同時に王と神ではない秩序に対する憎しみである。私は、神の権利を考慮しない人権宣言である。私は、神の御旨の代わりに、人間の意志の上に立つ宗教的かつ社会的状態の基礎である。私は、その王座から引きずり下ろされた神であり、その代わりに神の玉座についた人間である。これが私が革命、すなわち転覆と呼ばれる理由だ』と。」
革命とは、単なる暴力的な反乱やクーデター、政権交代ではない。もっと深く、もっと破壊的な精神としての革命である。それは破壊的宗教としての変化であり、すべての社会秩序を破壊したいという野望でもある。少子化、東京裁判史観による歴史教育、家族や中間共同体の破壊、道徳的・知的相対主義、戦闘心の喪失、名誉と犠牲という伝統的価値観の放棄、田舎の荒廃などに見られるように、現在の日本も以上の意味での革命の影響を受けている。
革命家自身が言うように、革命は決して終わらない。切りのない「進歩」のために、つねに人々を差別から解放しなければならないし、人々を変えなければならない。フランス革命に関する古典研究を欠いた法制史家フィリップ・ピショーは、次のように結論付けている。
「フランソワ・オランド大統領が 4 年後に教育大臣に任命することになるヴァンサン・ペイヨンが2008 年に強調したように、21 世紀初頭、フランス革命の人間を再生するプロジェクトは、燃えるような関連性を持っている。『フランス革命とは、時間に属さないものが時間に侵入することであり、絶対的な始まりであり、フランス国民の意味、再生、罪滅ぼしの存在であり、その計画の実現である。1789 年という他にはない年は、歴史の突然の飛躍によって新しい人間が創造された年であった。革命は超歴史的な出来事であり、言い換えれば宗教的な出来事である。革命は、それに先立つすべてのものの完全な忘却を意味する。学校は、子供を市民として育てるために、共和制以前の愛着をすべて取り除かなければならないからである。そして、新しい聖職者、新しい典礼、法律の表を持つこの新しい教会が、学校において、また学校を通して実現しようとしているのは、まさに新しい誕生であり、実体の転換なのである』。このような宗教的な色合いを強く帯びた数行が、『フランス革命は終わっていない』というタイトルがすべてを物語る本に印刷されている」
革命という宗教は日本にも侵入した。
II. 対策とは何か?
日本の保守派が戦わなければならない敵を知ることは必要である。孫子の兵法の「勝兵は先ず勝ちて、而る後に戦を求む」が述べるように、戦う前に勝つべきだが、そのために誰に対して戦うか知る必要がある。敵とは革命そのものである。共産主義、進歩主義、人権主義などはその子供に過ぎない。革命家たちは、革命思想の奴隷に過ぎない。
革命という敵がわかったら、どのような戦いをしなければならないのかも見えてくるはずである。
この良き保守的な戦いは一番良き対策であり、フランスの伝統主義者たちが「反革命」プログラムと呼ぶプログラムである。
反革命とは何か。反革命とは、以上のように理解されてきた革命に逆らうすべてのもの、言い換えれば破壊的精神として理解されている革命と戦うすべてのことである。
フランス革命と戦うために、革命を分析し、論じたフランス版の「孫子」とでも言うべきジョゼフ・ド・メーストルは、日本では知られていないが、18世紀のイギリスの政治思想家で「保守思想の父」と呼ばれるエドマンド・バークよりもさらに洞察力のある人物であり、次のように革命を定義する。
「反革命と(…)は、反対の革命ではなく、革命の反対である」(『フランスについての考察』第十一章より)。
つまり、反革命とはあらゆるものにおいて秩序を取り戻し、再構築し、革命とは正反対のことをするのである。人間の本性と歴史・伝統に沿った健全な秩序を維持・構築し、真の幸福を見出すために必要なこと、それは単純な物質的・動物的欲求の充足ではなく、アリストテレスや孔子がともに言ったように、正直な人間、善徳を実践する人間になることなのだ。
日本にも多くの先人たちが立ち上がって戦ったように、祖国を守るために戦った先人たちの常識に立ち返ることである。これを表現するために、革命期の時、革命政権と戦ったフランス人たちからなる反革命軍の指導者のひとりであり、ヴァンデ戦争の時に武装反革命の一人の指導家であり、勤王カトリック軍の将軍の一人であったシャレットの次の言葉を見よう。
「我々の祖国は、我々の村であり、我々の祭壇であり、我々の墓なのです。我々の祖国は我々の先祖が愛してきたすべてのことです。我々の祖国は我々の信仰であり、我々の故郷であり、我々の国王なのです。それに対して、彼ら(革命
家)の祖国なんのでしょうか。諸君、あなたはそれが分かるでしょう! 彼は慣習と秩序と伝統とを破壊しようとします。だから、過去を馬鹿にしている祖国なんて、忠誠の心のない祖国なんて、愛のない祖国なんて、一体どういった祖国なのでしょうか。無宗教と混乱の祖国でしょうか。彼らにとって、祖国は単なる概念に過ぎないようです。我々にとって祖国は故郷なのです。彼の祖国は頭の中にだけあります。我々にとって祖国は足の下にあるこの陸地なのです。彼らの祖国よりも本物でしっかりとしています! しかも、彼らは「新しい世界」などと言っていますが、天主なき世界など、悪魔のように古臭い世界にすぎません。彼らは、我々を「古くさい迷信の手先」だと非難していますが、それこそ笑ってやるべきことでしょう。むしろ、常に生まれ変わりながら現れる古い悪魔たちと戦ってきた我々こそが、本当の“青春”なのです。そうです、皆さん。我々は天主の青春であり、そして忠誠の青春なのです!」
結論
ではどうすればいいだろうか。革命と戦い、革命につながらない良き戦いはなんだろうか。どんなに厳しくても、健全な原理原則に立ち返ることである。戦前なら誉れ高き名声を得たであろうフランス王党派のもう一人の人物、シャルル・モーラスを引用しよう。
「皆様,改めて言っておこう。この本ではこれから厳しいことと発言することになるが、厳しいわりに,厳しい原則の応用は穏やかになることに注目していただきたいのである。また、書籍を読んで苦味を感じれば感じるほど、現実において安寧をもたらす効果があるのである。
人々には事情がいろいろあるからといって、原理原則が曖昧になっても大丈夫だろうと思うのは大きな間違いである。その逆である。原理原則を曖昧のままにするのならば,それぞれの事情を検討し分析することは非常に困難となり、これらの現象を整理することは至難の業となる。言い換えると、非常に多様な現象が存在するこの世界に、唯一、理性を照らしうる「原理原則」を曖昧にするならば、もう何ら考察はできなくなる。あたかもわざと天の太陽を雲で覆い隠し、この世界の複雑な事柄を見えないようにすることと似ている。真理というのは太陽と似ている。日差しは暑くて苦しいこともあるが、非常に明るいものである。このように真理というのは太陽のように高いところからこの世の出来事に光を浴びせている。つまり,そもそも,我々が行動する前に、知るべきことと考えるべきことを示してくれている。即ち,真理というのは善を奨励し、悪を戒めて、この世に存在する限りなく多くの事柄について善悪を意識し区別することを助けてくれる。もちろんこのように真理に照らしただけでは、人間の世界に起こる多くの具体的な問題がすぐに解決されるようなことはない。しかしながら、これらの問題を本気で解決しようと思ったら、真理に照らすことで初めて解決が可能となる。また、時にはなぜか悪と弊害ばかりが目の前に現れてくるようなときでも,真理の光のおかげで一番弊害の少ない方向を選ぶことも可能となる。即ち、真理に照らせば、最悪のことを避けるような方向で努力することが可能となる。このように考えれば、(真理に照らすことは)最悪を避けることや,自分自身を統治すること、または,他人を統治するにあたっても、政治上一番肝心な点であるかもしれない」
当時の三島由紀夫は「反革命宣言」を行い、共産主義者の暴力革命と闘うことを呼びかけた。『文化防衛論』(ちくま文庫)によると、この宣言は次のようにはじまる。 「われわれはあらゆる革命に反対する者ではない」。しかし、私たちはこう宣言する必要があると確信する。
「われわれはあらゆる革命に反対する者でなければならない」
本稿は全体像を示したに過ぎず、各自でさらにそれぞれのテーマを掘り下げていただく必要がある。その目的は、私たちが戦っている戦いの鍵を提供することであり、それは近現代の歴史をあらゆる側面から正しく理解することでしか見いだせない。日本には確かに特有の戦いがあるが、闘いの核心は変わらない。革命ひいては近代に対する闘いであり、それは全体的かつ全般的な革命であり、今日ではほとんどが非暴力であるので、家族、社会、人間関係を破壊するこの革命をより深く理解し、「反革命」思想を学び、本格的な伝統主義を実践する必要がある。


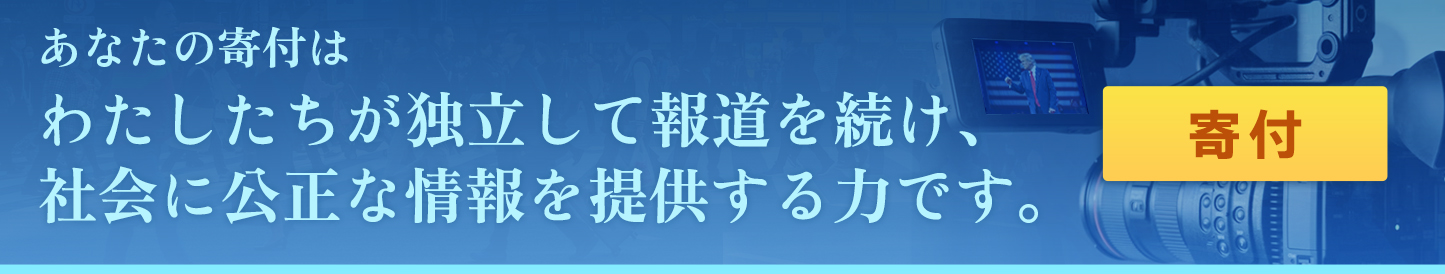












 ご友人は無料で閲覧できます
ご友人は無料で閲覧できます Line
Line Telegram
Telegram














ご利用上の不明点は ヘルプセンター にお問い合わせください。