友人から、ある有名ファッションブランドの最新メンズコレクションの写真が送られてきた。
私はそれが男性のものであることを確信していた。なぜなら、友人はわざと私を騙すようなことはしないからだ。しかし、私には、その服を着たモデルが重度の拒食症の女性にしか見えなかった。まるで残虐な政権が運営する強制収容所から集められたかのようだ。
メンズウェアの意図的なフェミニン化について、デザイナーは今回のコレクションを通じて「ジェンダーの固定観念と戦いたい」と主張していた。旧ソ連の独裁者スターリンはかつて、(殺したり追放したりしなかった)作家を「人間の魂の技術者」と呼んだ。これらのデザイナーも、その称号にふさわしい。
ファッションデザイナーにとって、アイデアは服と同じくらい重要なものになっている。この点では、建築家と似ている。建築家はもはや単なる建物の設計者ではなく、ソーシャル・エンジニア(詐欺師)としての役割も果たしている。
実際、その背後にある左翼イデオロギーは社会のあらゆる分野に浸透しており、その影響を受けない職業はほとんどない。近い将来、雇用主は、「多様性」や「平等」などへの取り組みを約束しなければならず、求職者もこれらの価値観を信奉することが求められる。この病的な「倫理観」から逃れることができるのは、自営業者だけである。
しかし、話をファッションショーに戻すと、私にとっては全くのミステリーである。前述の最新コレクションでは、モデルがオートマタ(自動人形)のようにキャットウォークを歩き回り、観客は暗闇の中でそれを見守っていた。
モデルたちは、北朝鮮の軍事パレードの兵士のように人間味のない無表情で、仮面のように動かず、まっすぐに前を見つめている。キャットウォークの曲がり角では、ロボットのように通り過ぎていく。
彼らの幽霊のような顔が何かを表現しているとすれば、それは悪意に満ちた嫌みであり、世界に対する憎しみでさえあり、デフォルト値として植え付けられた強い嫌悪感である。
実に奇妙なことだ。ファッションデザイナーの仕事は、楽しさと喜びに満ちていると思われるだろう。これらのモデルを見ていると、私がパリに滞在していたとき、滞在先の街をひたすらジョギングしていた青年を思い出した。彼はライクラを着た骸骨のようで、見るに堪えなかった。フランスの作家、ラ・ロシュフコーの言葉にあるように、「太陽も死も直視できない」。
しばらく見かけていなかったので、引っ越したかあるいは死んだかのどちらかだろう。痩せすぎは太りすぎと同様に健康に悪いということを忘れがちだが、ファッションモデルたちは死にかけているに違いない。
モデルになるための競争は非常に激しく、ガリガリに骨ばった、男か女かわからないほどの飢えた姿は、今や男性モデルの審査通過の条件となっているようだ。ファッションデザイナーは、モデルの健康を永久に悪影響を及ぼすようなライフスタイルを意図的に奨励している。子供が去年のクリスマスプレゼントを捨てるように、彼らはこれらのモデルをすぐに捨ててしまう。
このような搾取されることを選ぶ人がいることが不思議である。これは、フランスの人文学者で法官のエティエンヌ・ド・ラ・ボエシが「自発的な隷従」と呼んだケースである。しかも、ほとんどの人はあまり稼げず、有名になる人もごくわずかで、当選確率が非常に低い宝くじのようなものだ。
私は想像力に欠けているせいか、外見を唯一の財産とする人たち(成功しようとする意志は別として)には共感できない。少なくとも現代のファッション界では、成功の鍵は特別な魅力や個性ではないようだ。というのも、私の目には、モデルたちは見た目の微妙な違い以外に、ほとんど見分けがつかないからだ。
人と人との違い、個性こそが人間らしさを生み出しているのである。しかし、この業界は、些細だが重要な点において、全体主義体制の恐ろしさを内包している。
供給側はそうだが、需要側はどうだろうか?ファッションハウスの多くは大成功を収めた大手企業であるため、顧客が何を好むかを知っているはずだ。また、トレンドを作りたいと思っても、それが顧客にとって魅力的かどうかを知っているはずだ。
誤解を恐れずに言えば、ファッションショーはヴィクトリア朝時代の見世物小屋に相当するものになっている。そこでは、奇形に生まれた人々が、お金儲けのために、その身体的奇形を利用し、好色で下品な人々を喜ばせていた。
完全にマルクス主義に起因するものではないとしても、このファッションショーには経済的な関連性があるはずだが、それは間接的なものに過ぎない。仮装パーティーでもない限り、ショーで発表された服を実際に着る人はまずいないだろう。
どんなに高い値段をつけても、儲かるほど売れるとは思えない。というのも、パンクロッカーが保守的な紳士に見えるようなジェンダーダイバーシティの時代になっても、こんなに変な格好をしている人を見たことがないからだ。
このショーは宣伝のために行われたのかもしれない。たとえ宣伝のためとはいえ、企業に何らかの経済的利益をもたらすものでなければならない。そうでなければ、経営者はきちんと仕事をしていないことになる。
もちろん、後者の可能性もある。経営者は他の人と同様に、しばしば自分の仕事をきちんこなせないことがよくある。この場合、ジェンダーニュートラルの波に乗ることで、若くて裕福で教育を受けた「性に目覚めた」顧客の心をつかみ、自社製品の購入を促すことを計算しているのかもしれない。
私の考えが正しければ、これは何か不吉なことを反映しているように思える。つまり、彼らの顧客は愚かな左翼イデオロギーを信じるようにうまく洗脳されているので、ファッションショーで歩き回っているか弱い若いモデルが受けた恐ろしい搾取や、彼らが着ている服の醜さを認識することすらできないのだ。
執筆者プロフィール
セオドア・ダレンプル(Theodore Dalrymple)は、元医師。保守系の政策情報誌『City Journal of New York』の寄稿編集者であり、『Life at the Bottom(どん底の生活)』をはじめとする30冊の著書がある。最新作は 『Embargo and Other Stories(エンバーゴとその他の物語)』。
オリジナル記事:「The Sinister and Ugly Sides of Fashion Shows」より
(翻訳・王君宜)


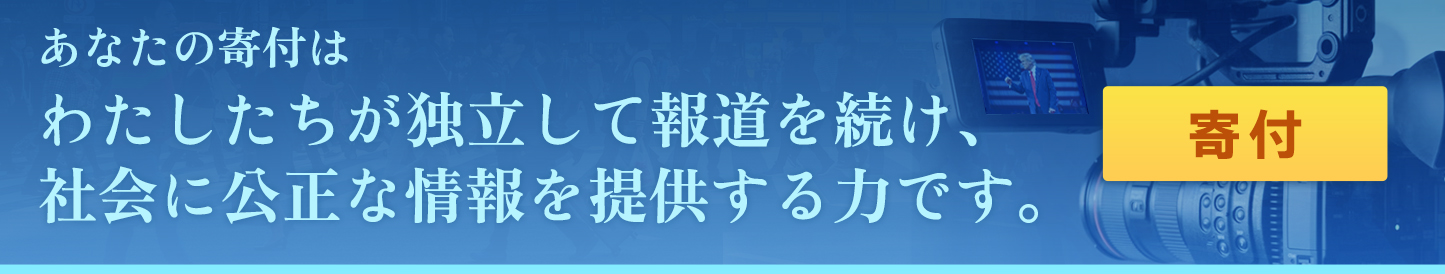












 ご友人は無料で閲覧できます
ご友人は無料で閲覧できます Line
Line Telegram
Telegram














ご利用上の不明点は ヘルプセンター にお問い合わせください。