今から1年ちかく前のことである。中国民衆の示威活動である「白紙革命」や「花火革命」の先駆けとなった、2022年10月13日の北京「四通橋事件」から、およそ数か月後だった。
2023年2月21日午後8時過ぎ、山東省済南市の繁華街にある高層の建物「ワンダ・プラザ」の北側の壁面に「共産党を倒せ、習近平を倒せ(打倒共産党,打倒習近平)」と書かれた赤地に白文字の電子横断幕が現れた。
それは遠方の別の建物から角度をぴたりと合わせて、狙撃の名手のように投影された10文字であった。
ビルの壁に浮かんだ「共産党を倒せ!」
中国共産党とその首魁・習近平の鼻先に「打倒」のナイフを突きつけた、度肝を抜くパフォーマンスである。
その文字は、多くの市民を驚かせ、大いに共感させたであろう。それとともに、現地である済南市の公安警察には、ほとんど発狂させるほどの衝撃を与えた。
なぜならば、その地域を所管する警察にとって、ビルの壁に「打倒共産党,打倒習近平」が投影されたことは、背筋も凍るようなペナルティを招く大失態に他ならないからだ。
中共の息の根を止めるその10文字の投影は、いったい誰が、どのようにして実現したのか。
それは、練りに練った計画と綿密な準備の上で、なんと海外からの遠隔操作によって投影されたものだった。
昨年撮影されたその現場を映した画像や動画が最近になって流出し、いま華人圏では、多くのネットユーザーやインフルエンサーによって「猛拡散」されている。
この件をめぐり、米国で民主運動を続ける組織「人道主義中国」の代表・周鋒鎖氏は、自身のSNSで以下のように評した。
「これは四通橋の勇士と同様の、偉大な壮挙だ。中共によるハイテク監視のなかで成し遂げたこの遠隔投影による抗議は、創造的な抗議が実行可能であることを証明した。綿密な計画によって、中共による逮捕から完全に逃げ切った、良い見本だ」
もう一人の「彭載舟」:柴松氏
この壮大な抗議活動を計画・実行したのは、体制に異議を唱える活動家の柴松(さいしょう)氏だ。柴氏は現在、中国を離れて米国にいる。米国への入国は、密入国だった。
「重要なのは、継続的に声を上げ続けることだ」。米国に渡って1年近くになる柴氏は、そう話す。
柴松氏は河北省出身。長年北京や山東省で商売をしてきた柴氏は、主に不動産賃貸業に携わってきた。しかし、3年にわたるゼロコロナ政策に伴う都市封鎖などで、柴氏のビジネスは大打撃を受け、多額の損失を出した。
「(ゼロコロナの頃)北京市が、市外から来る全ての人を拒む光景を目撃した。重症で死にそうな患者が北京市内の病院に向かっていても(封鎖措置によって)高速道路から降りることが許されなかった」
「新疆ウルムチでの火災など、都市封鎖による悲劇があった。ゼロコロナ政策の突然の終了(2022年12月7日)で、人々は何の準備もないまま次々と感染した。医療資源は完全に麻痺した。薬が手に入らず、亡くなった人も大勢いる」
柴氏は、中共当局が2020年から22年12月まで、約3年にわたって実行してきたゼロコロナ(清零)政策に対して「心底からの不満」を抱えていたという。
その頃、よくファイヤーウォールのネット検閲を突破して、ボイス・オブ・アメリカ(VOA)や新唐人テレビ、大紀元エポックタイムズ、ウォールストリートジャーナルなど海外メディアのニュースを見ていたという。
そして柴氏は「(彭載舟氏の)四通橋事件からヒントを得た」と語る。その「四通橋の勇士」である彭載舟氏にならって、柴氏は2022年末から、自身が抗議する「極秘計画」を練り始めた。
入念なテストと「監視カメラ」も設置
「共産党を倒せ、習近平を倒せ(打倒共産党,打倒習近平)」の投影は、ほんの一瞬である。実際に投影できたのは、警察が飛んでくるまでの10数分間ほどであっただろう。
しかし、その10数分のために、柴氏は1か月近くかけて準備をしていたのだ。
まずは、抗議スローガンを投影するのに適した位置の「部屋」を借りることから始め、そこから「スクリーン」となる遠方のビルの壁に投影するテストをした。
もちろん「共産党を倒せ」の文字でテストすることはできない。テストの際、代わりに使ったのは「食品の宣伝コピー」だったという。
借りた部屋からの角度や距離、投影効果を精密に調整した。次に、投影に使うプロジェクター内部のレンズを交換しなければならない。レンズに直接彫って、印字するのである。
そのため、レーザー彫刻機も購入して「打倒共産党,打倒習近平(共産党を倒せ、習近平を倒せ)」の言葉を、自分でレンズに彫ったという。最後に、携帯電話からの遠隔操作によって投影を開始するための起動装置も取り付けた。
また念のため、部屋のなかに誰かが侵入していないかを随時チェックできるよう、監視カメラも設置したという。こちらの計画を警察に察知されれば、柴氏自身にとって一巻の終わりである。もちろん逮捕されれば、命の保証はない。
ついに行動開始「さらば中国よ」
柴松氏は、国外へ逃亡する前提で、この計画を進めている。
投影を行うための準備が全て整った後、ゼロコロナ終了後である2023年1月初め、柴氏はすぐに中国を出ることを決意した。
中共政府はゼロコロナ終了直後のこの時には、海外からの観光客やビジネスマンが中国へ戻ってくるよう入国の門戸を広げるとともに、中国国民が出国する制限も若干ゆるめていた。
柴氏は「本来ならば、旧正月を家族と過ごしてから中国を離れるべきだった。しかし(中共政府が)渡航や出国政策を再び調整して、私が出国できなくなる懸念もあった。さらには、この3年間で溜め込んだ私の怒りと(中共への)失望感が一気に込み上げてきて、すぐに国を出ることにした」という。
中共当局による厳しいゼロコロナの封鎖政策により、民衆には普遍的な不満があった。そのため柴氏の秘密計画は、心を許せる友人とも共有していたという。
全ての準備を終えた柴氏は2023年1月18日、マカオから中国を出て、タイに渡った。それからトルコに飛び、南米のエクアドルに向かった。
「地球を半周」遠隔操作は大成功
投影のタイミングについては「2023年2月26日から28日の第20回2中全会において、習近平氏が国家主席に再選される見込み」というニュースを見て、柴氏は「2中全会」の前に投影開始することを決めた。
それは、柴氏が中国を離れて1か月余りが過ぎた2月21日午後8時(北京時間)であった。中米パナマのダビッドにあるホテルのなかで、柴氏は携帯電話を使い、遠隔投影装置のスイッチを入れた。
すると、はるか遠く、なんと地球を半周して、中国の山東省済南市の「ワンダ・プラザ」の壁に「共産党を倒せ、習近平を倒せ(打倒共産党,打倒習近平)」の文字が見事に投影されたのである。計画は、大成功だった。

投影された巨大な文字は、夜の闇の中でひときわ目を引き、道行く済南市民の間でたちまち話題となった。
投影された場所は柴松氏がとくに選んだ場所で、人通りが多く、大勢の市民がその光景を目撃することになった。
「打倒共産党、打倒習近平」
たった2行のスローガンだが、それが中国の民衆に与えた衝撃は計り知れない。
このスローガンは、人々の政治的要求を集約するとともに、人々の心の中にある恐怖を払拭するものであった。「中共を恐れない民衆」の出現を、中共は最も恐れるのである。
現場で待機していた柴氏の友人は、すぐにその様子を撮影して、中米パナマにいる柴氏に送信した。
投影が始まってまもなく、大勢のパトカーが轟音を立てて「事件現場」に駆け付けた。当局は約100人の警察を動員して、ビルに映ったスローガンを撮影していた市民を拘束するなど、大がかりな対応を行った。
また、国安、武装警察、警察、省庁、市役所など多くの部門からなる「特別チーム」を立ち上げて、柴松氏の逮捕に向かった。もちろん柴氏はこの時、国外にいる。
投影されてから約1時間後、柴氏の友人宅には警察関係の当局者70人以上が押しかけ、2人の友人を「共犯者」とみて逮捕した。柴氏の父親のところにも、大勢の当局者が行ったという。
そのとき中米パナマにいる柴氏は「友人や家族に連絡ウィーチャットで連絡したが、誰も返事してくれない。きっと捕まったんだ」と悟った。
柴氏はダビッドのホテルを出て、引き続き「北」を目指した。目的地は米国である。
決死の逃避行、血眼になる中国警察
その後、柴氏によると「両親は、1週間にわたって取り調べを受けた。私が帰国するよう、当局は両親から説得するよう求めた。私の全ての銀行口座は凍結された。親戚にも、柴松には送金するな、と当局が命じた。警察は、私の出身小学校にまで駆けつけて調査をした。とにかく、私が生まれてから現在までのことを洗いざらい調査したようだ。私の2人の友人や私の恋人は逮捕されて、今も連絡が取れない」という。
「私を逮捕しに来るだろうというのは分かっていた。ただ私も、私の友人たちも、まさか当局がここまで大掛かりにやるとは思わなかった」という柴松氏。財産を凍結された後、一時は、食料すら買えない無一文状態になったという。
柴氏は、メキシコでベネズエラ人の友人と命がけで走行中の列車に飛び乗り、米国へ密入国した。
柴氏は「メキシコでは危うく死にかけた。もしメキシコの移民局に捕まっていたら、中国に強制送還されていただろう。米国に入国する時、米国の国土安全保障省やFBI(連邦捜査局)の人から、中共警察が君を越境逮捕しようとしているよ、と聞いた」という。

密入国ではあるが、ともかく渡米して、まもなく1年になる。柴氏は長く悩んだ末、この件について海外メディアに暴露することに決めた。
柴氏がそれまで苦悩したという最大の理由は、もちろん自身の行動に関係して友人や恋人が中国警察に逮捕されており、彼らの安全が懸念されるからだ。
「中国共産党に反対している中国人は多い。ただ、みんな自身の安全のことを考えて、行動する勇気がないだけだ。だから、捕まらないようにできれば、中国国内で抗議の波が起こる。重要なのは、継続的に声を上げ続けることだ」と柴氏は話した。
それでも、なぜ抗議をするのか
「なぜ、あなたは中共に抗議するのか?」。海外メディア(VOA)にそう尋ねられた柴松氏は「世界を驚かせた四通橋事件の影響を受けたから」と話す。
「四通橋事件」とは、2022年10月13日の正午ごろ、北京市内の陸橋「四通橋」の上に、中共の政権を真っ向から批判するとともに、その最高権力者である現国家主席・習近平に対して「独裁の国賊、習近平を罷免せよ!(罢免独裁国贼习近平!)」と名指しで罵倒する横断幕が掲げられた事件だ。

当時は「ゼロコロナ(清零)政策」中であったため、スローガンには「PCR検査は要らぬ、食べ物が欲しい。封鎖は要らぬ、自由が欲しい」の文言があった。
さらに「嘘は要らぬ、尊厳が欲しい。文革は要らぬ、改革が欲しい。独裁者は要らぬ、選挙権が欲しい。奴隷になるのは嫌だ 、公民でありたい」と書かれていた。
この「四通橋事件」は、その後に続く中国民衆の示威活動である「白紙革命」や「花火革命」の先駆けとなった。中共当局に与えた衝撃の大きさは、この「四通桥(四通橋)」という何の変哲もない地名が、中国のネット上で検索不能になったことからも伺われる。
「四通橋」の上に横断幕を掲げたのは彭載舟(ほうさいしゅう)氏(本名・彭立發)である。彭氏は「四通橋の勇士」と呼ばれ、以来、中共の暴政に立ち向かう人々の象徴的存在となった。

その場で警察に取り押さえられた彭氏は、当局に連行されて以来、外界との接触を一切断たれ、その安否もふくめて現在も所在は分からない。彭氏の妻子は郷里で軟禁されている。彭氏の姉まで失踪して、行方不明の状態だという。
「四通橋事件が体現しているのは、その精神だ」と柴松氏はいう。
確かに、彭載舟氏は政府批判の横断幕を掲げたが、その場ですぐに逮捕されてしまった。陸橋に掲げた手書きの横断幕が、中共政権を脅かすほどの力をもっていたわけではない。しかし、柴氏は言う。
「彭載舟氏は、自分が何をしているのか知っていた。そして、それをしたことで直面する結果についても分かっていた。それでも彼は、中国の改革のために自分の命を差し出してもいいと覚悟をして決行した」
「この精神に、私は多大なる影響を受けた。彭載舟氏がスローガンに書いた文字が何であるかは重要ではない。死をも恐れず強権に立ち向かう彼の精神こそが尊いのだ」
「中共による政治や国家など、なくていい」
長い苦難の旅を経て、ようやく自由な米国まで辿り着いた柴松氏。今年1月、台湾総統選挙の期間中、米ロサンゼルスの中国領事館前で行われた抗議活動に、彼の姿があった。
そこで柴氏は「中共には完全に失望した。私を最終的に目覚めさせたのは、中共の重大な公的政策のミスだ」として、次のように語った。
「中国共産党による(ゼロコロナ政策などの)政策は、その政府の全てが非効率的で巨大なマシーンであることを浮き彫りにした。中共の出発点は、人命を第一に考えることではなく、常に政権の安定維持を第一にすることだ」
「その点は、私の価値観と相反する。どれほど多くの国民の命が失われようと、中共は国民に対して何の憐憫もない。それならば、中共による政治や国家など、なくてもいいと私は思った」



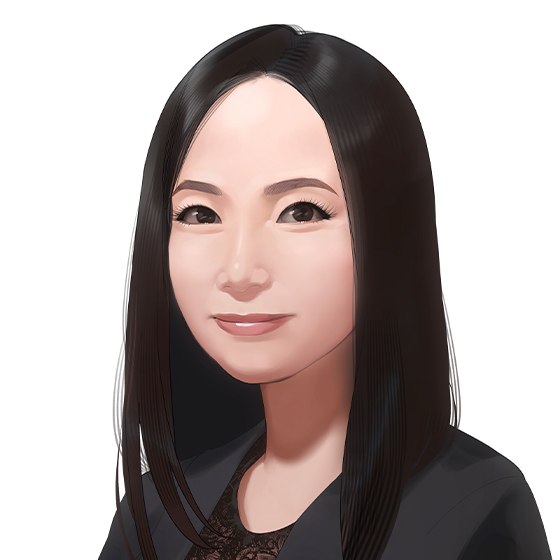

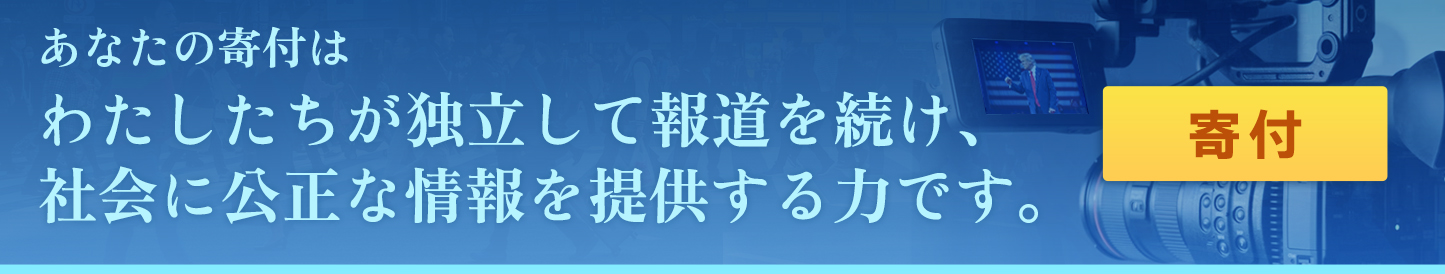












 ご友人は無料で閲覧できます
ご友人は無料で閲覧できます Line
Line Telegram
Telegram














ご利用上の不明点は ヘルプセンター にお問い合わせください。