経団連の十倉雅和会長は2025年2月25日の定例記者会見で、経済界の代表団として中国を訪問した成果について語った。十倉会長は、この訪問を通じて「建設的で安定的な日中関係をつくるために意見交換できた」と評価し、その意義を強調した。
代表団は今月、北京で何立峰副首相や王文濤商務相と会談を行い、レアメタル(希少金属)などの輸出規制の自制を中国側に要請した。これに対し中国側は、「輸出管理であって禁止ではない。安全保障上問題なければ輸出する。迷惑はかけない」と回答したという。
十倉会長は中国側の対応について、「非常にまじめな受け答えをしてくれた」と評価した。しかし、外資企業の安全なビジネス環境の整備を求めたことなどに関しては、「必ずしも満足いく答えばかりではなかった」と振り返り、経済交流の推進に課題が残されたことを認めた。
一方で、中国側は自国経済の先行きに強い自信を示した。何副総理は会談で、中国が質の高い発展に向けて取り組んでいると述べ、約5億人の中産階級の消費増加に伴う国内市場の拡大が周辺諸国にも好影響を及ぼしているという見解を示したという。
中国共産党のプロパガンダ
しかし、中国経済の実態は、中国共産党(中共)政権が示す強い自信とは対照的であることが指摘されている。2025年の新年を迎えた際、中共の機関紙は習近平の講話を発表し、「東昇西降」(東が昇り、西が降る)の観点を再確認したが、専門家はこれを国内向けのプロパガンダだと指摘している。
台湾大学の陳世民副教授は、「今は明らかに東が昇り西が沈むという状況ではなく、中国は徐々に、アメリカや西洋を超える可能性はもはやないと感じさせる状況になっている。ここ2、3年の中国の経済と社会の状況は、明らかに衰退していることがわかる。習近平の統治の下で、経済はますます大きな問題を抱えている」と指摘している。
実際、中国経済は深刻な課題に直面している。大和総研の予測によると、2025年の中国の実質GDP成長率は4.5%程度まで低下する見込みであり、これは政府目標を下回る水準である。さらに、不動産不況の長期化、人口減少と少子高齢化の急速な進展、過剰投資と投資効率の低下、過剰債務問題などの構造的な要因が中国の成長力を低下させている。
アメリカのセント・トーマス大学の葉耀元教授は、多くの専門家や学者が「東昇西降」という考えを信じていないと指摘している。葉氏は、「習近平の現在の状況を考えると、彼には他に選択肢がない。国内経済の内部競争が非常に深刻であることや、経済が崩壊する可能性を認める必要があると言っても、彼はその言葉を口にすることはできない。なぜなら、もし彼がそれを言ってしまったら、責任を負わなければならなくなるからだ」と述べている。
さらに、カナダの中国系作家、盛雪氏は、習近平がこの誤った見方に固執し続けることで、中共はさらに衰退すると警告している。盛氏は、「中共の抱える問題は、今や単なる経済衰退ではなく、この経済衰退は全体の体制に影響を及ぼしており、多くの調整ができず、互いに協力し続けることができない深刻な困難が生じている。この困難は習近平には解決できない」と指摘している。
このように、経団連代表団の訪中は日中間の経済関係の重要性を再確認する機会となったように伝えている一方で、専門家が伝える中国経済の実態は中共政権の主張とは大きく乖離しており、習近平が直面する課題の深刻さが浮き彫りになっている。中国経済の今後の展開と、それが日中関係に及ぼす影響が注目される。


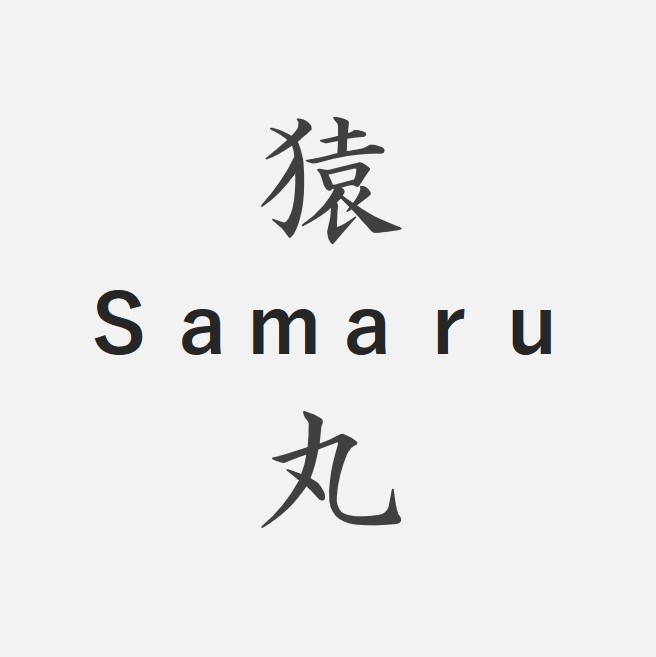













 ご友人は無料で閲覧できます
ご友人は無料で閲覧できます Line
Line Telegram
Telegram














ご利用上の不明点は ヘルプセンター にお問い合わせください。