米ホワイトハウスは6月4日、ハーバード大学に関連する国家安全保障上のリスクに対応する新たな大統領布告「ハーバード大学におけるリスクへの対応による国家安全保障の強化」を発表した。今回の布告では、特に中国共産党との関係に焦点が当てられている。
布告およびホワイトハウスの発表資料によると、ハーバード大学は過去10年間で中国から1億5,000万ドル以上の資金提供を受けており、同大学が中国共産党の中堅および高級官僚を多数受け入れてきたことが指摘されている。米下院中国共産党特別委員会の調査によれば、ハーバード大学は中国共産党の準軍事組織のメンバーを繰り返し受け入れ、訓練してきたともされる。
また、ハーバード大学の研究者が中国拠点の研究者と共同で、中国の軍事近代化に資する可能性のある研究を行っていたことも問題視されている。中国共産党の幹部がハーバード大学で研修を受けるプログラムが2000年代から存在し、習近平国家主席の娘も2010年代初頭に同大学に在籍していたと複数の報道が伝えている。
トランプ政権はこうした状況を「ハーバード大学が外国の敵対勢力、特に中国共産党と広範な関係を築いている」と強く批判。中国共産党と関係が深い中国人留学生や、重要分野の研究に従事する学生のビザ取り消しや、ビザ審査の厳格化を進める方針を明らかにした。
さらに、ハーバード大学に対する連邦助成金の凍結や研究委託契約の打ち切りといった経済的措置も実施されており、大学側には外国との共同研究や資金提供の透明性向上、厳格な管理が強く求められている。
今回の布告は、ハーバード大学をはじめとする米国の高等教育機関が中国共産党との関係を通じて国家安全保障上のリスクにさらされているとの認識に基づき、米政府が対策を一層強化する姿勢を鮮明にしたものだ。
大統領布告までの経緯
トランプ政権が6月4日に大統領布告を発表するまでには、いくつかの段階的な経緯があった。
まず、政権は2025年春以降、ハーバード大学に対して厳しい姿勢を強めていた。背景には、大学が「キャンパスの安全確保を怠っている」「外国勢力から多額の資金提供を受けている」「敵対国の関係者を受け入れ共同研究をしている」といった問題意識があった。特に中国共産党との関係や中国人留学生の存在が、国家安全保障上のリスクと見なされた。また、ハーバード大学が「過激な留学生」を放置していることも問題視された。こうした流れの中で、政権は4月から5月にかけて、ハーバード大学への連邦研究資金や助成金の凍結、研究委託契約の打ち切りなど、段階的に圧力を強めていった。
さらに、5月22日には国土安全保障省がハーバード大学の留学生受け入れ認定資格を取り消す通達を出し、全世界の米大使館・領事館に対して留学希望者のビザ面接の新規受付停止を指示した。これに対し、ハーバード大学は法的措置で対抗し、ボストンの連邦地裁が一時的な差し止め命令を出すなど、政権と大学の対立は激化していった。
また、政権は「反ユダヤ主義」や「DEI(多様性・平等性・包括性)」の排除も本音として掲げており、大学の教育内容や人事政策にも介入しようとした。しかし、こうした措置が裁判所によって差し止められる事態も発生したため、トランプ大統領は議会の承認を必要としない大統領布告という形で、改めて中国人を中心とした留学生の入国制限やビザ取り消しなど、より直接的な措置に踏み切った。
このように、ハーバード大学と中国共産党との関係や学内の多様性政策、反ユダヤ主義問題など複数の要素が絡み合い、連邦資金の凍結やビザ制限などの圧力を経て、最終的に6月4日の大統領布告発表に至った。
日本政府・大学の対応
米国の急激な政策転換を受け、日本政府および国内大学は迅速な対応を見せている。あべ俊子文部科学相は5月27日の記者会見で、国内の大学に対し、米国の大学に在籍または留学予定の学生の受け入れや支援策の検討を要請していると述べた。これを受けて、日本学生支援機構(JASSO)は6月6日現在、全国87大学が支援策を決定し、さらに5大学が検討中であると発表した。
代表的な大学としては、東京大学、京都大学、東北大学、北海道大学、九州大学、神戸大学、上智大学、埼玉大学、東京科学大学、東京理科大学などが挙げられる。受け入れ対象については、ほとんどの大学が「米国の大学に在籍し、受け入れ停止などで学業継続が困難となった学生」としており、国籍で限定していない。つまり、日本人留学生だけでなく、米国に留学していた中国人留学生やその他の国籍の学生も対象に含まれている。
日本の安全保障上の懸念
米国が安全保障上の理由でハーバード大学の留学生受け入れ資格を停止したことを受け、日本では学びの継続を支援するため、日本政府と国内大学による受け入れが進められている。
しかし、最大の懸念は、米国が問題視した安全保障上のリスクが日本にも波及する可能性である。米国では、特に中国籍の学生・研究者による機微技術の窃取や軍事転用可能な研究成果の流出、さらにはスパイ行為が深刻な問題として取り上げられてきた。
これらの背景を踏まえ、日本国内でも「米国で排除された学生や研究者を無条件で受け入れることは、同様のリスクを日本が背負うことになる」可能性について、議論の活発化が期待される。


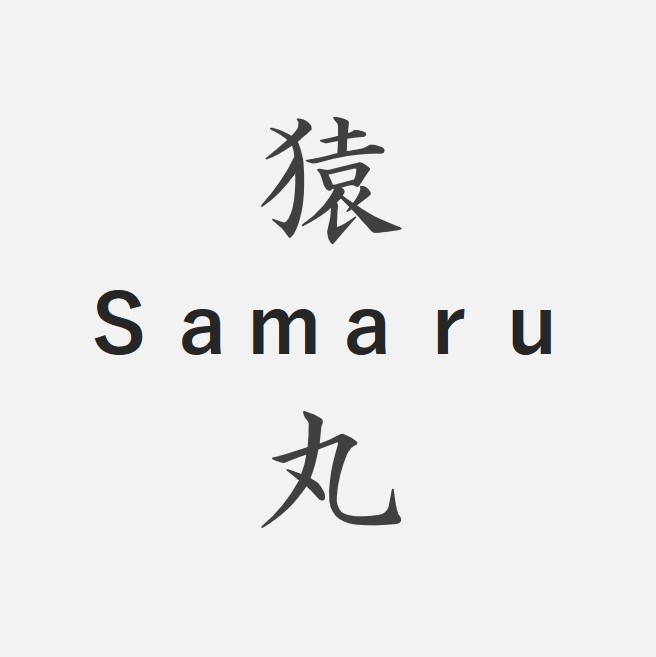













 ご友人は無料で閲覧できます
ご友人は無料で閲覧できます Line
Line Telegram
Telegram














ご利用上の不明点は ヘルプセンター にお問い合わせください。