6月23~30日に開催された第112回日本水彩画展において、台湾の風景を鮮やかに描き続けた画家・陳榮和(1928〜2005)の作品が12回目となる出展を果たした。1970年代に11年連続で入選を果たした彼の再出展は、台湾の文化的アイデンティティを日本に伝え、日台の美術交流史に新たな光を投じる。
今回の展示は、陳氏の娘さんが日本水彩画会に対し、父親がかつて出展した際の資料や写真を問い合わせたことに端を発した。同会は歴史的な画集をスキャンし、陳榮和氏の入選記録や、同時期に入選した画家たちの作品リストを提供してくれた。1970年代の美術活動をたどる貴重な史料となり、陳氏の功績を再評価する契機となった。
日本統治下の台湾・屏東に生まれ、台湾師範大学美術系第一期生として水彩画で首席卒業した陳氏は、画家としてだけでなく、屏東女子中学校や台北市士林商業高等学校で美術教師を務めたほか、日本ぺんてる(Pentel)美術文具用品の台湾市場開拓にも尽力。Pentelでは水彩やパステルなどの画材を台湾に紹介し、台湾における初期の美術用品の充実や美術情報の普及に大きく貢献した。
国際孤立下での文化的発信
1970年代、台湾が国際的に孤立していた時代、陳氏は日本水彩画会展で一貫して「台湾の風景」を描いた。屏東の椰林、台南の旧市街、基隆港、淡水河など、静物画や人物画をあえて捨て、イギリス式の透明水彩技法と明るい色彩を採り入れた作風は、高く評価された。1973年の展評では「堅実な素描と現代的感覚に富む色彩が好評」と記され、国際舞台での台湾の存在を証明する文化的意思表明となった。
今回展示された作品は、台南・安平の古厝(歴史的遺跡)を描いたものである。台南は、「一府二鹿三艋舺(台湾は台南(一府)、鹿港(二鹿)、艋舺(三艋舺)の順に栄えた)」という言葉にある「一府」にあたる場所で、台湾の発祥の地とも言われている。府」は台南府城、すなわち台南の旧市街地を指している。
安平に見られる椰子の木は、日本本土にはほとんど存在せず、沖縄の一部に限られる。まさに台湾固有の風土を象徴するモチーフである。
娘さんは「父は台湾という土地とそこに生きる人々に深い愛情を抱いていた」と語った。陳氏は壮大な自然や歴史的建造物だけでなく、市場、屋台、路地裏、工場といった庶民の生活を積極的に描いた。絵筆を通して、沈鬱な日常も多彩な表情を持って映し出し、見る者の心を捉えた。
また、陳氏が好んだのは、高層ビルと低層住宅が共存する都市の風景である。これらの風景は台湾人の努力によって成し遂げられた現代化の記録であり、都市と農村の融合を描く象徴でもあった。芸術評論では「陳榮和は生涯にわたり60年以上水彩画の創作を貫き、台湾各地の片隅を賛美すべき『壮大な風土』として描き出した」とも評されている。
試練と創作の持続
陳氏の人生は平坦ではなかった。長女を若くして亡くし、深い悲しみから約14年間(1979年の初個展から1993年の2度目の個展まで)画壇に姿をほとんど見せなかった。この間、必要最低限の仕事に取り組み、絵画に没頭することで心を癒した。台南の旧市街を描いた『夕暮れの古街』(1980年代)は、静かな哀愁と温もりを湛え、観る者の心を打つ。娘さんは「父は水彩画を心から愛し、どんな試練にも絵筆を置かなかった。その持続が、60年以上にわたる創作の原動力だった」と振り返る。
日台美術交流の未来へ
台北駐日経済文化代表処台湾文化センターの曽鈐龍センター長は本展を訪れ、次のように語った。「陳氏の作品は、台湾の風景と人文を見事に融合し、当時の文化や風情を後世に伝えます。私たちの使命は、こうした芸術を通じて台湾の芸術家を日本に紹介し、日台の文化交流を深めることです」
陳榮和の再出展は、過去と現在をつなぐ架け橋となり、台湾の文化的アイデンティティを日本に再認識させる契機となった。作品は台北市立美術館や高雄市立美術館、日本丸紅商社などに収蔵され、台湾の風土を後世に伝えている。台湾文化センターは、陳氏のような芸術家の紹介を通じて、日台の絆をさらに強化し、相互理解の新たな地平を切り開くことが期待される。


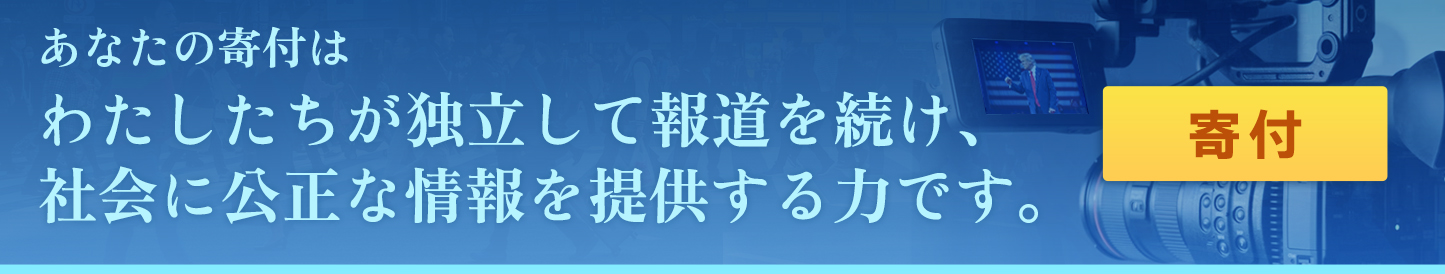












 ご友人は無料で閲覧できます
ご友人は無料で閲覧できます Line
Line Telegram
Telegram














ご利用上の不明点は ヘルプセンター にお問い合わせください。