トランプ米大統領の次男、エリック・トランプ氏が出版した新著『包囲の中で――わが家族の祖国を守る戦い(原題:Under Siege: My Family’s Fight to Save Our Nation)』で、自身と家族が直面してきた圧力を明らかにした。大紀元との独占インタビューでは、10年に及ぶ政治的左派からの攻撃が事業や家族を揺るがし、父親の命さえ脅かしたと述懐した。こうした経験を通じて、「信念のために戦う決意はいっそう固まった」と強調している。
(インタビュー内容は要約・編集された)
ヤン・エキレック あなたのご家族は長い間包囲下にあり、そのことは新著の中でも触れられている。では、ご自身についてはどうか。状況が不可逆的に変わってしまったと気づいた決定的な瞬間はいつだったのか。
エリック・トランプ あの時のことを決して忘れない。父がワシントンD.C.に行った際、会社を私に託した。だが、自分が「憲法上の保護を受けられない側」になるとは思ってもみなかった。アメリカ大統領には憲法上の保護があるが、私にはなかった。その結果、私はアメリカ史上最も多く召喚状を受けた人物になったとも言える。
(2023年から)私たちは短期間に112件もの召喚状を受け取った。上院や下院、国内有数の司法長官や地方検事などからの大規模な召喚状だった。彼らは我々一家を事業から追い出し、破産させ、父を刑務所に入れ、私を刑務所に入れ、世界中の建物から「トランプ」という名前を消し去ろうとした。
彼らは私たちの人間関係まで断ち切ろうとした。兄弟姉妹との絆を断ち切ろうとし、父とメラニア夫人の関係を壊そうとした。私たちの自宅は家宅捜索も受け、父は弾劾を仕掛けられた。彼らは私たちをツイッターやインスタグラム、Xから排除した。
彼らは司法省を武器として使い、父の選挙運動をスパイし、ロシアとの共謀という作り話をでっち上げた。彼らは汚い文書をでっち上げた。彼らはコロラド州で父を投票用紙から外し、その後メイン州でも父を投票用紙から外した。
父に対する起訴は合計で91件にのぼる。ジョージア州フルトン郡、ニューヨーク市、ワシントンD.C.などで起訴された。顔写真(マグショット)を撮られ、さらに政治的に追い詰めようとした。
同じことは私たち家族にも向けられた。家族を壊し、「MAGA(アメリカを再び偉大に)」運動そのものを潰そうとしたのだ。
そして2週間前、君たちもチャーリー・カークに何をしたか見ただろう? 同じことだったんだ。彼らはその声を封じ込めようとした。そして、それが『包囲の中で――わが家族の祖国を守る戦い』のテーマだ。私たちの家族や、アメリカ史上最大の政治運動を解体しようとした、数え切れないほどの舞台裏の物語を描いている。

ヤン・エキレック それはご家族にどのような影響を与えたのか。
エリック・トランプ 正直に言えば、私たちを岩のように強くしたと思っている。私自身について言えば、ある意味で感覚が鈍くなった。初めて召喚状を受け取った時のことを覚えている。本当に辛かった。でも10通目ともなると、『はい、また来た』という感じになる。
(今となっては)ゲームの内容は分かっている。あれは全部ゲームだ。楽しいゲームでもなければ、いいゲームでもない。でもゲームなんだ。それをまさにゲームとして区分し始める。そは邪悪なことだ。相手側には病んだ人たちがいる。
この国を壊そうとする人たちがいた。意見の違いだけで一人の人間を壊そうとする人たちがいた。
まず彼らがやったのは、父を笑い者にして、あざけることだった。ホワイトハウス記者協会ディナーのことを覚えているだろう。そのあと、父を黙らせようとした。彼らは父をSNSから締め出したのだ。ボコ・ハラムやイランの最高指導者、タリバン、ヒズボラは皆Twitterアカウントを持っていたのに、持てなかったのは誰だったと思うか。アメリカ合衆国第45代大統領だけだった。Facebookのアカウントを持つことすら許されなかったのだ。彼らは私の妻のもとには、「YouTubeでドナルド・トランプ氏について話せばアカウントを停止する」といった手紙まで届いていた。
そして、法廷闘争で父を捕まえることができなかったあとには、父に対して実際の暴力まで使われたのだ。
それは本当に過酷な戦いだった。しかし私たちはあらゆる困難を乗り越えて勝利した。そしてまさにその経験こそが、拙著『包囲の中で』で語っていることなのだ。
ヤン・エキレック これは本当に暗いと感じた瞬間について、ひとつ教えてくれますか。
エリック・トランプ ニューヨークでの裁判の間、毎日父の隣に座っていた。34件の起訴状が読み上げられたことを今でも覚えているが、それらはすべてでたらめなものだった。
父は発言を禁じられていた。私だけが口を封じられていなかったので、毎日裁判所の階段に立ち、裁判全体がいかに不正に操作されているかを大声で訴えていた。34件の重罪有罪判決が下されたあと、彼は振り向き、私と握手を交わした。そして一緒に法廷を後にし、車に乗り込み、そのまま資金集めの集会へ向かった。昼は法廷に立ち、夜は資金集めという日々だったのだ。
車に乗り込むとすぐ、父は私を見て「どうやってかは分からないが、我々は勝つ」と言ったのを覚えている。それは裁判のことだけではなく、大統領選全体のことを指していた。

法廷の傍聴席には報道陣がひしめいていたが、彼に勝ち目はゼロだと口を揃えていた。面白いのは、彼が若い頃に『The Art of the Deal』という本を書き、その後に『The Art of the Comeback』を出版したことだ。後者は90年代の実業家としての彼の復活を描いたもので、誰もが彼は窮地に陥っていたと思っていた時期の話だ。
まさに見事な符合だった。これこそ「カムバック」そのものだった。何も悪いことをしていないのに、完全に武器化された司法制度によって91件もの重罪で訴えられた人物が、最終的に大統領にまで返り咲くと誰が想像できただろうか。
しかも父は単に大統領になっただけではなく、すべての激戦州を制した。一般得票数でも勝利し、全米の州が右派に振れたのだ。カリフォルニア州では共和党が一度も勝ったことのなかった11の郡を獲得し、37年間共和党が勝てなかったマイアミ・デイド郡でも11ポイント差で勝利した。
カムバックの芸術について話しましょうか。彼が若い頃にあの本にそう名付けたことこそが、まさに1年前の我々の立場を予見していたのだ。

ヤン・エキレック カムバックの芸術の話になるが、お父さんがバトラーで銃撃された後に立ち上がり、「戦え、戦え」と叫んだ場面を、外から見てどう感じたか。
エリック・トランプ バトラーの暗殺事件の約6週間前、私が「聞いてくれ、父に身体的危害を加えようとする動きがあっても驚かない」と言ったとき、かなりの批判を浴びた。彼らはあらゆる手を使ってきた。最初は笑いものにしようとした。「ハハハ、彼が成功できるはずがない」と。バラク・オバマ氏が「トランプ氏は真剣に受け止めるべき人物ではない」と言っていたのを覚えている。だが、その言葉を発したのは「コミュニティ・オーガナイザー」だ。冗談じゃない、彼はこれまでの人生で何ひとつ成し遂げていないのだ。
そして当然のことながら、彼らは父を黙らせようとしたが、法廷闘争はうまくいかなかった。だから私は言ったのだ。「次に来る論理的な展開は暴力だ。彼らはそうする。物語の主導権を失ったら、暴力に訴えるのだ」と。そして私はその通りに当てたのだ。
私は散々叩かれた。「あいつは危険を煽るだけだ」と言われた。だが案の定、6週間後にバトラーで事件が起きた。そしてその2か月後にはゴルフ場での事件があった。そのさらに1年後には、いうまでもなく、我々の親しい友人(チャーリー・カーク氏)に同様なことが起きた。
2024年9月、トランプ氏がフロリダ州ウエスト・パームビーチのゴルフ場でプレーしていた際、暗殺未遂事件が起きた。2025年9月10日、米若手保守派活動家チャーリー・カーク氏がユタ州オレム市のユタ・バレー大学(Utah Valley University)で演説中に狙撃され、死亡した。
我々が生きている時代は本当に狂気じみている。国がここまで来てしまうとは夢にも思わなかった。だが断言できるのは、人々はこの茶番と愚行に心底うんざりしており、その実態を誰もが見抜いているということだ。
これこそが我が国で民主党からの大量離脱が起きている理由だと思う。そして、この4年間で、全国の大学生が教師や終身教授によって改ざんされた歴史を叩き込まれてきた世代が一斉にこちら陣営に加わるようになった。振り子は、ほとんどの国の人々には理解できないほどの規模で大きく振れた。私はその流れに大きく貢献できたことを誇りに思っている。

ヤン・エキレック バトラーで起きた暗殺事件は、2024年の大統領選にどれほど大きな影響を与えたと思いますか。
エリック・トランプ 非常に大きな影響を与えたと思う。父が手を挙げているのを見た時、心の中で思った。「これで選挙に勝った。人々はこんなことを見過ごさない。人々は急進左派の正体を知っている。もはや彼らは自分たちを隠していない。我々は彼らが何者であるかをはっきりわかっている」
彼らはあなたをファシストと呼びながら、黒ずくめで屋上に陣取り、狙撃銃を構えて、憲法修正第1条に基づく権利(言論の自由)を平和的に行使している人を撃つ連中だ。私にとって、それこそがファシズムの姿であって、発言している相手では決してないのだ。
これらの銃弾は一方向にしか飛んでこない。スティーブ・スカリス氏(下院多数党院内総務)、父とチャーリー・カーク氏だ。彼らがブレット・カバノー氏(共和党所属の米最高裁判事)にほとんど手を下しかけた。そしてその他大勢の人々に対してもそうだ。そうだろう? 彼らは私のような人間が舞台に立つことを望んでいない。地下室に押し込めたいのだ。2020年のジョー・バイデン氏のように、地下室から出ず、声を上げないことを求めている。もしそれが我々の戦略だったなら、勝ち目はまったくなかっただろう。
2016年、ヒラリー・クリントン氏は我々の5倍の資金を集めていた。我々が声を張り上げ、多少「政治的に正しく」なくても、心から語り、激戦州すべての農場のトラクターに乗って拡声器を握り、あらゆる教会、家庭、集会、ピクニックで演説をしなければ、勝利の可能性はなかっただろう。彼らもそのことを理解しているのだと思っている。だからこそ、人々が外に出て大規模な集会を開くことを阻止しようとしているのだ。
しかし、それを絶対に許してはならない。我々は今こそ、これまで以上に声を上げなければならない。人々は再び、あの党の正体を見抜き始めている。その結果、50州すべてが右へと振れ、我々は得票数でも勝利し、激戦州をすべて大差で制した。人々は確実に我々の側に集まってきているのだ。
ヤン・エキレック お兄さんと比べると、これまで控えめな印象だったが、2024年は非常に積極的に活動されているように見られた。僭越ながら伺うが、将来的に政治の道を志す考えはあるのか。
エリック・トランプ 私は、目立つ立場にいる必要のない人間だ。長い間、会社を経営してきたし、その仕事が得意でもある。仕事が好きだし、資本主義も好きだ。ホテルも不動産も愛している。政治も楽しんでいるが、私の本心ではない。正直に言えば、政治家の半分は嫌いだ。なぜなら彼らの多くは、これまで実際に何かを成し遂げたことのない、ただ乗りの人間だと思うからだ。
これまで一度も小切手の表に署名して(つまり従業員に給料を払って)きたことのない人間が、国中のすべての企業や人々に適用される法律を作っている。医療について何一つ理解していない人間が、何百万人もの命に関わる決定をしている。どう考えても筋が通らない。
例えばジョー・バイデン氏のように、20歳前後で政治の世界に入り、そのまま50年間も政治の世界に身を置き、やがて大統領になる。そんな人物たちを見れば、なぜ彼らの指導下で国がこれほど機能不全に陥るのか、不思議ではないだろう。彼らは一度も外の世界を経験したことがない。一生を通じて政府からの給料に頼り、「イエスかノーか」の投票だけで生きてきたのだから。
そうしたシステムは嫌いだ。私は決して臆病ではないが、必要があれば人前に出ずに身を引くこともできる。むしろ裏方で動いて、人目につかないまま目標を達成するのが好きだ。そして、いざ表に立つべきときにはきちんと立つ。例えば、共和党全国大会で父を紹介したときは、何億もの人々の前に立った。ステージに立つことには慣れている。
だが同時に、勝利した11月6日の朝一番、まだ眠っていなかった私は父に電話をかけた最初の人物でもあった。「父さん、心から愛している。本当におめでとう。私たちはスーパーボウルに勝ったんだ。ステージに立てたことは人生で最高の栄誉だった。でも私は会社に戻り、仕事に戻る。この国は素晴らしい人たちの手に委ねられているし、ビジネスもまた素晴らしい人たちに任されるだろう。父さんは父さんの得意分野で力を発揮し、私は私の得意分野で力を発揮する」とそう言った。だからこそ、こういうときは喜んでスイッチを切り、再び裏方に戻ることができる。そして、そのことをむしろ楽しんでいる。

ヤン・エキレック ちょっとシェアしたいことがある。2024年の前に、私のところにも「政治に出てほしい」と言ってくる人がいたし、きっとあなたのところにも同じような話があっただろうと思う。私はそういう人にこう答えていた。
「私たちには、結果を出せる人、何が何だか分かっている人、そして政治をあまり好きではない人が必要だ」と。だから今回はあなたに出馬をお願いしているわけではないが、あなた自身はその可能性を考えたことはあるのか。
エリック・トランプ 世の中において何事も完全に否定はしないし、この生態系は美しいと思っている。
父が変革を起こしているのを見守っている。バイデン政権下での軍入隊は、我が国の歴史上最悪の状況だったが、その一か月後には誰もが志願し、誰もがアメリカ軍に入りたがるようになった。愛国心が再び芽生えたのだ。
つまり、本当にリーダーとして正しい行動をとれば、いくつかの物事を大きく変えることができるということだ。「自分はワシントンに行って世の中を変える」と言うキャリア政治家たちのことは忘れたほうがいい。ほとんどの者は結局ワシントンの政治の渦にのみ込まれてしまうのだから。
でも、私はどんな可能性も否定しない。政治の場が、私たちに大きな発言力を与えてくれたと思う。私たちは皆、素晴らしい声を培ってきたと思っている。ビジネス界での声、そしてナンバーワンのリアリティ番組「アプレンティス」での声も持っていた。あの頃私たちは自信もあったし、芯もあった。そして突然政治の世界に足を踏み入れていた。あの舞台に立ったからこそ、本物の声、本物の自信、そして気骨を身につけられたと思う。
要するに、ここには本物の気骨が求められる。というのも、彼らは魂から会社、家族、結婚生活に至るまで、あらゆるものを標的にして、徹底的に打ちのめそうとしてくるからだ。
私は、政治というものがある意味で私たちに強い「防御力」を身につけさせたと思う。(政界入りすることは)可能だと思う。ただ問題は「本当にそれを望むかどうか」だ。私たちは政治の華やかな面も見てきたが、同時に最悪の部分も目の当たりにしてきた。その闇の深さは、おそらく多くの人が想像する以上のものだろう。『包囲の中』という本、そのすべてを記録し伝えるために書いたのだ。

しかし、私はどんな可能性も排除していない。この国を信じ、赤・白・青の星条旗を愛し、第一修正条項を愛し、憲法を愛している。アメリカは世界一の超大国であり続けなければならない。
この国には優れた人材が必要だ。ドナルド・トランプのように、富も財産も家族も会社も脇に置いて常識では考えられない挑戦に身を投じる人物であることが望ましい。そういう胆力を持った人は多くない。フォーチュン500の経営者の中で、「すべてを犠牲にして、政治のことをよく知っている16人の共和党候補と渡り合い、(党内指名を勝ち取る)」と言える人はほとんどいない。我々は政治について何も知らぬ立場から、現代でも屈指の名門政治一家に属するヒラリー・クリントン氏と戦わねばならなかったのだ。資金力では五対一の劣勢、しかも自己資金のみで選挙戦を戦い抜き、最後には大統領選に勝利した。
そんな条件を呑む億万長者が他にいるか。ゼロだよね。多くの人間は確率で物事を判断し、伝統的な見方をすればその確率では勝ち目は小さい。そのようなリスクを背負う億万長者がどれほどいるだろうか。だからこそ、多くの人々はウォーレン・バフェット氏のような実業家ではなく、ジョー・バイデン氏を大統領に選んだのだ。
だからこそ、もっと多くの優れたビジネスリーダーが必要であり、変革的な変化をもたらせる人材を私はもっと見たいと思っている。そして、もし星がすべて揃い、自分にとって政治が「正しい呼びかけ」となる時が来れば、私はそれを考えるかもしれない。
とはいえ、社会を変える力を持つ優れたビジネスリーダーは必要である。そうした人物がもっと現れることを心から望んでいる。もし時が熟し、そのときに自分が政治の道に進むべきだと感じたなら、私は真剣に考えるつもりだ。
ヤン・エキレック 本の収益の一部をチャーリー・カーク氏を記念して「ターニング・ポイントUSA」に寄付されるそうですね。その理由を簡単に教えてくれますか。
エリック・トランプ それこそが『包囲の中』のテーマだ。チャーリーに起きたことそのものだからだ。本が彼の暗殺の3日前に出ていなければ、最終章はチャーリーの話になっていたはずだ。彼らは私たちの声を消し、ステージから引きずり下ろそうとしている。しかし、それを許してはならない。
ターニング・ポイントは非常に重要な組織であり、独立した声を持つことも同じく重要だ。だからこそ私は本の収益の一部をターニング・ポイントに寄付し、その使命が続くようにするつもりだ。彼らが試みたように、私たちの声を再び奪われないようにするためだ。
彼らはたった一発の弾丸で彼の声を消せると思ったのだろうが、それは誤りだった。むしろその逆だ。今、私たちの声はこれまで以上に強くなっていると私は考えている」



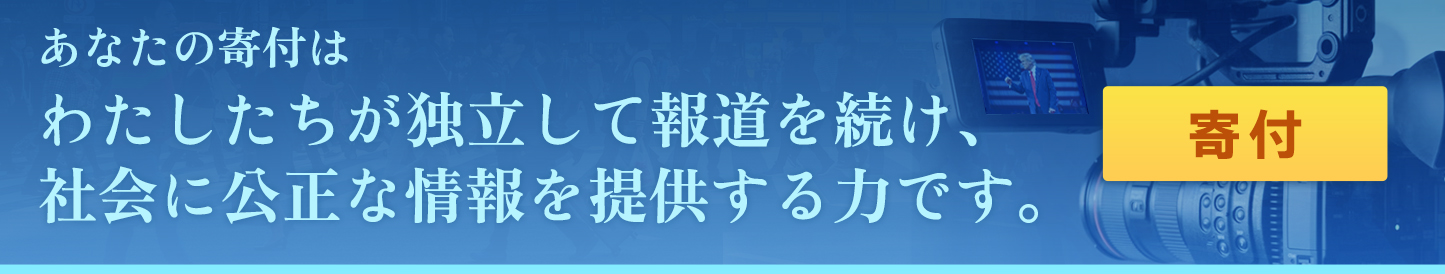









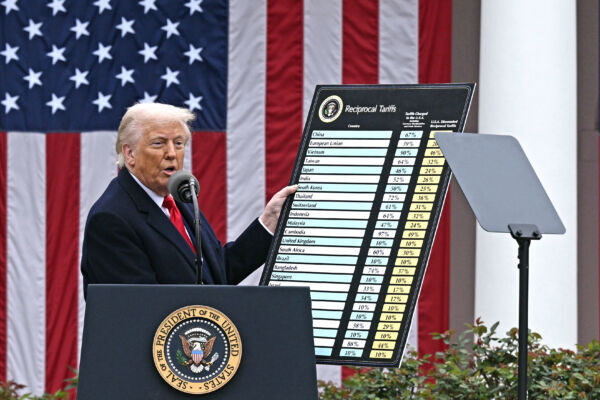


 ご友人は無料で閲覧できます
ご友人は無料で閲覧できます Line
Line Telegram
Telegram











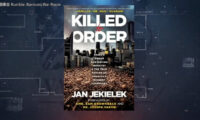

ご利用上の不明点は ヘルプセンター にお問い合わせください。