キヤノンの2024年12月期連結営業利益が前年比25.5%減の2797億円となった。中国市場の低迷が主因で、医療機器事業で1651億円の巨額のれん減損を計上。中国での需要減少や国内医療機関の経営難が影響し、当初の増益計画から一転、大幅減益となった。
ロイター通信によると、キヤノンが2025年1月30日に発表したこの数字は、同社が以前に発表していた会社計画4555億円を大きく下回り、増益予想が一転して大幅な減益となった。
減益の主な要因は、メディカル事業における1651億円という巨額の「のれん減損」を計上したことにある。キヤノンは2016年に東芝メディカルシステムズ(現キヤノンメディカルシステムズ)を約6600億円で買収し、複合機やカメラに次ぐ新たな経営の柱として期待していた。しかし、地政学的リスクによるビジネスの縮小や中国の景気低迷、日本国内の医療機関の経営状況悪化などのビジネス環境の変化を受け、より保守的な販売予測に基づいて将来計画を見直した結果、事業価値が帳簿価額を下回ることとなった。
中国市場では、政府による病院関係者の贈収賄摘発などの反腐敗キャンペーンの影響で、高額医療機器の購入を先送りする動きが出ている。また、国内でも新型コロナウイルス禍で経営難に陥った病院が支出を抑える傾向にあり、これらの要因がメディカル事業の業績に影響を与えたとみられる。
一方で、キヤノンは2025年12月期の連結営業利益を前年比85.5%増の5190億円と予想しており、アナリストの予想平均4907億円を上回る見通しを示している。また、株主還元策として最大1千億円の自社株買いの実施や、2024年12月期の年間配当を前期比15円増の155円とすることも発表した。
キヤノンは引き続きメディカル事業を長期的に安定した成長が期待できる事業と位置づけており、今後も積極的に成長戦略を推進していく方針だ。しかし、今回の大幅な減損処理は、医療機器市場の変化や競争の激化に直面する同社の課題を浮き彫りにしたとも言える。今後、キヤノンがどのようにしてメディカル事業の立て直しを図り、成長軌道に乗せていくのか、注目が集まっている。
日本企業が中国から撤退加速
日本企業の中国市場からの撤退が加速している傾向が見られる。2024年時点で中国に進出している日本企業は約1万3034社であり、2年前と比べて328社増加しているものの、この数字はコロナ禍前のピーク時には及ばない。特に上海市では約1千社、全体の1割を超える日本企業が減少しており、2020年から2022年にかけて累計2292社が中国から撤退したことが報告されている。
この撤退の背景には複数の要因が絡んでいる。経済的要因としては中国経済の成長鈍化や人件費の上昇による採算性の悪化が挙げられる。また、米中対立の影響やサプライチェーンへの影響懸念といった地政学的リスク、中国政府の政策変動や「ゼロコロナ政策」によるロックダウンの影響などの政策リスク、さらには中国現地企業との競争激化による競争環境の変化も大きな要因となっている。
業種別に見ると、製造業では事業統合や整理が進行中で、生産拠点の再配置や東南アジアへの移転が加速している。自動車産業では日産自動車や三菱自動車が工場閉鎖や事業撤退を決定した。一方で、サービス業や販売業では中国市場への新規進出が継続している傾向も見られる。
今後の展望としては、日本企業の中国ビジネスに対する姿勢が慎重になっており、多くの企業が事業の再編や多様化を進めている。一極集中から分散化へと戦略を転換しつつあるが、完全な撤退ではなく事業の最適化や再編を行う企業も多く見られる。
この動向は、日本企業が中国市場のリスクと機会を慎重に評価し、グローバルな事業戦略を再構築する過程にあることを示している。
トランプ新政権で新局面
日本企業の中国市場からの撤退傾向に加え、トランプ新政権の誕生により、日本企業は新たな課題に直面している。
トランプ大統領の「アメリカ・ファースト」政策の下、米中経済のデカップリングが加速する可能性が高まっている。これにより、日本企業は以下のような影響を受ける可能性がある。
対中関税の引き上げ
トランプ政権は中国からの輸入品に対する関税を60%程度まで引き上げる可能性があり、中国に生産拠点を持つ日本企業の輸出に大きな打撃を与える恐れがある。
サプライチェーンの再編
米中対立の激化により、日本企業は中国からの生産拠点の移転や、サプライチェーンの見直しを迫られる可能性が高い。
技術規制の強化
人工知能や先端コンピューティングなど、軍事転用可能な技術分野での対中輸出規制が強化される可能性がある。
二国間交渉の重視
トランプ政権は多国間協定よりも二国間交渉を好む傾向があり、日米間で新たな貿易交渉が行われる可能性がある。
対米投資の重要性
日本企業は米国内での投資や雇用創出をアピールすることで、トランプ政権との関係構築を図る必要性が高まっている。
保護主義の台頭
米国の保護主義的な政策により、日本企業の輸出環境が悪化する可能性がある。
変化への対応
これらの変化に対応するため、日本企業は米国市場への依存度を高めつつ、同時にリスク分散を図る必要がある。また、米国政府や州政府との関係強化、研究開発投資の拡大、サプライチェーンの多様化などの戦略が重要となる。
トランプ政権下での米中対立の激化は、日本企業に大きな課題をもたらすと同時に、新たなビジネスチャンスを生み出す可能性もある。日本企業は、この変化する国際環境に柔軟に適応し、戦略的に対応していく必要がある。


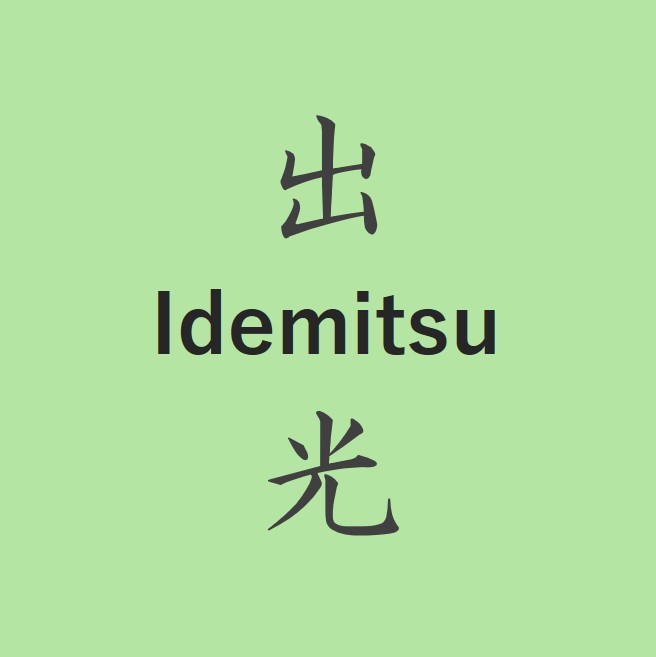













 ご友人は無料で閲覧できます
ご友人は無料で閲覧できます Line
Line Telegram
Telegram


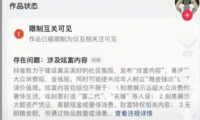







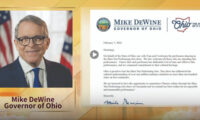



ご利用上の不明点は ヘルプセンター にお問い合わせください。