2024年の実質賃金は前年比0.2%減となり、3年連続のマイナスとなった。賃上げの動きはあるものの、物価上昇に追いついていないのが現状だ。
厚生省が5日に発表した勤労統計調査の結果によると、名目賃金(現金給与総額)は2.9%増の34万8182円となり、33年ぶりの高水準を記録。しかし、消費者物価指数(CPI)が前年比3.2%上昇し、賃金の伸びを上回ったため、実質賃金は引き続き減少した。特に、エネルギー価格の上昇や円安による輸入物価の高騰が影響している。
2024年9月の実質賃金は前年同月比0.1%減となり、マイナス幅は縮小した。これは、政府の電気・ガス料金補助金の復活により、物価上昇率が低下したことが要因とみられる。
物価の変動を反映した実質賃金指数を見ると、規模5人以上の事業所は前年に比べて0.2%減少して、3年連続のマイナス。一方、規模30人以上の事業所は99.0と、前年より0.1%の増加で、2年ぶりにプラスとなった。
この結果から、大企業では賃上げが進んでいるものの、中小企業では物価上昇に対する給与の伸びが追いつかず、厳しい状況が続いていることが分かる。人件費の上昇や原材料価格の高騰が続くなか、価格転嫁が難しいことが背景にある。
さらに、円安による輸入コストの増加やエネルギー価格の上昇も、中小企業の負担を一層重くしている。実質賃金の低下が続けば、労働力の確保や従業員の生活維持にも影響を及ぼす可能性がある。
日銀は1月24日の金融政策決定会合で、政策金利を0.25%から0.5%に引き上げた。 植田和男総裁は、今後も経済・物価の見通しが実現すれば、利上げを継続する意向を示している。利上げが企業の資金調達コストを押し上げ、中小企業の経営に影響を及ぼす可能性も指摘されている。特に、資金繰りが厳しい企業にとっては、借入金の利息負担が増加することで経営環境が一段と厳しくなる恐れがある。

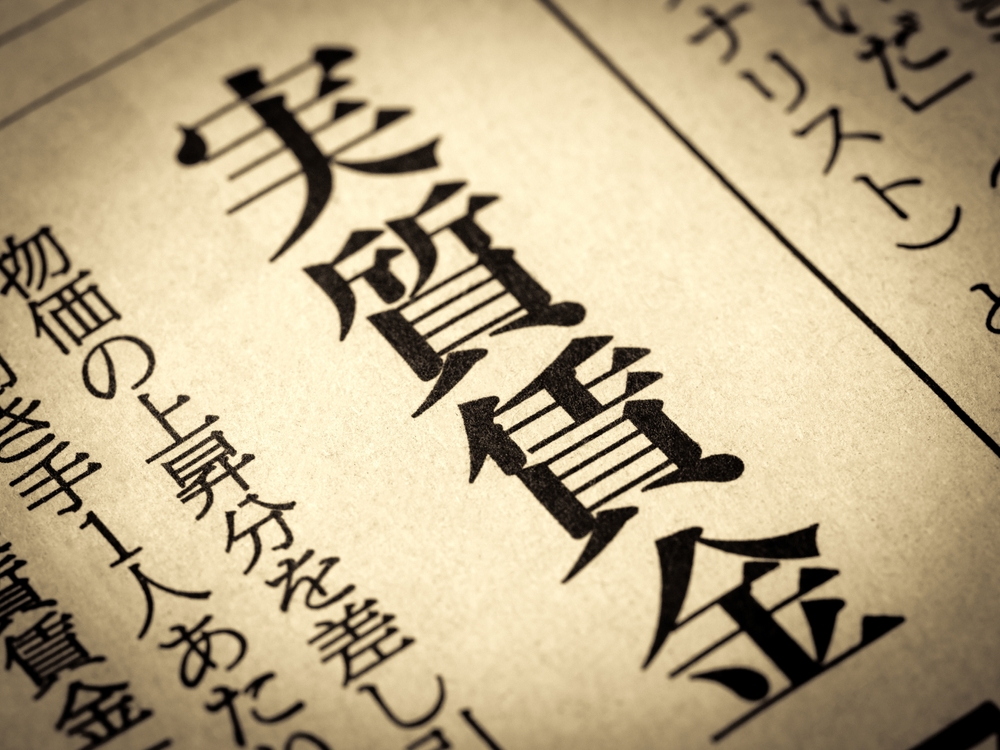









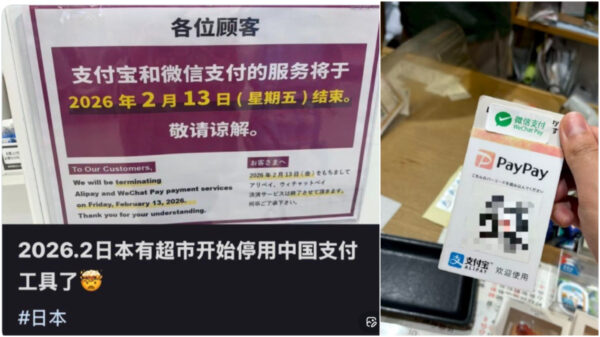




 ご友人は無料で閲覧できます
ご友人は無料で閲覧できます Line
Line Telegram
Telegram













ご利用上の不明点は ヘルプセンター にお問い合わせください。