(魏徴の上書、続き)
「ですので、君主たるものは、以下の十のことがらについて、心に留めることが肝要でございます。まず、欲しいものを見ても知足(足るを知る)を忘れず、自ら戒めるようにすること。造営しようとするときには、民を疲弊させず、安んずることを思うこと」
「高くて危ういことを心に思うときは、謙遜して自己を慎むこと。満ち溢れることを思うときは、江や海があらゆる川よりも低い場所に位置している事実に思い至ること。狩猟などで遊び楽しみたいときは、三駆を限度とすること」
「怠惰な心が出て、なまけたいと思うようなときは、始を慎み、終を敬することを守って、最後まで完遂すること。君主の耳目を覆い隠す者があることを懸念するならば、虚心に臣下の言を聞き入れるよう努めること。讒言する邪悪な臣があるのを恐れるときは、君主みずから身を正しくして、悪を斥けること」
「臣下に恩恵を与えるときは、君主が小さな喜びで賞を誤ることがないよう注意すること。罰を加えようとするときは、怒りにまかせて、むやみに重刑を科することがないよう心がけること」
「この十思を、君主がしっかりと守り、その徳をひろく人民にまで敷衍すれば、皆これに感化され、文人も武人も争って国家のために、進んで尽くすようになりましょう。そうなればもはや、無為にして天下が平和に収まるという、古の聖天子の大道に欠くところがございましょうか」
ここまで魏徴の上奏文を読んだ太宗は、自ら詔書をしたため、こう答えられた。
「卿(けい)の意見書をたびたび読むにつけ、その真心に深く感じ入った。朕は、開き読んで倦むことを忘れ、いつも夜半に至ってしまったほどだ。卿が国家と同体になっているほど情が深く、自身の利害もかえりみないほど義を尽くすのでなければ、どうしてこれほどの文書を示してくれるだろうか」
「朕は、必ずこれを机上に置き、我が不足を正す戒めとしよう。君臣水魚の交わり当代に無し、とはさせるまい。卿は今後も、朕に直言して、いささかも隠すことあるべからず。朕は虚心にこれを聞く。敬して、卿の徳音を待つであろう」
*****************************
魏徴のこまごました上奏文に対して、太宗が、このような親筆の返書を送ります。
実際は、非常に長い返書であり、過去の教訓となる事例を太宗も多く引用していますが、要は魏徴の諫言の通り、君主が高い徳をもたなければ、臣下も忠義を尽くさないことを述べています。そして、太宗みずから、「これを机上に置き、そのような君主になるよう努力する」との決意を示しています。
いずれにせよ、この返書を開いた魏徴は、感激のあまり恐懼して、号泣したかもしれません。まさに太宗は、そういう名君でした。
魏徴の文中にある「三駆」とは、例えば狩猟で獲物を追い込むときでも、四方すべてを塞ぐのではなく、一方の逃げ道を残しておく「三駆」にすることで無駄な殺生をしなくてすむという、帝王ならではの配慮を指します。
この一書『貞観政要』が編纂されたのは、太宗の死後40~50年のころであったとされています。日本には、平安時代の中期には伝わっており、以後、北条氏、足利氏、さらには江戸期の徳川家康から明治帝に至るまで、政治の最重要職にある日本人にとっても、帝王学の指南書として愛読されてきました。
『貞観政要』が繰り返し説くのは、枝葉のような政治の方法論ではなく、君主たるものが絶対に違えてはならない仁政の根幹であり、まさに為政者のもつべき正しい心構えなのです。
まずは君主が自身を正してこそ、その徳が臣下にも人民にも伝わり、国家が安らかに栄えていく。
その理想政治が、太宗の後につづく中国歴代王朝でどれほど実現できたかは難しい議論になりますが、ともかくも尭舜による古代の聖人政治から下ること約2千年、中古(または中世)の中国に、「貞観の治」という極めて理想的かつ具体的な「お手本」を提示した太宗は、後世の中国人の誰もが敬愛する大皇帝であったことは疑いありません。
小欄【古典の味わい】における『貞観政要』第一部は、今回で終了します。また機会を改めて、第二部をお届けする予定です。
(鳥飼聡)


 【古典の味わい】貞観政要 12
【古典の味わい】貞観政要 12 
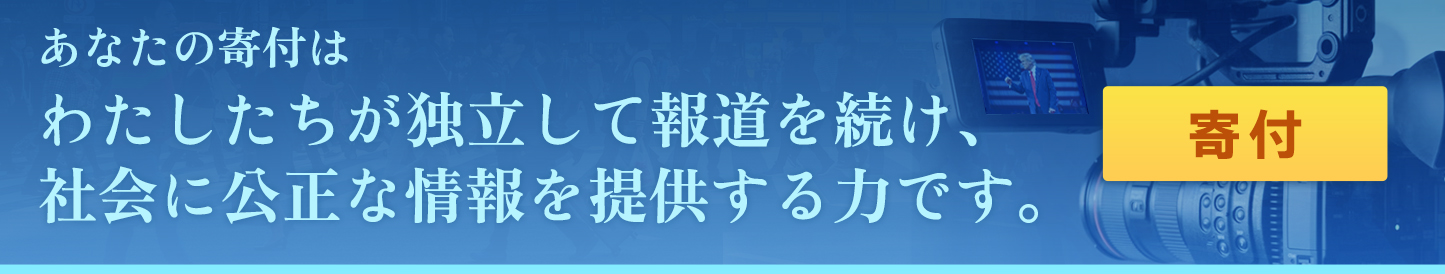







 ご友人は無料で閲覧できます
ご友人は無料で閲覧できます Line
Line Telegram
Telegram












ご利用上の不明点は ヘルプセンター にお問い合わせください。