中国発の越境電子商取引(EC)がコロナ以降急激に成長し、日本や米国など先進国への過剰供給が問題となっている。激安製品が世界に広がる要因には、先進国が送料負担するという巧みな国際条約の利用にある。条約上は発展途上国にある中国は、日本側に激安製品の送料を負わせることができるのだ。
急伸する中国EC
中国ECはいまや世界を席巻している。激安と広告戦略が目を惹く「Temu(テム)」を運営する中国EC大手「拼多多(pinduoduo)」は、創業から1年半あまりで50カ国に進出。23日に発表した第1四半期の純利益は昨年比で246%増だったという。
中国共産党の機関紙「新華社」は2023年11月、過去5年で越境電子商取引の対外貿易に占める割合は1%未満から約5%に上昇したと報じた。
こうした急伸の背景には、国際条約「万国郵便条約」の抜け道を利用にあるのではないかと、米国サウスカロライナ大学エイケンビジネススクールの謝田教授は指摘する。
万国郵便条約には、発展途上国が先進国へ荷物を送る際に、先進国側が一定の郵便料金を負担するという仕組みがある。元々は発展途上国の貿易促進を目的としているが、近年では中国のような輸出大国が、先進国への過剰供給を助長させている。郵便条約上、中国は発展途上国扱いなのだ。
大紀元の取材に応じた謝田氏は、万国郵便条約のこのような仕組みがなければ、中国発の通販サイトは存続が困難になるのではないかと考えている。
先進国の立場にある日本とて例外ではない。日本の消費者にとって数百円の小物が中国から送料無料で届くのは魅力的にうつる。しかし、日本国内での送料を負担するのは、日本の郵便事業者だ。
Xユーザーの「souco中原(@souco_ceo)」氏は今年3月、「日本までなんとかコンテナに詰めて運べば、そのあとの国内配送コストは日本持ち。単価あたり一番コストがかかるラストマイルコストは日本に負担させてる」と投稿し、話題を呼んだ。
郵便事業者への送料の負担が大きい場合、郵便料金の上昇や利用者である国民の負担増につながる。コスト増を料金に転嫁できない場合、郵便事業者の収益性が悪化することにもなりかねない。国内の郵便事業者が、国際条約によって不公平な競争にさらされている。
経済学者の李恒青氏は取材に対し、中国はすでにWTOに加盟して20年以上経っており、もはや発展途上国ではないと強調。廉価な商品によって自国の産業が空洞化しないように注視することは、政府の責任であると指摘した。
李恒青氏は、欧米諸国は今後、中国系通販サイトに対して対策を取る可能性があると語る。
実際に欧州では、このような不平等な仕組みを変更する機運が高まっている。EUは2021年から少額輸入商品に対して増値税を課し始め、2023年には「EU関税改革提案」を発表。150ユーロ以下の輸入貨物に対する関税免除を廃止する計画を立てた。
フランスの下院は3月14日、中国の激安通販サイトを念頭に、過剰消費を抑えることを目的とする「2129法案」を可決した。「衝動買い」を促す広告を禁止し、規制に従わないブランドには衣料品1点ずつに罰金を課する。
韓国でも公正取引委員会傘下の消費者院が中国系通販サイトのアリエクスプレスとTemu(テム)と製品の安全に関する協定を締結した。韓国メディアによると、消費者院はモニタリングと危害性試験を強化する予定だ。














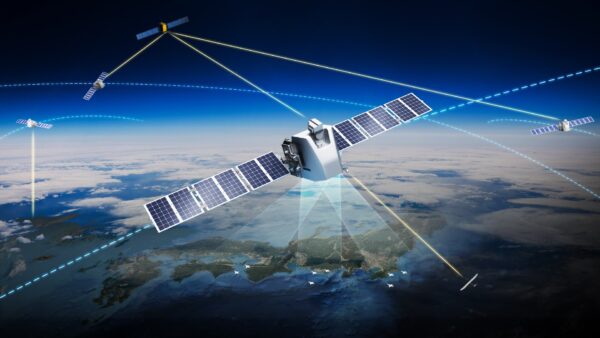

 ご友人は無料で閲覧できます
ご友人は無料で閲覧できます Line
Line Telegram
Telegram













ご利用上の不明点は ヘルプセンター にお問い合わせください。