初夏の暖かい日差しがカフェの窓から差し込み、木製のテーブルに柔らかな光を投射する。カップの中のコーヒーをかき混ぜる顔さん(ヤンさん、中国人留学生)の目には、深い思索の色が宿っていた。中国本土の学校に通い、愛国主義を信奉していた彼は、今や全く異なる道を歩んでいる。その眼差しの奥には、語り尽くせない数々の物語が潜んでいた。
内心の変化は、一見何気ない出来事から始まることがある。一本の映画、ひとときの会話、そうした要素が彼の内面に深い影響を与えてきた。映画『大隻佬』(Running on Karma)で顔さんの心に生じた波紋は、やがて「小粉紅」[1]を反共主義者へと導くこととなった。真実に向き合うなかで、顔さんはどのような心の旅路を歩んだのか。一連の出来事を彼自身の言葉で語ってもらった。
[1] 中国共産党を熱心に支持し、インターネット上で中国の国家主義的な立場を強く擁護する人々
洗脳教育と転機
――中国本土でどのような教育を受けたか教えてください。
中国本土で極端な愛国主義教育を受けたため、外国は基本的に「万悪の資本主義」で満ち溢れており、人々は苦難のなかで生活していると思っていた。そして、幼い頃から「中国共産党こそが最善である」と教育されていたため、アメリカや日本といった西側諸国に対して敵意を抱いていた。
また、自分の意見と合わない人に対しては、過激な言葉を用いて「対話」をすることが多かった。
――そうしたなかで、どのようなことが転機となったのか。
2012年に『大隻佬』(Running on Karma)という映画を見たことが大きな転機となった。主演は劉徳華(アンディ・ラウ)と張柏芝(セシリア・チャン)で、戦争に参加した日本の老兵が死後に転生し、善良な中国の女性として生まれ変わるという話だ。その女性は善行を積むが、悪夢に悩まされ、常に危険にさらされる。劉徳華が演じる少林武僧「大隻佬」が何度も彼女を救おうとするが、最後には追手に殺されてしまう。
――具体的にどのような部分から影響を受けたのか?
大隻佬は葛藤を抱えていた。彼の師匠は『彼女は前世で日本兵だったから、今生で彼女が斬られるのは因果応報だ』と言った。しかし大隻佬は納得せず、『彼女の前世は日本兵だが、今生の彼女は別人だ。前世の罪を償うために、今生の彼女が犠牲になるのはおかしい』と反論した。
この映画を見てから、私は深く考えるようになった。過去の出来事にこだわる必要があるのか。なぜ人々は戦争に執着するのか。人間の本性は一体どのようなものか、と。そこから、私の考えが大きく変わり始めた。
――その後、どのように考えたのか。
祖父母の家に行ったとき、仏教を信じる祖母が寓話(ぐうわ⦅たとえ話⦆)を語ってくれた。人は悪事を働くと、死後地獄に落ちるが、罪を償った後は再び人間として生まれ変わると言った。中国では『悪有悪報、善有善報(善には善の報いあり悪には悪の報いあり)』という考え方が何千年も伝えられてきた。悪事を働けば必ず償わなければならないという考えだ。
また、子供の頃から様々な伝説や物語を聞いてきた。この世で悪事を働くと、動物などに生まれ変わるといった話や、『西遊記』の猪八戒がなぜ豚の姿になったのかという話は印象に残った。これらの話を聞いて、私は納得した。
中共の無神論教育とその矛盾
――中国共産党が喧伝する無神論についてどう思ったか?
一時期はどちらが正しいのか分からなくなった。その後、私は世界にある様々な謎について興味を持つようになった。ピラミッドなどの遺跡は進化論と必ずしも一致しない部分がある。物事を深く考える性格なので、これらの問題について思索を深めた。
古来から世界中の人々は、殺人を悪だと考えてきた。これは全人類の共通認識だ。それならば、闘争哲学を説き、数多くの人々を虐殺してきた共産党の教えは、人類に反するに違いないのだ。
このように考えて、輪廻転生をますます認識するようになった。私たち一般人は、大きな善行も悪行もない。人を殺す勇気もないので、再び人間に生まれ変われる可能性は高いのだろうか。来世では他の国や、他の人種の人間に生まれ変わる可能性もあるのではないかと思うようになった。たとえば、アメリカ人、ヨーロッパ人、日本人、インド人、アフリカ人などに。
――この考えを周囲の人に話したことがあるか?
この考えを周囲の人に話したことはある。でも、多くの人には受け入れられなかった。特に、愛国心を持ち、共産党を支持する「小粉紅」たちはそうだ。高校の同級生にこの考えを話したところ、「勉強が無駄になった」と言われ、政治の教科書をもっと勉強するように言われた。
洗脳教育の影響
――一部の中国人が外国に対して強い敵意を抱くのはなぜか。
外国や敵対勢力に対して憎しみを抱くよう教え込む中国共産党の教育が原因だと思う。彼らはこれを「愛国主義教育」と呼んでいる。
例えば、中学校のときには国民党が抗日戦争で消極的だったと教えられ、中国共産党だけが功績を持つと教わった。しかし、当時の戦争を描いた映画を見ると、国民党軍と日本軍が戦闘を繰り広げる様子は多く描写されていた。
映画の中で、私と同じ年頃の兵士たちが中華民国の国旗を守って戦っているシーンがあった。それを見て、国民党が消極的だったという話はおかしいと感じた。さらに当時の歴史資料を読み込んだところ、中国各地には多くの国民党軍の兵士の墓があることを知った。中国の歴史教科書が真実を歪めていることに気づき、中国共産党が若い世代に外国への敵意を植え付けようとする魂胆を見抜いた。
――あなたが感じた最大の欺瞞(ぎまん)は何か?
一番大きな欺瞞は台湾問題だと思う。中国本土では国外のサイトを閲覧できないが、私は反抗的な性格だったので、中学生のときに初めてVPNを使ってFacebookをダウンロードした。そして台湾人中学生の友達ができた。
彼が私に「どこから来たの?」と尋ねた時、私は「広東省から来た」と答えた。すると彼は「大陸から来たんだね」と言った。中国共産党の教育では、台湾も中国共産党が支配する共産主義中国の一部だと教えられていたので、なぜ彼が私を「大陸の人」と呼ぶのか理解できなかった。その後、さらに調べてみると、台湾と中国本土には「2つ」の政府があることが分かった。これが私が最も深く欺かれていたと感じるところだ。
天安門事件の真相
――こうして少しずつ「小粉紅」から反共主義に転向していったのか。
私を完全に「小粉紅」から転向させたのは、六四天安門事件の真相を知ったことだ。今日の中国本土の中学校で天安門事件を教えているかどうかは分からないが、私が中学校に通っていた頃は教えられていた。ただ、その内容は非常に簡略化されていて、「悪い学生たちが反乱を起こして政権を倒そうとした」としか教えられていなかった。実際にはこの事件についてほとんど何も知らなかった。
広東人なので、香港に親戚が何人かいる。ある時、香港の親戚の家を訪れた際に、空港で無料で使用できるコンピュータがあったので、それを試してみようと思って画面を点けると、前の利用者が残した検索ページが表示された。最初に見た写真は、天安門広場に集まった多くの学生が拳を突き上げて何かを叫んでいるものだった。

当時私は、「天安門のような場所でこんなに多くの人が集まってスローガンを叫ぶなんて、本当だろうか。すぐに逮捕されるはずじゃないか」と思った。しかし、彼らの顔には全く恐れがなく、むしろ晴れやかだった。
次の写真では、彼らは頭に「絶食」「正義」「死」などと書かれたハチマキを巻いていた。しかし、その後の写真には血まみれの自転車や両脚を切断された人々が映っていた。人々が負傷者を引っ張って狂奔する様子も写っていた。この瞬間、私の世界観が崩れ始めた。最初はこれらの写真は偽物だと思っていたが、BBCの報道だと分かり、本物だと思うようになった。その後、真剣に記事を読み進め、これが六四天安門事件だと知った。

記事を読み終えると、私はその場に呆然と立ち尽くしていた。中国に対する恐怖と憎悪の感情が心の底から湧き上がってきた。ちょうどその時、中国に戻る飛行機に乗るところだったが、それ以来、私は中国共産党の統治下にある土地に足を踏み入れることに強い抵抗感を覚えるようになった。「私のような人間は、いずれ『戦車にひかれて両脚を失う』運命に直面するだろう」と感じたのだ。
日本への留学
――最終的に日本への留学を選んだが、きっかけは何か。
中国で生活することに危険を感じていたのが、一つの原因だ。そして、私は広東省で生まれたが、香港にも親戚がいた。香港は当時、中国本土よりも自由で、特に信仰の面ではそうだった。香港の親戚の数人はキリスト教を信仰していた。その後、親戚や友人たちは日本に移住した。私は中国の宣伝による憎しみを信じていなかったので、日本を見てみたいと思った。
また、中国の大学入試で1千万人以上と競争したくなかった。その後、日本の大学に進学して、キリスト教系の大学を選んだ。
――日本での学びの中で何か興味深い経験はあったか?
実際、日本で勉強していても中国共産党の影響を感じることはあった。私の大学には孔子学院があり、先生から「大学内での発言には注意するように」と言われた。日本の大学にいるのに言論の自由がないのかと驚嘆した。
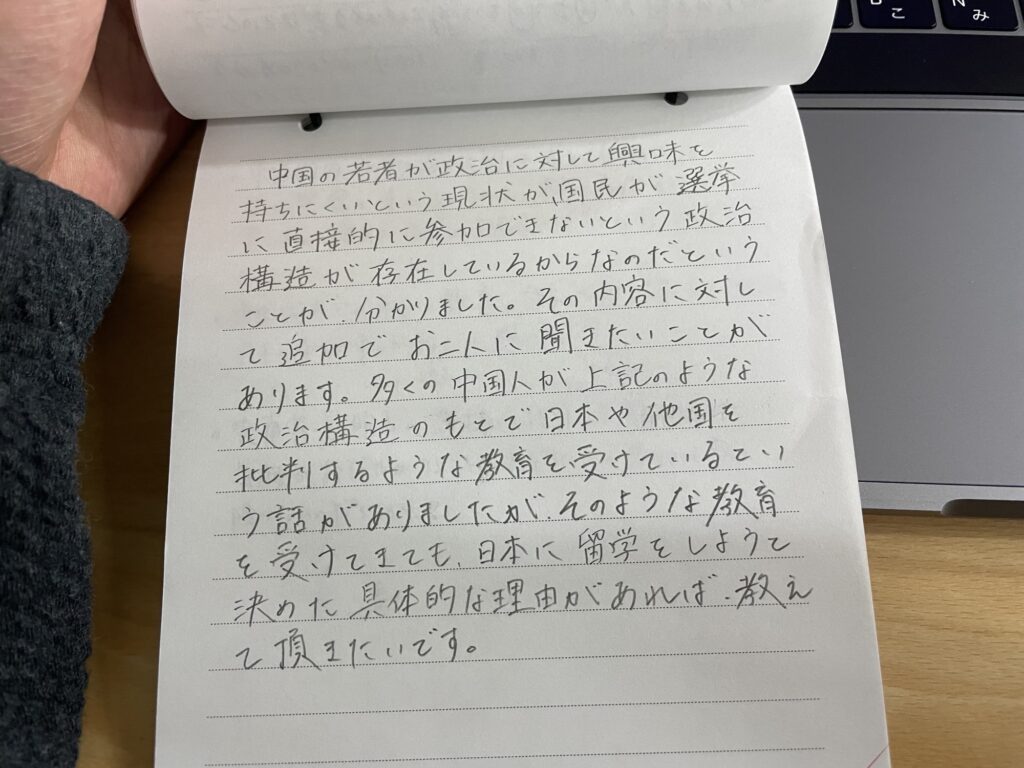
クラスメートが、孔子学院はスパイ機関だと言っていて、いつどこで何を話しても周りの「小粉紅」に報告されるかもしれないと注意を呼びかけていた。もちろん、学内には中国共産党を批判する先生もいて、授業中に中国人学生が先生に暴言を吐くこともあった。しかし、4年間の大学生活で中国共産党からの脅威を感じることはなかった。その点では、私は大学に感謝している。
4年間で様々な人に出会い、私と同じ考えを持つ人々がいっぱいいることを知った。これらの考えは中国では『神経症』と見なされるが、日本の大学では課題として議論されることもあると知って驚いた。
(続く)
















 ご友人は無料で閲覧できます
ご友人は無料で閲覧できます Line
Line Telegram
Telegram














ご利用上の不明点は ヘルプセンター にお問い合わせください。