中国の「一帯一路」構想の支援を受けて建設されたダムは、採算性に乏しいものだった。
「一帯一路」構想の一環として、中国は海外で数多くの巨大ダム建設(水力発電機能付き)を支援してきた。目的は、中国の国際的な影響力の拡大だ。
中国の国営メディアはよく、これらのダム建設を海外版「三峡ダムプロジェクト」と吹聴する。しかし、中国の三峡ダムはその環境ダメージの大きさから、各界の批判を受けている。
2009年に竣工したスーダン・メロウェダムは「スーダン版三峡ダム」と呼ばれ、その他エクアドル、パキスタン、エチオピア、マレーシア、ボリビアなどでのダム建設も似たような呼称がつけられた。
これらの建設計画を詳しく調べると、ダム建設による利益はほとんど無いに等しく、国の威信や政治的圧力、宣伝効果のために建設が進められたものが大半を占める。
実利より政治
中国共産党(中共)が打ち出した「一帯一路」構想は、彼らの世界戦略を基礎づける政治的ビジョンだ。それは、中共の統治モデルを推進し、いわゆる社会主義の優越性を喧伝し、「東昇西降」「人類運命共同体」といったナラティブ(物語)を進展させるためのものだ。
中共が目指す究極の目的は何だろうか。
それは、中共がデザインし、影響力を持ち、コントロールするような世界新秩序をつくりだすことにある。債務や技術移転、インフラ整備などを通じてソフトパワーを強化し、外国への影響力を行使する。
経済的な視点で見ると、「一帯一路」構想は中国の過剰な生産力と労働力を外へ吐き出し、世界の重要インフラを長期にわたって支配できるようになる。
では、中国はどのようにして世界のダム建設市場を牛耳るようになったのか。
中共が統治する中国は、その戦略的行動を特徴とする。党中央の一元的な指令と組織的な協調を通じて、中国は大規模なプロジェクトを遂行する。そこでは、外交、金融、プロパガンダ、教育、国家安全保障、国営企業などの要素全てを一つの戦略の元に統合する。
国際的なダム建設では、三峡ダムグループや葛洲ダムグループといったパイオニア企業を中国電力建設グループ(メインバンクは中国輸出入銀行)傘下に置くなど、統合合併を進めてきた。
このような「軍隊方式」の海外展開によって、外国の競合企業はほとんどが撤退を余儀なくされた。関係者は、「彼ら(中国の国営企業)が行くところは、生える草なし」と、競合他社を蹴散らす中国企業の進撃を表現した。
さらに、多くの外資系企業が長い間中共に取り込まれ、その独立した地位を利用して中国の利益を増大させてきた。
世界の水力発電建設における中国の市場シェア
2019年に開かれた中国水力発電発展フォーラムでは、世界の水力発電プロジェクトのうち70%以上は中国企業が受注していることを政府関係者が明らかにした。水力発電分野における中国の対外投資額は少なくとも2千億元(約4兆円)に上り、「一帯一路」構想に沿って40か国以上のプロジェクトに参画してきた。
中国電力建設グループが2023年11月に発表した報告書によると、「一帯一路」構想がスタートした2013年からの10年間で、中国企業は海外で300を超える水力発電プロジェクトに参画してきた。全ての発電量を合計すると1億キロワットに及び、三峡ダムの発電量(2250万キロワット)の4.44倍に相当する。
中には、複数のダム建設プロジェクトに関わった国もある。メロウェダム(100スーダン・ポンド札の絵柄に採用)、改修されたRoseiresダム、Upper Atbaraダムを有するスーダンや、Tekezeダム、ギルベル・ギベ III(Gilbel Gibe III)ダム、大エチオピア・ルネサンスダムを有するエチオピアは代表的な例だ。
コンゴ民主共和国は、2018年に中国とスペインのコンソーシアムとの間でグランド・インガ・ダム計画の契約が完了した。同ダムの発電能力は三峡ダムの2倍(4400万キロワット)、年間総発電量は3倍を見込み、「スーパー三峡ダムプロジェクト」と呼ばれている。
水力発電は「一帯一路」における巨大インフラプロジェクトの一角にすぎない。中国の国営企業はその他にも世界の高速道路、鉄道、空港、港湾、通信、水道などのプロジェクトに積極的に参画している。
大エチオピア・ルネサンスダムVS三峡ダム
大エチオピア・ルネサンスダムと三峡ダムを比較してみよう。同ダムは三峡ダムと同様に重力式コンクリートを用いているが、従来型の柱状ブロック工法(コンクリート冷却時のひび割れを軽減)ではなく、RCD工法(面状工法の一種)を採用した。
堤高(ダムの高さ)180m、堤頂長(ダムの幅)2335mの三峡ダムに対し、大エチオピア・ルネサンスダムは堤高170m、堤頂長1800mと下回るが、湛水面積(貯水池の面積)は1800平方キロメートルと、三峡ダムの1100平方キロメートルを上回る。
発電量は670万キロワットと三峡ダムの2250万キロワットには遠く及ばないが、それでもアフリカ最大の発電量を誇る。送電設備も含めた工事の発注費用は48億ドル(約4800億円)で、ダム単体で300億ドルかけた三峡ダムより低コストであり、送電設備を含めた1キロワットあたりのコストで比較すれば三峡ダムの半分におさまる。
魅力的な価格と大規模融資で無数の契約をとりつけてきた中国だが、それら「三峡ダムプロジェクト」の多くは経済的利益に乏しい投資であることを意味する。
これは、重要な問いを突きつける。なぜ海外のダム水力発電におけるキロワットあたりのコストは、中国国内のものよりも格段に低いのか。
「大国の重器」
中共トップの習近平が我々にヒントを与えてくれるかもしれない。習近平は2018年、三峡ダムを視察した際に同ダムを「大国の重器」と呼び、「真の大国の重器は、我が国がしっかり掌握しなければならない」との言葉を残した。
中共は巨大なダム建設プロジェクトを最重要インフラの一つとみなし、それを国家の生命線として掌握してきた。それを自国だけでなく、海外でも進めているのである。
しかし、中共が「大国の重器」の掌握を叫ぶなら、「一帯一路」構想で支援してきた国々も将来同様に彼らの「大国の重器」を自国のコントロール下に置きたいと思うようになるだろう。その時までにダムプロジェクトの融資を担ってきた中国の国営銀行が投資を回収できるかどうかは、大きな疑問である。















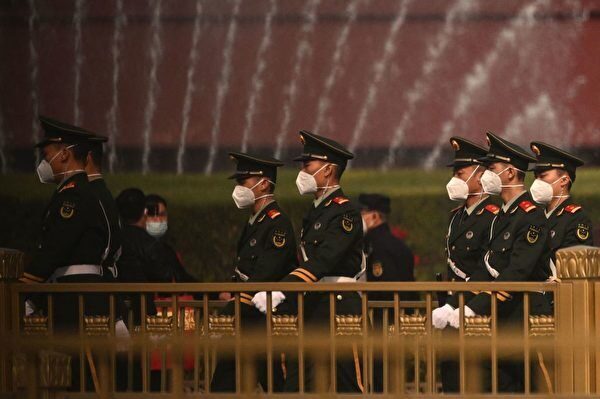
 ご友人は無料で閲覧できます
ご友人は無料で閲覧できます Line
Line Telegram
Telegram














ご利用上の不明点は ヘルプセンター にお問い合わせください。