中国は2000年以降、臓器移植ツーリズムの中心地となっている。1999年には160か所だった臓器移植機関が2005年には600か所以上に増加し、年間6万件以上の移植手術が行われているとされる。しかし、中国の文化的背景から臓器提供率は世界最低レベルである。
中国共産党(以下、中共)はかつて、移植臓器の多くが死刑囚由来であると説明していたが、2015年に死刑囚からの臓器使用を停止し、民間ドナーに依存すると発表した。それでも、提供者数と移植件数の間に大きな乖離があり、出所不明の臓器が存在する可能性が指摘されている。国際社会では、人権団体がウイグル族、法輪功学習者、地下教会信者などの良心の囚人からの強制臓器摘出を非難している。
イタリア、スペイン、台湾など複数の国は、臓器ツーリズムを規制する法律を導入している。台湾国際臓器移植を考える協会の王舒眉理事長に、台湾の取り組みと日本への提案を聞いた。

──台湾で臓器ツーリズムを禁止する取り組みの中で、最も困難だった課題は何か
「法制化が最も困難だった。私たちの協会は、これまでに2度、立法を推進してきた。最初は2015年であり、その際には『人体臓器移植条例』の改正を行った。
シンポジウムでも触れられたように、海外で移植を受けた者に対して登録を義務づけた。帰国後、適切な登録を行わなかった場合、免疫抑制薬は健康保険の適用外となる。
もう一つ重要なのは、『臓器移植において売買があってはならない』と法律で明確に規定した点である。仮に売買が行われた場合、それは刑事犯罪と見なされる。
ただし、当時の法改正は、海外での移植行為自体を直接禁止するものではなかった。違法な移植をしてはならないとは定められていたが、その具体的な執行のあり方には課題が残っていた。
法案自体は比較的スムーズに可決され、台湾では超党派の支持を得た。その後、台湾の患者が海外で移植を受けたデータが確認された。依然として問題は存在している。なぜなら、当時の法律は臓器の売買行為のみを規制していたからだ。患者が海外で移植を受けても、金銭のやり取りや売買の事実を明らかにしない場合、調査を行うことは事実上不可能だった。
2022年、私たちは新たに『生体臓器収奪の防止および取り締まりに関する法案』の推進を開始した。この法案はすでに一度可決されており、2024年5月には台湾の立法院において第一読会を通過している。
一方で、2024年には立法院の選挙が行われ、『会期不継続の原則』により、会期内に議決されなかった法案は次期国会に引き継がれない。そのため、再び法案を提案する必要が生じた。2回目の提案では、超党派の議員が共同で法案を提出し、3つの主要政党に所属する立法委員らが共同提案者となった。さらに、30人を超える議員が共同提出者として署名し、今年1月には再び第一読会を通過した」
台湾の立法院(国会)では、法律案を成立させるために「三読会制」という3段階の審議手続きを行う仕組みが採用されている。第一読会(第1読)は法案の基本的な趣旨や目的を審査する段階で、委員会に付託されるかどうかを決定する。
──日本では、違法な臓器ツーリズムを規制する立法の動きがまだあまり見られない。台湾がこの分野で先行している国として、日本に対してどのような提案があるか?
「まず重要なのは、国民一人ひとりが生体臓器収奪の問題を理解することである。台湾で法案を推進した当初、二読に入ろうとした段階で、立法院の司法および法制委員会の召集委員が非常に強く支援してくれた。
しかし委員は、法案推進の過程において『民間の声がまだ十分に大きくない』と指摘した。立法委員(議員)は国民によって選出されるため、何よりも国民の意見を重視する。ゆえに、より多くの市民がこの問題を正しく認識する必要があるという助言を受けた。
委員の提案は、民間での教育活動を通じて理解を広げることで、中央での法案推進がより容易になるというものだった。
昨年、台湾では『国家の臓器』という映画(臓器収奪をテーマにするドキュメンタリー映画)が上映され、大きな反響を呼んだ。上映初期には、台湾北中南部の複数の映画館が(中国からの)脅迫状を受け、上映が中止されるという事態が発生した。しかしその後、この事実がメディアにより報じられると、『なぜ台湾で一本の映画さえ自由に観られないのか』と多くの議員が声を上げた。
これをきっかけに、映画は議会主催のもとで上映され、多くの人々が臓器収奪の実態を認識するに至った。以前は報道が少なかったが、現在はソーシャルメディアの発達により、若者たちが自ら情報を拡散している。その結果、台湾国内ではこの映画を観ようとする人々が急増し、大きな市民の声へとつながった。
──法制化を推進する過程において、中国共産党による妨害などの行為を受けたか。
「全体としては、かなり順調だったと言える。とはいえ、中共による浸透工作は各国に対して一貫して行われている。政府機関であれ、立法委員や行政官であれ、その周囲に中共の影響が及んでいない者がいるとは考えにくい。おそらく何らかの形で浸透されていると見てよい。
ただし、今回台湾で『生体臓器収奪の防止及び取り締まりに関する法案』を推進するうえで特に印象的だったのは、台湾の人々は善悪の判断が非常に明確であるという点である。たとえ親中派であっても、「生きた人間から臓器を強制的に摘出する」という行為については、誰もが「それは明らかに誤っている」と認識する。
ゆえに、多くの台湾人は正しいことを実行しようとする意志を強く持っている。たとえば、ある政党について中共寄りだという印象を持っていたが、その政党の議員の多くはこの問題を聞いた際に『これは議論の余地もなく“誤り”だ』と明言した。『もしこの法案に反対する者がいれば、メディアで公表すればよい』と語る議員さえいた。
もちろん、すべての人がそうとは言えない。一部の立法委員はアポイントの取得すら困難であり、この問題に正面から向き合おうとしない者もいる。しかし、実際に会って話ができた議員の多くは、この件については「人を殺して臓器を取ることなど、議論の余地はない」と明確に述べてくれた。結局のところ、正しい道を選ぶか、誤った道を選ぶかの問題にすぎない。
──中共が映画『国家の臓器』の上映する会場に爆破予告をしたり、さまざまな妨害をしているが、逆に関心が高まり、上映回数も増えたと聞く。本来多くの人が知らなかった問題が、中共の動きによって逆に注目を集めてしまったのではないか。
「その通りだ。中共が行動を起こすほどに、社会の反発は一層強まっている。
たとえば、台湾の歌手Tankは先天性の心筋肥大により心不全と肝不全を併発していた。昨年、中国側から「心臓と肝臓のドナーが見つかった」と連絡を受け、中国で心肝同時移植を受けた。当初はこの事実を多くの人が知らなかったが、移植手術後に中共メディアがこれを大々的に報道した。
彼らは「台湾では臓器を手に入れられなかったが、我々がその問題を解決した」と宣伝したかったのだろう。しかし、その結果として、台湾社会では「なぜ短期間で心臓と肝臓の両方が手に入ったのか?」と疑問の声が上がった。
医師たちも説明に加わり、「心肝同時移植は極めて稀であり、順番待ちのシステム上、短期間に2つの臓器が同時に得られることは通常ない」と指摘した。Tankは先天性の心疾患に起因して肝不全を発症していたため、通常はまず心臓移植を行い、その後に肝機能の回復を観察するのが一般的である。したがって、通常は心肝同時移植は実施されない。
──手術の難易度もかなり高い。
「まさにその通りだ。そのため、この件は社会的に大きな議論を呼び、広く話題となった」
──ところで、先生は医師であるが、医師から見て今と10〜15年前を比べて、臓器移植の待機期間に変化はあるか。
「台湾の場合、現在も過去も平均して2〜3年程度であり、大きな変化はない。臓器不足は世界的な問題であり、どの国も課題を抱えている。ただし、それが理由で違法な手段に頼るべきではない」
──中国や台湾では「遺体をきれいに保ちたい」という文化があり、欧米に比べて臓器提供が進みにくいのではないか。
「確かに過去にはそのような価値観が強かった。台湾でも『遺体を損なわずそのまま残したい』と考える文化的傾向があった。しかし、時代の変化とともに意識も変わってきた。
現在では政府がさまざまな方法で臓器提供を促進するキャンペーンを行っており、提供者やその家族への感謝を示す取り組みも広がっている。たとえば、家族が過去に臓器提供を行った場合、将来その家族が移植を必要とした際に、移植待機リストにおいて優先される制度なども存在する。こうした制度や文化的取り組みによって、臓器提供は徐々に進展していると実感している」















 ご友人は無料で閲覧できます
ご友人は無料で閲覧できます Line
Line Telegram
Telegram

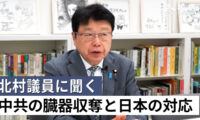






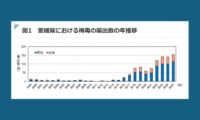




ご利用上の不明点は ヘルプセンター にお問い合わせください。