参政党の吉川りな衆議院議員は、令和7年6月4日付で「太陽光パネルの災害リスクと情報提供の不備に関する質問主意書」を政府に提出した。主意書では、太陽光パネルの設置拡大に伴う国民負担の増加や、災害時のリスク、そして情報提供の現状について、政府の対応を問いただしている。
吉川議員は、再生可能エネルギーの導入推進によって、電気料金に上乗せされる再生可能エネルギー賦課金の国民負担が累計約23兆円に達し、令和7年度には年間3兆円を超える見込みであることを指摘した。標準家庭でも年額約1万9千円の負担となるとされ、こうした巨額の負担が国内産業や国民生活に十分還元されていないとの批判が高まっていると述べている。
また、日本は地震や水害など災害が多い国であり、南海トラフ地震の発生も予想されている。その中で、太陽光パネルの設置後に発生しうる水没や破損時の感電・火災リスクについて、住民向けの情報提供や対策が十分とは言えないと吉川議員は指摘した。実際、令和6年の能登半島地震では、斜面設置型のメガソーラーが崩落して道路を塞ぐ事例や、倒壊建物に設置された太陽光パネルの発火リスクを設置者が把握していなかった事例が報告されている。これらの事例から、災害時の安全確保とリスク情報の周知が課題であることが明らかになった。
地方自治体からも、破損パネルによる感電、火災、有害物質のリスクとその対処法について、国民への周知が不十分であるとの意見書が出されている。しかし、こうした教訓が制度面に十分反映されているとは言い難い。たとえば、東京都で新築住宅へのパネル設置義務化条例が施行されているが、公式ウェブサイトには経年劣化後の交換費用や廃棄時の有害物質処理費用、災害時の消火困難や水没時の感電リスクなどへの注意喚起や具体的な対応策を記した文書は確認できず、住民への安全対策の指導も限定的であると主張している。
総務省消防庁は平成25年3月、太陽光発電システムを設置した住宅に関する感電・落下リスクについて、各都道府県を通じて市町村等に周知するよう事務連絡を発出している。しかし、こうしたリスク情報は消防機関内にとどまり、設置者や住民に十分伝わっていないことが懸念されている。
7つの質問
吉川議員は、こうした現状を踏まえ、質問主意書には七つの具体的な質問が盛り込まれた。
第一に、太陽光発電の設置による災害リスクや廃棄費用について国民がどれだけ知っているか、政府が全国的な調査を行っているかを尋ね、もし行っていなければ新たな調査を実施すべきではないかと問うた。
第二に、住宅用太陽光パネルの営業担当者が災害リスクや廃棄・買い替えについて十分に理解せず設置を勧めていた事例を踏まえ、政府がリスク情報の周知徹底を図るべきではないかと求めている。
第三に、地方自治体から太陽光パネルの破損による感電や火災、有害物質などのリスクについて住民への情報提供が不十分との指摘があることを受け、現状の情報提供のあり方を見直す考えがあるかを質問している。
第四に、多くの自治体が住民向けリスク情報を十分に発信できていない現状を踏まえ、政府が自治体向けのモデル文書作成や設置業者による説明の制度化など、支援策を講じる考えがあるかを尋ねている。
第五に、令和六年の能登半島地震で明らかになった斜面設置型メガソーラーの崩落や倒壊建物に設置された太陽光パネルの発火リスクなどを踏まえ、こうした災害時の安全確保やリスク情報提供について、政府がどのような教訓を得て今後の対応にどう反映させるのかを問うた。
第六に、太陽光パネルの経年劣化後の交換や廃棄にかかる費用について、設置者や住宅購入者に対する周知や説明が正しく行われていると政府が認識しているかを確認している。
第七に、固定価格買取制度のもとで売電事業者の倒産や廃業が実際に起きている現状を踏まえ、小規模や個人の設置者による設備廃棄費用が将来的に国民負担とならないよう、積立制度の強化や対象拡大など、さらなる対策を講じるべきではないかと提案している。
今後の政府の対応が注目される。


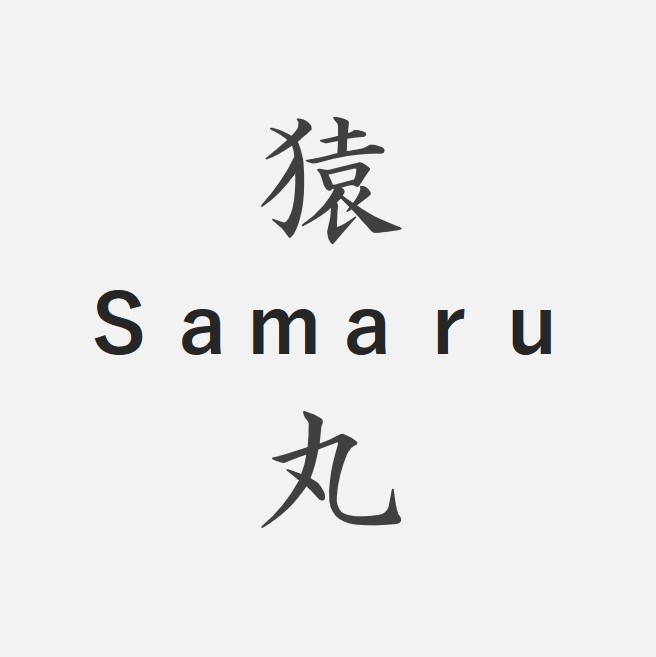












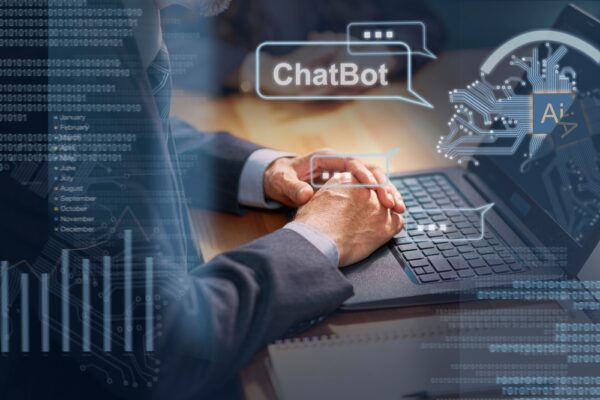
 ご友人は無料で閲覧できます
ご友人は無料で閲覧できます Line
Line Telegram
Telegram














ご利用上の不明点は ヘルプセンター にお問い合わせください。