論評
経済分野のさまざまな「専門家」が、日常的に「経済」の状態についてコメントをしている。たとえば、「経済」が何パーセント成長したとか、貿易赤字の拡大が「経済」を脅かしている、といった具合で、論評によれば、「経済」は財やサービスを生産し、それが国民総生産(GNP)と呼ばれ、そして、ひとたび生産された後、次に求められるのは、それをいかにして最も公平に個人へ分配するかということになる。
しかし、「経済」が財やサービスを生産するという見方は妥当なのだろうか。分配されるべき「国民総生産」というものは、実際に存在するのだろうか。そもそも、論者たちが用いる「経済」という言葉は、何を指しているのか。それは、実体をもつ存在といえるのか。
自由市場においては、財やサービスが全体として生産され、単一の最高指導者によって統括されるものではなく、各個人は、自身の生産と消費に関心を向けており、それぞれが独自に活動するものである。したがって、自由な環境において「総生産」という表現を用いるこ政府の統計調査者が、最終的な商品やサービスの価値を一括りにすることで、GDP統計や他の経済指標を通じて「経済」という概念を具体化しているのだ。こうして「経済」がさまざまな経済指標によって具体化されると、政策立案者は「専門家」が望ましいと考える成長経路に沿って「経済」を導くことができるように見える。
一度、GDPなどの様々な経済指標によって「経済」が表現されると、それは政府の計画立案者によって描かれた成長路線に沿って進むことが期待される。そして、成長率が想定よりも下回ると、政府や中央銀行の政策担当者は、財政政策や金融政策を通じて「経済」に適切な刺激を与えるよう求められ、時に政府関係者は、「経済」が過熱している(つまり「成長が速すぎる」)と警告し、その場合には過熱を防ぐことが自らの責務であると主張する。
しかし、「いわゆる「経済」は、個人の選択や行動と独立した、独自の生命を持つような存在ではないということを理解しなければならない。さらに、「ジャガイモ」と「トマト」を単純に足し合わせるような計算はできないから、我々は実質総生産を算出ことすらできない。
政府の統計調査者ら自身も、こうした指標が現実を完全に反映しているわけではないと認めている。アメリカ商務省経済分析局(BEA)のJ・スティーブン・ランデフェルド氏とロバート・P・パーカー氏は、次のように述べた。
「特に重要なのは、実質GDPが分析上の概念であるということを理屈上で認識することだ。実質という名がついていても、実質GDPは実際に観察されたり、直接収集されたりするような『実在する』ものではではない。名目GDPも同様に、経済における最終的な商品やサービスの実際の支出を合計して直接把握できるわけではない。たとえば、リンゴやオレンジの数量は個別に集計できるが、それらを足して「果物」の総生産量を求めることはできない」
このことはつまり、政府の統計調査者が作成するさまざまなマクロ経済指標は、現実から切り離されているということを意味する。ゆえに、こうした架空の指標に基づいて、存在しない「経済」というものを操作しようとする政策は、個人の幸福に損害を与える結果になる。
制限された市場環境とマクロ経済データ
困難な経済環境で成功するためには、起業家は中央銀行や政府の政策に影響される現況に適応しようとする。ビジネスマンは、GDPなどの経済指標の変化を無視できない。なぜなら、政府や中央銀行の当局者は、これらの指標の変化に対し、財政や金融政策で反応するからだ。例えば、たとえば、GDPの上昇を受けて中央銀行が金融引き締めに動くと予想される場合、企業家はその影響を考慮せざるを得ない。
このような環境では、企業家たちは、各種経済指標が政策当局にどう解釈されるか、そしてその政策が自社の事業環境にどのように影響するかを予測しながら行動する必要がある。政府はさまざまな経済指標を構築するため、企業からデータを収集するが、企業はこれに対応するため、労力を割かなければならない。こうした経済指標の構築は、経済学者や数学、統計の専門家に雇用機会を生み出す。これらの専門家は、経済データを集めるだけでなく、データを解釈し、企業に助言を提供する。
オーストリア学派の中心人物ミーゼスに学んだマレー・ロスバード氏は、
「個々の消費者は、日常生活で統計をほとんど必要としない。広告や友人からの情報、自身の経験を通じて、身の回りの市場で何が起きているかを把握しているからだ。これは企業にも当てはまる。ビジネスマンは、自身が関わる市場を見極め、購入する物の価格を決め、仕入れ価格や販売価格を判断し、原価計算を通じてコストを見積もるなど、さまざまな実務を行う必要がある」
「経済」に関する統計は 自由市場の企業家に役立つのか?
政府や中央銀行の干渉がない自由市場環境において、さまざまな経済指標を構築・公表することには、あまり意味がない。この種の情報は、企業家にとってほとんど実用性を持たないからである。たとえば、GDP成長率に関する情報は、自由市場において企業家にとってどのような役に立つのか。GDPが何パーセント増加したという情報が、企業経営の成功にどうつながるのか。それとも、国の国際収支が赤字または黒字に転じたというデータは、事業判断に何らかの有効性を持つのか。
自由市場経済では、企業が成功するには消費者の要望に応えなければならない。消費者のニーズに注目するということは、企業家がその目的に、最も適した生産体制を築かなければならないことを意味する。マクロ経済指標に関する情報は、こうした判断に対して、ほとんど意味を持たない。企業家にとって本当に必要なのは、一般的なマクロ情報ではなく、特定の製品または製品群に対する消費者需要に関する具体的な情報だ。政府が提供するマクロ経済指標は、企業家にとってあまり役立たない。
企業家は、自らのビジネスに必要な情報ネットワークを構築する必要がある。どのような情報が事業の成功に必要であるかを最もよく知っているのは、他ならぬその企業家自身である。消費者の需要を正しく見極めれば、企業家は利益を得ることができる。一方で、判断を誤れば損失を被る。利益と損失の仕組みは、消費者の優先順位を読み違えた企業を退場させ、正確な評価を行った企業に報いる働きを持つ。このプロセスによって、消費者の要求に十分な注意を払わない企業家からは資源が引き上げられることになる。
20世紀の自由主義経済思想における最も重要な人物の一人、ルートヴィヒ・フォン・ミーゼスは「利益と損失は、生産活動の方向を消費者の最も切実な需要に適応させることに成功したか、あるいは失敗したかによって生じるのだ」と述べた。
結論
政府の統計者が作成するマクロ経済データは、「経済」という抽象的な概念をあたかも現実に存在するかのように見せた。これによって、政府や中央銀行の当局者は、専門知識を駆使して「経済」を安定成長へと導けると考えている。しかし、実際には、この導きは経済の不安定さ、物価の上昇、好況と不況の繰り返しという問題、そして富を生み出す力の衰えを引き起こすのである。















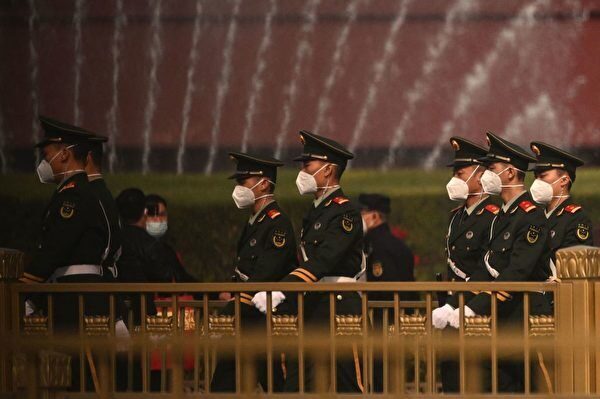
 ご友人は無料で閲覧できます
ご友人は無料で閲覧できます Line
Line Telegram
Telegram














ご利用上の不明点は ヘルプセンター にお問い合わせください。