自民党は6日、党本部で「氏制度のあり方に関する検討ワーキングチーム」を開催し、選択的夫婦別姓制度の導入を提言した経団連の担当者から意見を聴いた。この会合には約60人の議員が出席し、経団連は1996年の法制審議会の案を評価し、早期の制度導入を求めた。日本経済新聞やNHKなどが報じた。
経団連の担当者は、女性の活躍が広がる中で、海外では戸籍上の姓とビジネスで使う旧姓が異なる場合、トラブルが生じることがあると指摘。また、姓を変えることへの心理的な抵抗もあると述べたという。1996年の法制審議会の案では、選択的夫婦別姓制度を導入し、子どもの姓は結婚の際に夫か妻のどちらの姓に統一するか決めることが提案されている。
会合では、議員から「姓の選択は人権の問題であり、解決に向けて取り組むべきだ」と賛同する意見が出た一方で、「旧姓の通称使用が広がることで状況は改善されてきているので、経団連も通称使用の拡大により取り組んでもらいたい」という指摘もあったという。自民党の作業チームは、今後も有識者などから意見を広く聴き、制度のあり方の検討を続ける予定だという。
DEIを推進する経団連
経団連は、DEI(Diversity, Equity, Inclusion)を推奨しているとしている。DEIとは多様性、公平性、包括性を指し、経団連はこれを企業の存続やイノベーションの源泉として重要視しているという。特に、女性のエンパワーメントを通じてDEIを推進し、企業の事業変革や価値向上を図る活動を展開している。また、DEIに関連して「選択的夫婦別姓制度の導入」も、多様性を推進するための重要な要素として提言している。経団連はこれを「選択肢のある社会の実現を目指して」と題した提言書としてウェブサイトに掲載している。
アメリカでのDEI
アメリカでは、DEIに対する見解は分かれている。最近の動きとして、トランプ政権はDEIを「違法で非道徳的」と批判し、連邦政府内でのDEIプログラムの廃止を目指す大統領令に署名した。
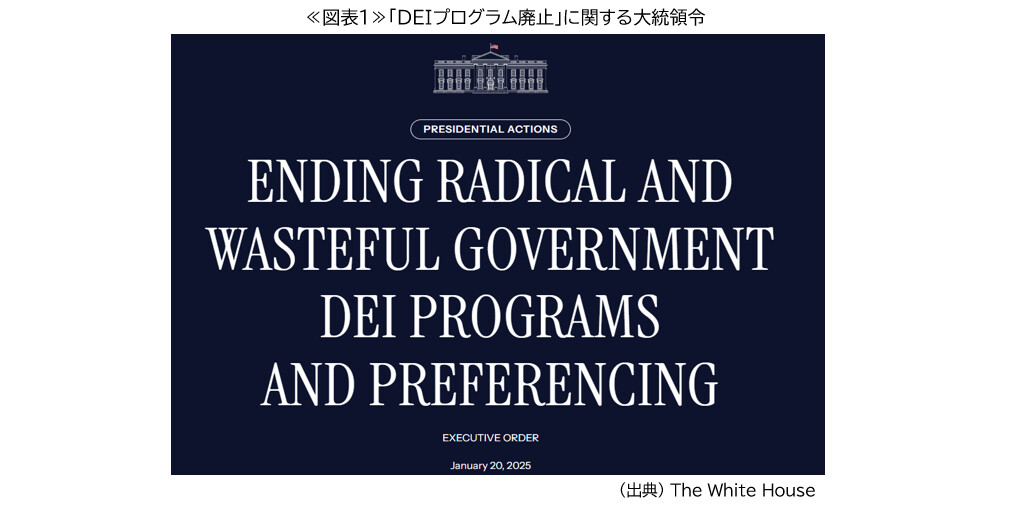
大統領令のタイトルは「過激で無駄な政府の多様性・公平性・包摂性(DEI)プログラムを終了し、優遇を廃止する(Ending radical and wasteful goverment DEI programs and preferencing)」だ。前政権が強制したDEIを「過激で無駄なもの」と批判している。
一方で、多くの企業や団体はこれまでDEIを重要視し、多様性と公平性を推進するために取り組んできた。特に、2020年のジョージ・フロイド氏の死後、企業や社会全体でDEIへの関心が高まり、多くの企業がDEIプログラムを導入した。しかし、最近では一部の企業でDEIプログラムを縮小する動きが見られている。
DEIが「違法で非道徳的」とされる理由
DEI(多様性、公平性、包括性)が「違法で非道徳的」とされる理由は、主に以下の点に基づいている。
逆差別の懸念
DEIプログラムが有色人種や女性などの特定のグループを優遇することで、他のグループに対する不公平感を生み出す可能性があると指摘されている。特に、白人男性などが不当に扱われるのではないかという懸念が強い。
能力主義との衝突
DEI施策が採用や昇進において「多様性」を優先することで、純粋な能力や実績よりも人種や性別が重視されることが批判されている。
強制的な実施
企業や政府機関がDEIを強制的に推進することが、思想や価値観の押し付けと見なされることがある。
組織の効率性への影響
DEIプログラムが行き過ぎると、企業や組織の効率性や競争力が低下する可能性があると指摘されている。
これらの理由から、特に保守派や一部の企業ではDEIが批判されている。フロリダ州では「Stop WOKE Act」として、特定のDEIプログラムを人種・性別差別として禁止する法律が施行されている。
DEIのルーツ
DEIのルーツは1960年代のアメリカにおける公民権運動に遡る。特に、1964年の公民権法の施行以降、企業は差別を避けるために多様性を受け入れる姿勢を見せ始めた。
その後、1990年代には多様性の受容が組織に利益をもたらすと認識されるようになり、D&I(Diversity & Inclusion)という言葉が登場した。さらに、2015年以降、SDGs(持続可能な開発目標)が打ち出されると、Googleなどの企業がD&Iに「Equity(公平性)」を加えたDEIを推進するようになった。
2020年のジョージ・フロイド事件をきっかけに、DEIは社会的責任の重要な徳目としてさらに注目されるようになった。この事件は、アメリカ全域で「黒人の命も大切だ(Black Lives Matter)」運動を広げ、多様性と包容性を重視する社会的潮流を加速させた。
共産主義的なグローバリズムの危険
夫婦別姓について、「世界ではその制度がほとんどであり、日本は遅れている」とか、「ビジネス上の不便」「平等の問題」などなど、いろいろと理由が挙げられている。しかし、この制度導入が共産主義的な目的を達成させるための手段であるのかどうかを国家として検証することについては、あまり議論が聞こえてこない。ここで大紀元の社説「悪魔が世界を統治している」第十七章「序文」の文章の一部を紹介したい。
共産邪霊が操るグローバル化は、「グローバリズム」とも称される。それは驚異的なスピードでさまざまな分野に浸透し、あらゆる手段やルートを通じて世界中に触手を伸ばしている。当章はグローバリズムの経済、政治、文化的な側面を検証する。
この3つの側面が一つに融合し、グローバル化という世俗のイデオロギーが形成された。このイデオロギーは異なる時期にさまざまな外見を呈し、時には矛盾する内容を利用する。しかし、基本的には、このグローバル化は共産主義と非常に似通っている。グローバル化は無神論と物質主義を信奉し、豊かで平等な、搾取、抑圧、差別のない社会を描写する。それは世界政府によって管理されるユートピアである。
また、グローバル化は、神への信仰とその価値観を理念とする全ての民族の伝統文化を排斥する。最近、このイデオロギーは、ますます「ポリティカル・コレクトネス」(政治的に正しい言葉遣い)「社会正義」「価値中立性」「絶対平等主義」という左翼の思想をあらわにしている。これが、グローバル化のイデオロギーである。
各国それぞれに独自の文化が存在するが、それらは伝統的に、普遍的価値観の上に成り立っている。それぞれの民族にとって、国家の主権と伝統文化は国家遺産や自決権を有するための要であり、それによって共産主義を含む強大な外部勢力から自らを守ることができる。
世界の中で日本だけが違うとしても、それが弱点であるとは限らない。伝統文化に守られた強みである可能性もあるだろう。「グローバリズムに飲み込まれ共産化が進めば、いとも簡単に私有財産は廃止、国家、民族、伝統文化は消滅する」と大紀元の社説は述べている。
選択的夫婦別姓制度の導入をめぐる議論は、経団連からの早期実現を求める提言で活発化し注目されている。自民党内でも慎重派と推進派の意見が分かれている。

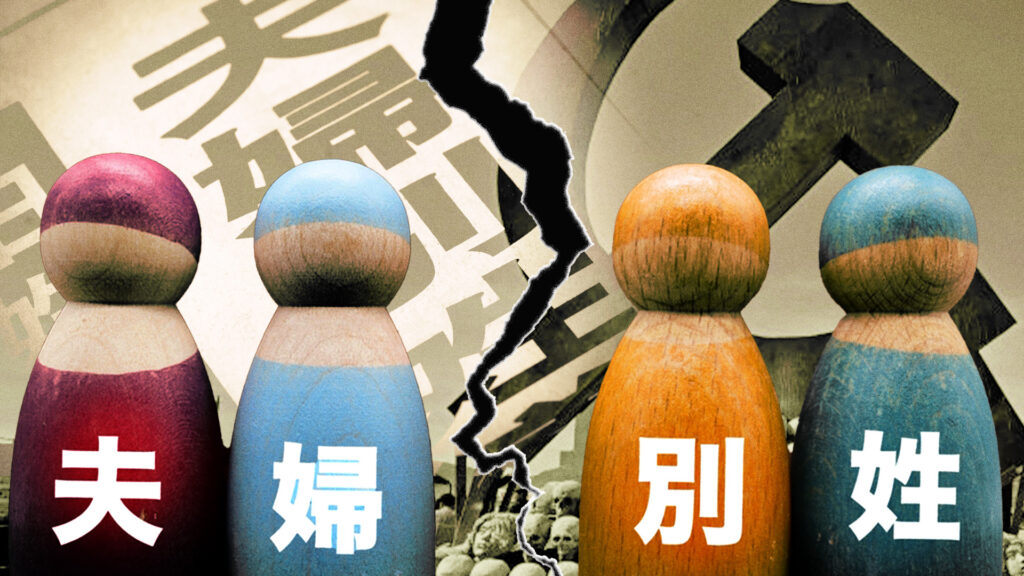
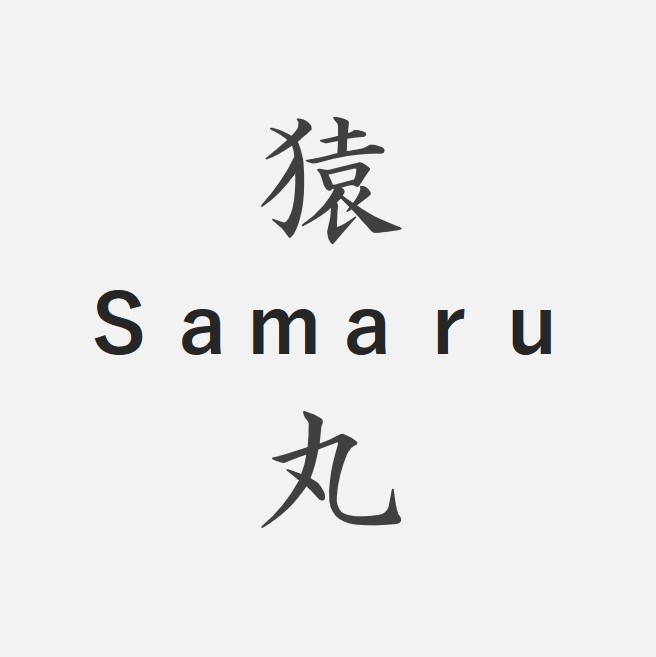













 ご友人は無料で閲覧できます
ご友人は無料で閲覧できます Line
Line Telegram
Telegram














ご利用上の不明点は ヘルプセンター にお問い合わせください。