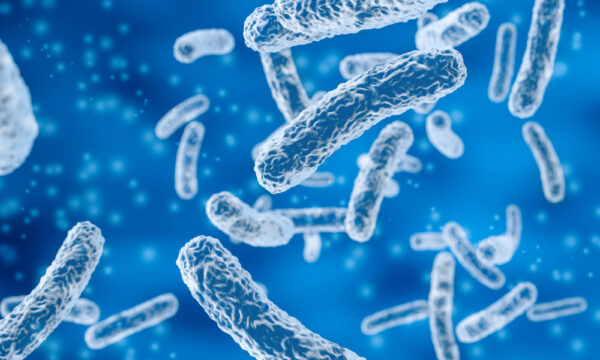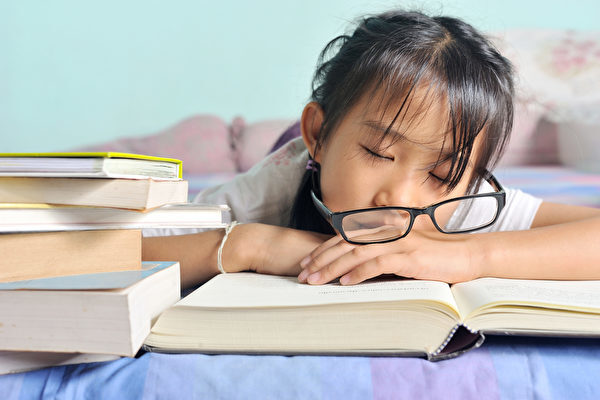がん予防の味方! ブロッコリーを食生活に取り入れる簡単なコツ
がん予防に効果的なブロッコリー。栄養豊富なこの野菜の秘密や、美味しく取り入れるレシピ、調理法のコツを紹介します。健康的な生活習慣にも役立つ情報満載です。
食生活でがんリスクを減らす
食生活の改善でがんリスクを減少!野菜や果物を増やし、調理法に工夫を凝らすことで、健康を守る方法を具体的に解説します。
突然のめまいとしびれ、脳卒中のサインに注意
脳卒中の予防と早期発見が重要なテーマです。台湾の中医学医師、董燕玲氏が紹介する脳卒中の9つの警告サインや予防のための食事療法には、ニンニクやシイタケなど身近な食品が含まれています。また、日常的に取り入れられるツボ押しや天麻茶も効果的です。この記事では、脳卒中を防ぐための具体的な方法と早期対応について解説しています。
楽器演奏で認知症予防?研究が明かすその効果
音楽が認知症予防に効果的!新しい研究で、楽器演奏や歌うことが脳の健康を守る鍵になる可能性が示されました。日常生活に取り入れるだけで、あなたの脳を若々しく保つ方法とは?
ニンニクは「がん予防の王様」
「がん予防の王様」として知られるニンニク。その驚くべき健康効果が明らかに。古代から愛用されてきたこの万能食材が、どのように私たちの健康を守ってくれるのか、ぜひご一読ください。
日本で流行「人食いバクテリア」 専門家が予防のポイントを解説
夏の観光シーズンに増える「人食いバクテリア」感染症のリスクに注意。特に高齢者や免疫力が低下している人は感染リスクが高まります。症状や予防方法を知って、安心して夏を楽しむための対策を学びましょう。
ケトジェニック食とヴィーガン食で免疫系がどう変わる?
ケトジェニック・ダイエットとビーガン・ダイエットが、免疫系にどのように影響を与えるのかを解説した最新の研究が紹介されています。それぞれの食事法が病気の予防や健康維持に与える効果について詳しく知りたい方におすすめの内容です。
認知症の半数は防げる? ランセット委員会の新報告
認知症リスクは避けられないものと思われがちですが、最新の研究では、視力の低下や高コレステロールなど、14のリスク要因に対処することで、発症を遅らせる可能性があるとされています。
「チャーハン症候群」とは?微生物専門家が語る食中毒と予防法
「チャーハン症候群」と呼ばれる食中毒が再び注目されています。常温で放置された食品によるバクテリア「バチルス・セレウス」が原因で、最悪の場合、命に関わることも。この症候群のリスクを避けるため、食品保存の基本を学びましょう。
小児の原因不明の突然死は、発作との関連が疑われる
原因不明の小児突然死に関する新たな研究で、発作との関連が示唆されています。幼い命を守るために、最新の知見と予防策を知ることは大切です。ぜひお読みください。
高齢者のビタミンD不足が虫歯リスクを増加?
最新研究によると、ビタミンD不足の高齢者は虫歯リスクが44%増加することが判明しました。ビタミンDは歯のエナメル質形成に不可欠であり、不足すると虫歯や歯周病のリスクが高まります。高齢者の口腔ケアには、適切なビタミンDレベルの維持が重要です。健康な歯を保つために、ビタミンDの摂取を見直しましょう。
1日1本のニンジンががん予防に効果? 最新研究が示す
ニンジンが視力を向上させるだけでなく、がん予防にも効果があることが明らかになりました。ニンジンを食べることでがんリスクが10~20%低下することが示されています。週に5回、合計400gのニンジンを摂取することが推奨されています。おいしく健康的な食生活にニンジンを取り入れてみませんか?
毎日のプルーンで骨を強く! 高齢女性に嬉しい効果
ペンシルベニア州立大学の研究で、毎日プルーンを食べると閉経後女性の骨量減少が遅れ、骨折リスクが軽減する可能性があることが分かりました。プルーンの効果に注目です。
コーヒー好き必見! ベストな飲み方と健康効果11選
コーヒーには抗酸化物質であるクロロゲン酸とカフェストールが含まれており、これらは炎症を軽減し、心血管疾患や癌を予防するのに役立ちます。台湾の著名な乳がん専門医であり、「一杯のコーヒーで全ての病気を予防する」の著者である張慶堅医師は、コーヒーの健康効果とベストな飲み方について説明しています。
脳卒中リスクが4.5倍に? 微小プラスチックの脅威
研究結果によれば、マイクロプラスチックは至る所に存在しており、心臓の動脈硬化のプラーク内にも見られることが明らかになっています。これは心臓疾患による健康リスクを大幅に高める要因となります。
胃がんには多くの誘因がある 胃を守るためのヒント
胃癌には多くの種類があり、腺癌、リンパ腫、悪性肉腫などが含まれますが、ほとんどの胃癌は胃粘膜の腺体細胞から発生する腺癌です。臨床統計によれば、胃癌は発病率と致死率が比較的高いがんの一種であり、初期段階では症状がほとんどないため、診断が遅れやすいとされています。しかし、胃を効果的に保護し、胃癌を予防する方法は何でしょうか?
睡眠中の突然死ーその原因、見分けるサイン、予防策
中国のAI企業センスタイムの創業者で、過去に米国から制裁を受けた湯暁鴎氏が、昨年12月15日に睡眠中に亡くなりました。彼は55歳でした。睡眠中に突然死する原因は様々です。本記事では、睡眠中に死亡する可能性のある原因、リスクが高い人々、そして予防策について解説します。
新アプローチ:「ワキガ」の悪臭を制御する方法
腋臭症は病気ではありませんが、脇から異臭が発生することは非常に恥ずかしいです。そのため、台湾の専門医が大紀元の読者に対して予防と治療方法を提案しています。
アブラナ科野菜:脳卒中の予防と回復に役立つか
アブラナ科の野菜は、その脳卒中の予防効果で知られていますが、研究者は、一部の人気が低い野菜が脳卒中のリスクを低減し、さらには脳卒中症状を逆転させるのに役立つ可能性があることを発見しました。
身近の食べ物ががん予防?!研究で支持された13の食材
食品とがんとの関係は、昔から切っても切れないものでした。実際、アメリカがん協会によると、「人は食べたものでできている」とのことです。結果、抗がん性の食品は、がんの予防と治療として多大な影響があるということになります。
楽しく生活して認知症予防:20年の先行きを変える方法
近年の研究では、アルツハイマー病患者は症状が現れる数年前から脳に病変が生じ始める可能性があることが示されています。したがって、認知症や行動の予防は老化してからでは遅すぎます。日本の専門家は、40代から予防策を取ることを提案しています。
乳酸菌でCOVID-19対策!感染予防と症状緩和の可能性
新型コロナウイルス(COVID-19)が世界中に広がり続けている。最近の研究で、プロバイオティクスは、新型コロナワクチンを接種していないが、感染者と接触したことのある人の感染リスクと症状を軽減することがわかった。
気づかない5つのアレルギー症状! 医師が教えるアレルギー対策
アレルギーは多くの人々の健康問題となっています。環境中にはさまざまなアレルギー原が存在しますが、日常の健康管理や症状の軽減にはどのような対策を取れば良いでしょうか?
40代からの新常識!代謝力を高める5つの食材
年を重ねるにつれて、特に40歳を過ぎたことにより、以前より多く食べていないにも関わらず太りやすくなることに気づくかもしれません。これは新陳代謝が低下しているためです。食生活を変えて、代謝を向上させる食品を積極的に摂取することで、痩せることができます。
医学専門家がキャベツを推奨!食事前に食べるだけで痩せる科学
痩せられないのは「デブ菌」が多すぎるから?食事前に1つの食品を食べると改善されるかもしれません。日本の多くの著名な医学専門家や医療センターは、糖尿病や肥満の患者にキャベツの摂取を推奨しています。これにより、減量と血糖値の低下が期待できます。
口腔ケアが命をつなぐ!歯磨き習慣が心臓病リスクに影響
口腔衛生を軽んじてはならず、歯磨きは心臓病やがんを含む様々な慢性病との関連が指摘されています。最近の日本の研究によると、就寝前の歯磨きが特に重要で、歯磨きの習慣が心臓病患者の生存率に影響を及ぼしていることが明らかになりました。
研究:植物性の食事はコロナ感染率が低い
新しい研究によると、植物性またはベジタリアンの食事は感染率を最大39%減少させる。この冬、JN.1変異株による感染が急増する。そうした時、食生活を調整したほうがいいかもしれない。
認知症リスクを高める新型コロナウイルス、専門家が予防法を提言
COVID-19(新型コロナウイルス感染症)は、さまざまな方法で脳に影響を及ぼす可能性があります。最新の包括的な研究結果は、COVID-19感染がアルツハイマー病などの神経変性疾患のリスクを増加させ、長期的な認知障害を引き起こす可能性があることを強調しています。
テクノロジーがあなたの視力を奪う スクリーンが与える害とは(3)
幼児の近視が悪化するにつれ、近視をコントロールしたり、マネージメントしたりする方法が盛んになってきています。近視コントロールクリニックは、米国の裕福な地域にも出現しており、中国では一般的になっています。近視コントロールの目的は、この病気で起こる軸方向に伸びる速度を抑えることです。
その方法は、アトロピン点眼薬、多焦点ソフトコンタクトレンズや角膜移矯正レンズ(オルソレンズ)などがあり、夜間を通して装着し、透明な前眼部の形を矯正し、光の入り方を変えて視力回復を助けます。
テクノロジーがあなたの視力を奪う スクリーンが与える害とは(2)
子共の近視の発症が早く、しかも進行性が高いということは、将来的にあまり良い傾向ではありません。11~13歳の子供でも、「強度近視の流行」のリスクが高いのです。 近視になると眼球が引き伸ばされ、この解剖学的変化は不可逆的で、特に後年、深刻な視力障害を引き起こすリスクが高くなります。